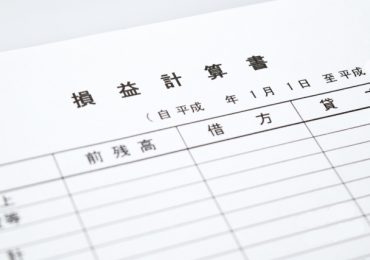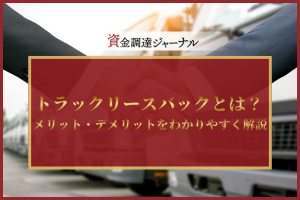決算書を構成する書類には、キャッシュフロー計算書以外に「貸借対照表」と「損益計算書」があり、表示される内容等に違いがあります。
貸借対照表と損益計算書はどちらも「財務三表」と呼ばれる重要な決算書類で、企業の経営状況を示します。
この2つの表から得ることができる情報には明確な違いがあるため、経営分析では貸借対照表と損益計算書それぞれの役割を理解しておくことが大切です。
そこで、貸借対照表と損益計算書とはどのような表なのか、それぞれから確認できる内容や経営分析で活用する方法について説明します。
中小企業経営者向け!

貸借対照表とは

貸借対照表は会社が決算のときに作成する財務諸表(決算書)を構成する書類の1つです。
決算日など、一定の時点において企業が保有する資産や経営資金の調達方法などが一覧で表示されます。
バランスシート(B/S)とも呼ばれのは、企業の保有する資産額と調達した資金額は必ず一致するからです。
- 貸借対照表があらわすこと
- 貸借対照表に表示される内容
- 貸借対照表のポイント
それぞれ説明します。
貸借対照表があらわすこと
企業が保有する資産(プラスの財産)や権利と、負債(マイナスの財産)のバランスをまとめ財務状況をあらわします。
出資・融資などどのように資金を調達し、何にお金を使ったのかという財政状況をまとめたものです。
貸借対照表に表示される内容
貸借対照表は、会社の所有する財産や負債をまとめた表であり、
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部
の3つに分かれ、左側には資産、右側には負債と純資産が表示されます。
それぞれに表示される内容を説明します。
資産の部
「資産の部」には、現金・預金・土地・建物など、会社が所有または保有する財産について記載されます。
販売したもののその代金をまだ受け取っていない売掛金も、資産の部に含まれます。
負債の部
「負債の部」には、たとえば銀行から融資を受けたときの借入れや、すでに納品されているもののまだその代金を支払っていない「買掛金」などが表示されます。
純資産の部
「純資産の部」には、会社設立時に準備されていたお金や株主からの出資金(資本金)、それまでの利益で蓄積された分などが記載されます。
貸借対照表のポイント
貸借対照表は、以下の計算式で成立します。
| 資産 = 負債 + 純資産 |
左側はお金の使い道、右側には資金を調達した方法が示されます。
お金の出どころとそれによる資産を明らかにすることができ、両者に不明な差異はないか確認することができます。
貸借対照表を使った経営分析は、資産と資金の構成比から経営の安定性や支払能力が評価されます。
「資産」や「純資産」の規模が同じであるとき、「負債」がより少ない会社のほうが健全な経営であると判断できます。
損益計算書とは
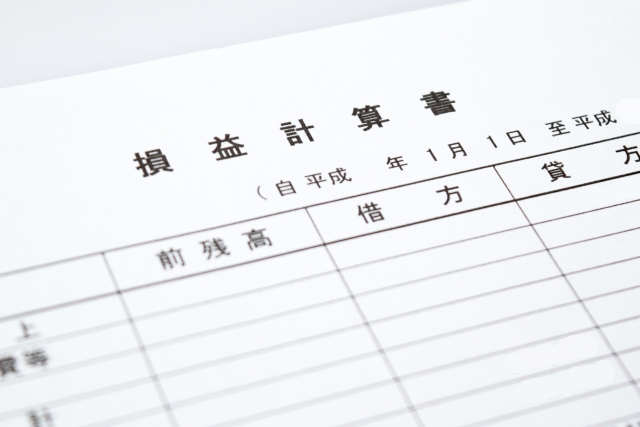
損益計算書は、収益・費用・利益という3要素から成り立つ書類です。
一定期間で発生した収益・経費を一覧で示したときの差額(利益)を明らかにする表ともいえます。
プロフィット&ロス・ステイトメント(Profit & Loss statement)を省略し「P/L」と呼ばれます。
収益から経費を差し引いた金額が「当期純利益」であり、その期における企業の経営成績です。
より詳しく損益計算書を理解するために、次の3つを押さえておきましょう。
- 損益計算書の示すこと
- 損益計算書に表示される利益
- 損益計算書のポイント
それぞれ説明します。
損益計算書の示すこと
貸借対照表は決算時点の財務状況を示しますが、損益計算書はその期間の収支の内約を示します。
売上高・利益の推移、経営の効率性など収益性を分析するときに活用する書類です。
損益計算書では次の計算式が成立します。
| 収益 = 経費 + 当期純利益 |
また、左側に経費と当期純利益、右側には収益の勘定科目が表記されます。
収益から費用を差し引くことにより最終的な利益を計算でき、損益計算書を読むことで企業の業績が良いのか悪いのか判断できます。
損益計算書に表示される利益
損益計算書から確認できる利益は、
- 売上総利益
- 営業利益
- 経常利益
- 税引前当期純利益
- 当期純利益
の5種類です。
確認したいのは利益がマイナスになっていないかであり、プラスなら「利益」、マイナスなら「損失」が発生します。
特に重要なのは通常業務で得た「経常利益」がマイナスになっていないかです。
「当期純利益」がプラスでも経常利益がマイナスなら、通常業務は赤字だったことをあらわします。
損益計算書のポイント
損益計算書は、一定期間の収益と費用をまとめた表ですが、特に注目したいのは次の3つです。
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
「売上高」から材料費や販売でかかった費用などを差し引いた利益が「営業利益」で、本業以外の入出金を営業利益と加減した利益が「経常利益」です。
売上高が大きければモノがよく売れ、利益を生み出す能力が高いことをあらわします。
しかし売上高が大きくても、材料費や人件費などのコストがかかり過ぎ、借金を抱えすぎていて利息負担が多ければ儲かっているとはいえません。
そのため売上高だけでなく、そのために発生するコストなどにも注意しておくことが必要です。
貸借対照表と損益計算書の関係

貸借対照表と損益計算書は、それぞれ異なる経営指標を示します。
ただ、2つの表は最終的な利益である「当期純利益」を通した密接な関係にあります。
たとえば株式会社では、当期純利益を一定割合で株主へと分配し、残った資金を「当期未処分利益」として自己資本に組み込みます。
繰り越された利益を蓄積することで、貸借対照表の純資産の「利益剰余金」が増えます。
そのため、損益計算書の当期純利益の増減は、貸借対照表の純資産額に影響を与える存在です。
貸借対照表と損益計算書の関係を把握しておけば、純資産に影響を与える利益の増減を意識しやすくなると考えられます。
損益計算書と貸借対照表で確認できること

損益計算書と貸借対照表は、どちらも会社の経営分析において欠かせない表ですが、確認できることはそれぞれ異なります。
活用方法が異なるため、次の2つを説明します。
- 貸借対照表の活用方法
- 損益計算書の活用方法
貸借対照表の活用方法
貸借対照表はある時点の財務状況を確認でき、損益計算書では一定期間の業績を把握できます。
会社の財務状況を点で確認できるのが貸借対照表であり、線で確認するときには損益計算書を用います。
ある時点の財務状況が確認できることは、言い換えれば会社の診断書としての役割を担えることであり、支払能力や安定性の分析にも使えます。
分析で使える代表的な指標は次の3つです。
- 流動比率
- 固定比率
- 自己資本比率
それぞれの分析指標を説明します。
流動比率
「流動比率」とは、次の2つの比率のことです。
- 短期で現金化される「流動資産」
- 返済期限が短期の「流動負債」
| 流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 |
120〜130%程度であれば、支払能力に余裕があると判断できます。
固定比率
「固定比率」とは、長期保有する「固定資産」に対する自己資本(純資産)の比率です。
| 固定比率(%) = 固定資産 ÷ 自己資本(純資産) × 100 |
自己資本で固定資産を賄うことができていれば、余計な借金はなく安定経営が望めるといえます。
自己資本比率
「自己資本比率」は、経営の安定性を示す指標であり、高ければ高いほど倒産しにくい会社と判断することができます。
総資産に対する純資産の比率を示す値です。自己資本比率が高い企業は借金そのものが少なく、健全な資金繰りができていると考えられます。
| 自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資本(負債+純資産) × 100 |
損益計算書の活用方法
損益計算書は一定期間の収益と費用を表すため、会社の成績表として活用できます。
貸借対照表から一定期間の資産の調達方法や資金使途を読み取り、損益計算書で当期純利益(純利益)を確認しましょう。
加えて売上高の増減や売上総利益の変化についても、過去のデータと照合することで、業績の変動や原因を知ることができます。
売上に対する収益性(利益率)を分析する場合に用いる指標は次の3つのです。
- 粗利率
- 営業利益率
- 経常利益率
それぞれ説明します。
粗利率
「粗利率」とは、総売上高から売上原価を差し引いた利益であり、粗利率が高ければ実際に儲かっているとは限りません。
| 粗利率(%) = 粗利 ÷ 総売上高 × 100 |
粗利率が高くても諸経費がかかるため、実際の売上高(純利益)は少なくなります。
営業利益率
「営業利益」は粗利から販売管理費を差し引いた利益であり、本業の儲けをあらわします。
営業利益率が低ければ、包括的な業務効率を改善していくことが必要です。
| 営業利益率(%) = 営業利益 ÷ 総売上高 × 100 |
経常利益率
「経常利益」は、本業の儲けといえる「営業利益」に対し、本業以外の損益を加えた利益です。
企業活動全体で得た利益であり、業績評価で重要視される利益ともいえます。
| 経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 総売上高 × 100 |
まとめ
損益計算書と貸借対照表はどちらも財務三表のうちの1つであり、企業の経営状況を示すため経営分析に欠かせない書類です。
ただ、これらの2つから得ることができる情報はそれぞれ異なるため、役割や表示する内容の違いは理解しておきましょう。
簡単にまとめると、貸借対照表は資産・資金のリストで、企業の財務状況を示します。
対する損益計算書は企業の収支内約を示し、当期純利益など経営成績をあらわします。
分析において使用する指標も異なるため、経営状況や資金繰り問題など把握したいときなど、状況や知りたい内容に合わせた分析を行ってください。
中小企業経営者向け!