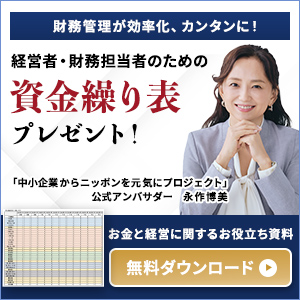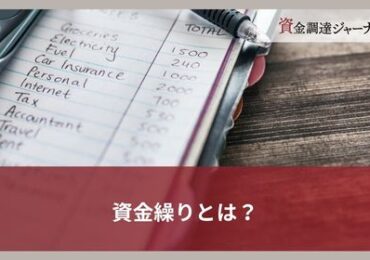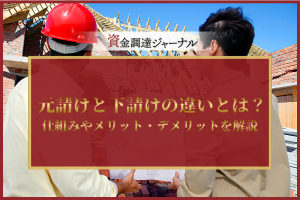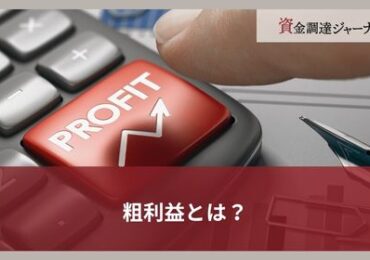小切手とは、一定金額を支払うとき現金の代わりになる有価証券です。
支払いを約束する証券として他にも手形が挙げられますが、どちらも似ているようで実際には大きく性質が異なります。
そのため小切手と手形の違いを理解し、代金の支払いに利用するときには目的等に合ったものを選ぶことが必要です。
そこで、小切手について、手形との違いや振出し・換金の流れをわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

小切手とは
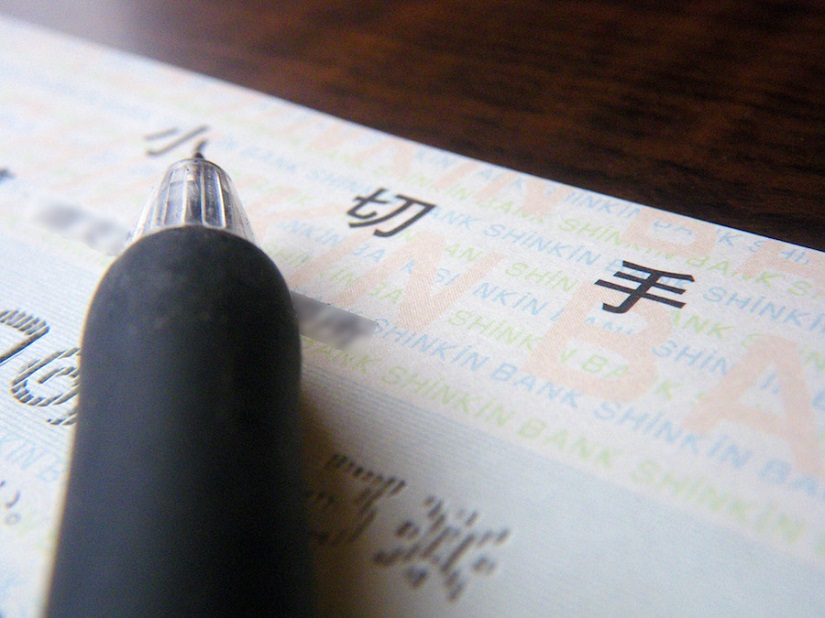
「小切手」とは、一定金額の支払いを約束する有価証券であり、多額の現金を持ち運ばなくても現金の代わりに使えます。
現金が盗難に遭ったり紛失したりという心配なく、入出金の事務負担を軽減させることが可能となるため、多額の取引には利用されています。
小切手を利用するのなら、前もって銀行で当座預金口座を開設することが必要であり、小切手用紙に記入する金額以上に預金残高がなければなりません。
小切手についてさらに理解を深めるために、次の3つについて説明します。
- 振出しとは
- 手形とは
- 小切手の手形の違い
振出しとは
小切手用紙に必要事項を記載し、銀行印を押して支払う相手に渡すこと「振出し」といい、振り出した会社は「振出人」となります。
手形とは
「手形」とは、一定期間後の支払いを約束する有価証券で、取引時点で必要金額がなくても発行できます。
指定した日に一定の場所で記載した金額を支払うことを約束する証書のため、支払期日にならなければ現金化できません。
支払期日を先に設定しておくと期日までの間に支払いが発生しないため、資金繰りもスムーズになると考えがちです。
しかし期日に当座預金残高が足りていなければ、決済されずに「不渡り」を起こします。
不渡りは半年間に2回出せば、事実上の倒産とみなされるため、手形による取引はより注意が必要です。
小切手と手形の違い
「小切手」と「手形」は、専用の用紙に支払う金額・支払う日などの必要事項を記入し、相手に渡すことは共通しています。
しかし小切手は、手形の受取人が銀行へ持参することで、いつでも現金化することができます。
対する手形は、記載されている期日後でなければ、銀行に持ち込んでも現金化できません。
小切手の振出し方法

小切手を振出すとき、小切手用紙への記載にミスがあれば、無効という扱いになります。
小切手用紙は銀行に発行してもらうときに費用もかかるため、記載ミスがあれば受け取る相手に迷惑がかかり、発行費用も無駄になってしまいます。
正しい書き方を覚えておくために、小切手を振出すまでの以下の手続を理解しておきましょう。
- 当座預金口座開設
- 小切手帳の受け取り
- 支払金額の記載
- 振出日の指定
- 振出人の署名
- ミシン目部に割印
それぞれ説明します。
①当座預金口座開設
小切手を利用する場合、銀行で当座預金口座を開設することが必要です。
銀行に申し込み、金融機関所定の審査を通過すれば無事に開設できます。
そして開設と同時に、銀行と委託契約を締結します。
小切手を振出す前は、必ず支払う金額以上のお金を当座預金に預けておきましょう。
決済できず不渡りになれば、銀行取引が停止される恐れが高くなります。
②小切手帳の受け取り
実は小切手の振出しは、法律上、必要事項を記載した紙であれば使用できます。
しかし銀行では安心したスムーズな取引のため、統一した様式の小切手用紙が使用されており、銀行に小切手帳を発行してもらうことが必要です。
③支払金額の記載
支払金額は、手書きまたはチェックライターで記します。
手書きの場合には漢数字で記入していきますが、金額の頭に「金」を付け、末尾に「円也」と記載しましょう。
チェックライターを使うときには、金額の前に「¥マーク」を入れ、算用数字で金額を記し、末尾には「※」または「☆」を印字します。
書き損じた小切手は無効となるため、新たな用紙を使うようにしてください。
なお、書き損じの破棄の際には、それぞれの項目に「×印」を入れ、シュレッダーで断裁すると安心です。
④振出日の指定
振出日は「発行日」にすることが一般的ですが、空白でも銀行で換金することはでき、必要に応じて未来の日付を記載することもできます。
⑤振出人の署名
振出人は銀行に届出している振出人の「名義」を署名します。
個人で小切手を振出すときには、個人名を記載し捺印してください。
法人の場合には、会社の社名・所在地・役職・氏名を記載しなければ、個人が発行したものとして扱われるため注意しましょう。
ゴム印がある場合には使用しても問題ありません。
⑥ミシン目部に割印
小切手の左側は、控え部分が手帳本体とつながっています。
つなぎ目であるミシン目部に、署名で使用した印鑑で割印をしましょう。
割印がなくても決済に影響はないものの、不正利用や偽装防止につながります。
小切手の換金方法・流れ

小切手を現金化するためには、受取人が支払銀行に小切手を持参し、「店頭呈示」して支払請求が必要です。
小切手記載の支払銀行でなくても、受取人の取引銀行に依頼し、「取立委任」すれば後日、口座にお金が振り込まれます。
小切手現金化までの流れは、主に次の5つです。
|
また、小切手を換金できる期間は、振出日翌日から10日目までであるため注意してください。
小切手のメリット
小切手を利用すれば、現金を持ち運ぶ必要はありません。
そのため多額の資金が必要な取引などで現金を持ち運び、盗難や紛失の不安を感じることがないことはメリットです。
また、万一小切手を紛失してしまった場合でも、銀行に連絡すれば支払いを停止できます。
もしも売上代金を小切手で支払った場合、小切手受取人は小切手に記載された支払地に出向くことなく、自社の取引銀行に持ち込み現金化することが可能です。
小切手のデメリット
小切手に記載している金額など内容は大変強い意味を持ちます。
本来は10万円の振出しなのに、「¥100,000※」ではなく「¥1,000,000※」と印字してしまうと、100万円として通用してしまうのはデメリットです。
また、取引先が小切手を銀行に持ち込んだとき、当座預金残高が小切手金額に満たなければ決済されず「不渡り」となります。
不渡りは半年間に2度発生すれば、銀行取引は停止されてしまい、事実上の倒産として扱われます。
社会的な信用を失い、取引先とのその後の契約にも影響を及ぼすため、当座預金残高の管理は非常に大切と理解が必要です。
なお、銀行と当座貸越契約を事前に結んでおくことで、万一当座預金残高が不足していても一時的に銀行に立て替えてもらえます。
小切手取り扱いの注意点

小切手は何も記載していなければただの紙切れと感じることでしょう。
しかし必要な項目を記載することで、記された金額を支払うことを約束することになり、現金と同等の価値を持ちます。
そのため現金と同様に、小切手の取り扱いにも、特に以下の3つについて細心の注意が必要です。
- 振出人の注意点
- 受取人の注意点
- 盗難・紛失の対応方法
それぞれ説明します。
振出人の注意点
小切手を扱う上で振出人が注意したいことは、当座銀行口座に小切手金額に相当する資金が残っていなければならないことです。
決済期日に残高が不足していれば、最終的に不渡りとなり銀行取引が停止される処分となる恐れがあります。
そのため小切手を振り出すときには、必ず当座預金口座の残高を確認しておくようにしてください。
受取人の注意点
小切手を受け取ったときには、必ずその場で記載されている内容に不備がないか確認しましょう。
確認するべき項目は主に次の5つです。
|
正しく記載されていなければ、無効という扱いとなり決済されない恐れがあるため注意してください。
盗難・紛失の対応方法
小切手が盗難に遭ったり紛失したりしたときには、振出人が当座預金開設の銀行に「事故届」を提出することが必要です。
それと同時に、警察に遺失届や盗難届を提出しましょう。
ただし手続の際には、盗難に遭ったまたは紛失した小切手の額面金額と同額を預けることが必要です。
この預託の手続がされていないと、振出人は取引停止処分を受けることがあるため注意してください。
預けておいた預託金は、手形交換所が一定手続を済ませた後で後日返還されます。
まとめ
小切手とは何のために利用するのか、その仕組みや振出し・受け取りの際の注意点などを理解しておくことで、取引の決済に有効活用できます。
多額の現金を持ち歩くことなく支払えるため、現金を盗まれたりなくしたりするリスクを防ぐことにつながります。
ただし小切手に記載されている金額よりも多く当座預金残高を残しておかなければ、不渡りになる可能性があるため適切な管理も必要です。
なお、小切手の受取人も銀行に持ち込むなど一定の手間はかかるため、互いのメリット・デメリットを理解した上で利用してください。
中小企業経営者向け!