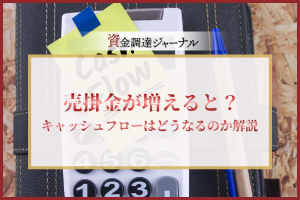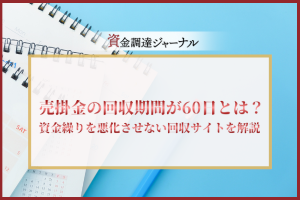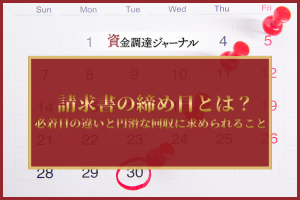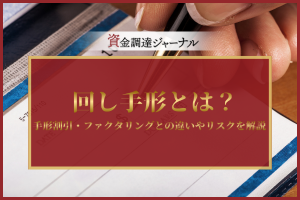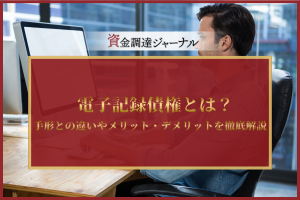2017年5月の法改正により、企業や契約ルールを定める債権関係の規定(債権法)に関しての法律が見直されました。
それにより、債権譲渡禁止特約も改正されています。
そこで、民法改正における債権譲渡について、禁止特約が付帯された債権の扱いを解説します。
中小企業経営者向け!

債権譲渡禁止特約が付帯された債権の扱い
従来までの民法では、債務者が譲渡を禁止する特約が付帯された売掛債権を譲渡しても、債務者の承諾を得ていなければ譲渡自体が無効になりました。
しかし、改正民法により、譲渡を禁止している債権でも、有効とされる扱いに変わったといえます。
債権譲渡禁止特約が付される理由
債権譲渡禁止特約は、コンプライアンス厳守や債務管理において、発注者側には使い勝手のよい特約といえます。
すべての支払い先をデータ化し手続をシステム化している企業の場合、取引のない企業に債権が譲渡されれば、データ化している支払い先を変更しなければなりません。
支払変更の稟議を回すことや、債権譲渡を承諾する通知書に印鑑を押すなど、事務的な手間も増えます。
また、債権を譲り受けた企業などが反社会的勢力ではないかを調査するコストも発生します。
そのためこれらのリスクを低減するために、債権譲渡禁止特約を付した契約が結ばれます。
債権譲渡禁止特約の中小企業への影響
債権譲渡禁止特約が付された契約の場合、債権を流動化しにくくなるため、中小企業の資金調達の手段を狭くします。
中小企業の多くは赤字経営のため、銀行融資を資金調達に活用しにくい状況といえます。
不動産を担保に差し入れれば融資を受けられる場合でも、所有していなければ借入れはできません。
これに対し、売掛債権は中小企業の多くが保有しています。
売掛債権を流動化すれば資金調達に活用できるものの、債権譲渡禁止特約が付帯されている契約では、資金を調達できなくなります。
日本の企業の大半は中小企業のため、積極的に資金が流れるように国が動き、民法改正により債権譲渡禁止特約の扱いが変わったといえるでしょう。
民法改正後の譲渡禁止特約付きの債権の扱い
民法改正により、法律上は譲渡禁止特約の付帯された売掛債権でも譲渡することが可能となりました。
売掛先にも、債権譲渡禁止特約を抗弁という形で主張できる権利は保証されています。
これにより、譲り受けた第三者が売掛先に支払い請求をしても、元々の取引先と債権譲渡禁止特約を合意していたために第三者への支払い義務はないと拒否できます。
ただし売掛先とのトラブルに発展する恐れもあるため、その点は注意しておくことが必要です。
中小企業経営者向け!