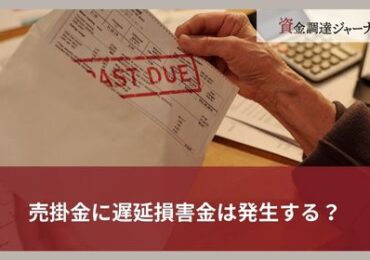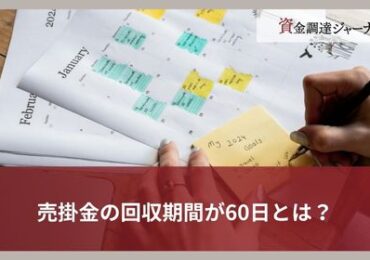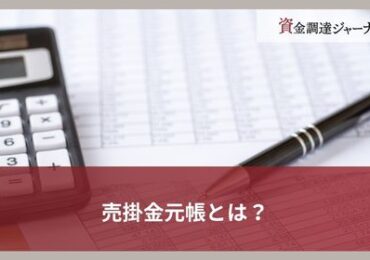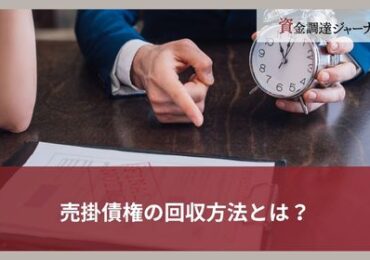約束手形とは、一定期日に一定金額を支払う約束で振り出す手形です。
仕入れ代金を支払うときに約束手形を振り出すときは、手元にお金がなくても支払いができます。
ただし売上代金の決済で手形を受け取った場合、記載された期日にならなければ現金化できないため、入金まで期間が長いほど資金繰りは悪化します。
また、万一の不渡りの発生により、経営危機に追い込まれてしまう恐れもあります。
そこで、約束手形について、振り出す目的や流れ、仕訳方法をわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

約束手形とは
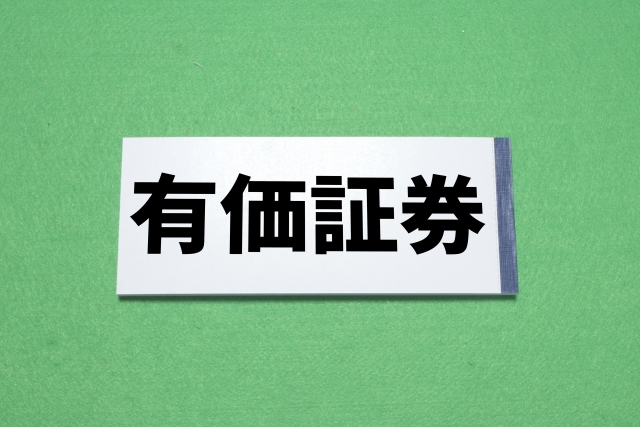
「約束手形」とは、一定期日に一定金額を受取人・指図人・手形所持者に支払うことを約束することを前提として振り出す手形です。
商取引において決済するときに用いますが、振り出した後は手形に記載された期日に、記載の代金を支払います。
約束手形について、以下の4つを説明します。
- 仕組み
- 目的
- 小切手との違い
- 為替手形との違い
仕組み
約束手形は、振出人が受取人に向けて支払いを目的として発行する仕組みです。
受取人は、手形記載の期日に、金融機関で現金化できます。
約束手形は、銀行が発行している統一手形用紙を利用して振り出します。
事前に取引金融機関で当座預金を開設することが必要であり、利息のつかない決済用預金のため金融機関が破たんした場合も全額保護されます。
当座預金口座開設においては審査もあるため信用力が高くなければ認められません。
約束手形を決済で使えることは、金融機関に信頼されていることの証明であり、請求書で支払期日を定める売掛金よりも売掛債権としての効力が強いと考えられます。
目的
約束手形の目的は、売掛金よりも支払期日を先延ばしできることです。
売掛金は第三者を挟むことなく、請求書に支払期日を定めて、その期日に回収します。
約束手形も証書に記載された期日に代金を回収できますが、一般的に売掛金より期日までの期間は長めです。
そのため約束手形を振り出す目的は、仕入れ代金などの支払いを数か月先まで延ばしし、猶予を持たせることといえます。
小切手との違い
「小切手」とは、現金の代わりとして、一定金額の支払いを約束する有価証券です。
受け取ったタイミングから現金化できる有価証券であり、受け取った受取人は翌日から10営業日以内に銀行で提示して現金を受け取ることが必要となります。
約束手形は支払う期日が先延しされるのに対し、小切手は受け取り後に金融機関ですぐに現金化できます。
振り出し時点で当座預金にお金を預けておくことが必要です。
なお、小切手と約束手形はどちらも当座預金残高が足らずに、引き落とし不能となれば不渡りとして扱われます。
一定期間に2度の不渡りを出すことで、金融機関との取引停止となり、事実上の倒産として扱われるため注意してください。
為替手形との違い
「為替手形」とは、手形振出人が支払人である第三者へ委託し、一定金額が受取人に支払われる仕組みの手形です。
そのためお金のやり取りは、以下の3者で行われます。
- 振出人(商品を購入して代金を支払う人)
- 受取人(商品を販売して代金を受け取る人)
- 名宛人(代金を支払う人)
振出人に代わって名宛人が代金を支払う手形です。
現在では振出人と受取人で取引を行う約束手形が使用されているため、実務上使用されることはほとんどありません。
約束手形の流れ

約束手形は、受取人に向けて振出人が振り出します。
受取人は期日に金融機関へ手形を持ち込み、手形の取り立てを行い現金化することが必要です。
一般的に、自社と取引のある金融機関へ取り立てを依頼し現金化します。
取り立て依頼を受けた金融機関は、約束手形の決済交換を行う手形交換所で手形を交換し、振出人の口座から現金を回収して受取人の口座へ振り込む流れです。
なお、約束手形の以下の2つの使い方について、おおまかな流れを理解しておきましょう。
- 裏書譲渡
- 手形割引
それぞれ説明します。
裏書譲渡
「裏書譲渡」とは、他から受け取った手形を、手形裏面に記載されている会社が支払人であることを明記し、転譲することです。
受け取った手形を次の第三者へ譲渡し、代金の支払いに使用します。
手数料なしで手続できるため、額面通りの金額を決済できます。
決済日までいろいろな企業を転々とすることがあるのは、この裏書譲渡によるものです。
ただし裏書譲渡した手形が不渡りになれば、最後に裏書した者から順番に買い戻すことが必要となり、最終的に振出人が買い戻すことになります。
手形割引
手形割引とは、受け取った約束手形の支払期日を待たず、前倒しで現金化できる仕組みです。
受け取った約束手形の期日よりも前にお金が欲しいときには、銀行や手形割引専門業者に手形を売却することにより、現金化できます。
審査では、振出人の信用力や決済日までの期間などの情報をもとに行われるため、業者によっては審査時間が短く即日現金化できるなどスピーディさが魅力の方法です。
ただし受け取ることができる現金は、手形額面から割引料が差し引かれた額であるため注意しましょう。
約束手形のメリット
約束手形のメリットは、振出人が代金を支払うまでの期間を延ばせることです。
取引において、多額の資金が必要となる建設業などの場合、着工から完成までの期間は6か月や1年など長期に渡ります。
材料費や外注費などの支払いは先行するため、手元にお金がなければ銀行融資などで資金を調達しなければなりません。
銀行融資を受けることが難しい場合でも、約束手形を振り出すことで手元にお金がなくても決済できます。
約束手形のデメリット
約束手形のデメリットは、不渡りによる倒産リスクを抱えることです。
手形に記載された期日に、手形額面以上のお金が当座預金口座へ入金されていない場合、決済できず不渡りになってしまいます。
半年以内に2度不渡りを出せば銀行取引は停止となり、事実上の倒産とみなされます。
不渡りの情報は取引先などにも知られるため、資金面で困窮している会社と懸念されれば、その後の取引の見直しや停止になるといった恐れがあります。
なお、手形の受取人も手形記載の決済日を含めた3営業日以内に換金しなければ効力を失います。
約束手形を銀行で取り立てることを忘れれば、現金化できず資金ショートしてしまう恐れもあるため充分に注意が必要です。
約束手形の仕訳方法

約束手形を振り出して決済したときや、取引相手から受け取ったときには、適切な仕訳処理が必要です。
そこで、以下の5つのケースに分けて、約束手形の仕訳方法を紹介します。
- 約束手形を振り出した仕訳
- 約束手形を受け取った仕訳
- 受取手形を決済した仕訳
- 受取手形を裏書譲渡した仕訳
- 受取手形を手形割引で現金化した仕訳
約束手形を振り出した仕訳
約束手形を振り出したときには、「支払手形」の勘定科目で仕訳処理を行います。
| 例:仕入れ代金10万円を約束手形の振り出しで決済した | |
| 借方 | 貸方 |
| 買掛金 100,000円 | 支払手形 100,000円 |
約束手形を受け取った仕訳
取引先から代金の支払いとして約束手形を受け取ったときは、「受取手形」の勘定科目で仕訳処理を行います。
| 例:売上代金の10万円を約束手形で受け取った | |
| 借方 | 貸方 |
| 受取手形 100,000円 | 売掛金 100,000円 |
受取手形を決済した仕訳
取引先から受け取った約束手形を決済したときは、受取手形が減って当座預金が増えます。
| 例:取引先から受け取った10万円の受取手形を決済した | |
| 借方 | 貸方 |
| 当座預金 100,000円 | 受取手形 100,000円 |
受取手形を裏書譲渡した仕訳
取引先から受け取った約束手形を、別の取引先への支払いとして譲渡することもできます。
| 例:10万円の買掛金の支払いに、同額の受取手形を裏書譲渡して支払った | |
| 借方 | 貸方 |
| 買掛金 100,000円 | 受取手形 100,000円 |
受取手形を手形割引で現金化した仕訳
取引先から受け取った約束手形を、手形割引を利用して現金化することもできます。
このとき、手形額面からは割引料が差し引かれるため、「手形売却損」の勘定科目で処理します。
| 例:受取手形10万円を金融機関で割引し、割引料3,000円を差し引した残りが当座預金へ入金された | |
| 借方 | 貸方 |
|
当座預金 97,000円 手形売却損 3,000円 |
受取手形 100,000円
|
下請法の運用ルール変更に注意
2024年11月以降は、下請法の運用ルールが変わる点にも注意しましょう。
中小企業庁では、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形や電子記録債権、一括決済方式での下請代金支払いサイトを短縮するように推進しています。
下請法上の運用変更で、60日を超えるサイトの約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式の支払いは行政指導の対象です。
サイトの短縮は下請法の適用対象にならない取引も含めて、サプライチェーン全体で取り組んでいくことが求められます。
中小企業庁と公正取引委員会が連名で、各事業者団体等に対する要請文も発出しているため、その点も理解しておきましょう。
なお、詳しくは経済産業省の「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」を参考にしてください。
まとめ
決済方法に約束手形を使うケースもあるといえますが、振り出すことで支払うまでの期日を先延ばしにできます。
また、約束手形を支払い方法として受け取った場合には、裏書譲渡することで別の代金支払いに充てることが可能です。
手形割引を利用すれば、現金化により手元のお金を増やせます。
ただし手形が不渡りになれば、銀行取引が停止されて事実上の倒産として扱われるため、約束手形の扱いには十分に注意しましょう。
なお、約束手形は、経済産業省の方針で2026年を目処に廃止が予定されています。
売掛金が発生する取引であれば、手元の資金不足に陥ったときにファクタリングなど活用できるため、資金を調達する方法として検討してください。
中小企業経営者向け!