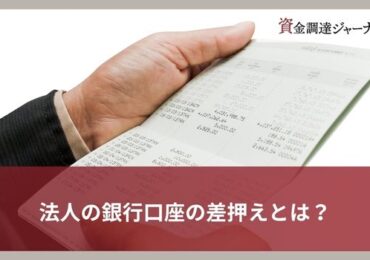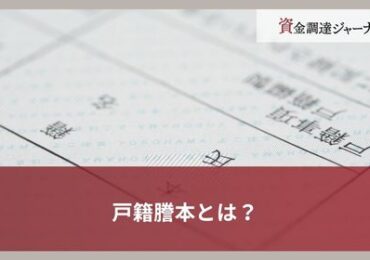経営がうまくいかず資金繰りが悪化すると、必要な支払いも滞る恐れがあるため、税金の支払いを滞納するリスクも高くなります。
仮に税金を滞納した場合、差押さえ予告には注意が必要です。
差押さえ予告を受けているのにもかかわらず、滞納が解消されなければ、差押えが実行されてしまいます。
そこで、差押さえ予告を法放置するとどうなるのか、適切な解決方法を解説します。
中小企業経営者向け!

税金滞納における措置

税金を滞納してもすぐに差押え予告を受けるわけではありません。
以下の流れで手続が進みます。
- 督促状が届く
- 延滞税が発生する
- 催告書が届く
- 差押予告通知書が届く
督促状が届く
滞納が続くと税金を滞納している機関、法人税などの国税であれば税務署、地方税であれば地方から督促状の送付を受けます。
地方税法では納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと法律で定められています。
納期限からおおむね20日ほど税金を滞納したら督促状が届くものと考えて差し支えありません。
延滞税が発生する
督促状は滞納している税金の納付を促す書類で、税金の新たな支払期限が記載されています。
指定された期日までに税金の納付がない場合は延滞税が発生します。
延滞税とは、滞納している税金の利息に相当するものです。
滞納分に対して、法律で規定された一定の割合を乗じた延滞税が本来の納付税額に加算されます。
督促状の指定期日までに支払いがない場合、原則として本来の納付期限の翌日から納付が行われるまで延滞税が発生するため、滞納が続くほど負担が増すことになります。
催告書が届く
督促状が届いてもなお滞納が続く場合は、督促状よりもより効力のある催告書が届きます。
ただし、催告書が届いてもすぐに差押えになるわけではありません。
差押予告通知書が届く
税金を滞納してから、しばらく督促や催告書が届く状態が続きます。
なお督促や催告書を無視し続けると、差押えに発展します。
再三の納税の催促にもかかわらず納付を無視し続けると、差押予告通知書が届きます。
差押予告通知書とは、指定期日までに納付がないときに差押えを執行することが記載された書類です。
差押予告通知書には差押えの時期までは記載されていないことが多く、基本的には支払期限のみ記載されます。
差押え予告を放置した場合の措置

差押えの執行を警告する差押予告通知書を受けた後でも、税金を滞納すると以下の状況に陥ります。
- 財産調査が入る
- 差押えが執行される
それぞれ説明します。
財産調査が入る
通常の強制執行による差押えでは、差押予告通知を無視すると、裁判所から支払督促が届きます。
税金の滞納は通常の強制執行とは異なるため、裁判所を通さなくても強制執行ができます。
差押えの前段階として、事業者がどれほどの財産を有しているのか財産調査が始まります。
財産調査で調べられるのは、以下の内容です。
- 収支や預貯金の残高
- 不動産や自動車などの固定資産
- 取引先
- 勤務先の状況
- 家族構成
- 生命保険
上記はあくまでも事例のため、他にも調査対象に含まれるケースはあります。
差押えが執行される
財産調査の結果、差し押さえ可能な資産がある場合は、差押さが行われます。
まず、差押えの対象になるのが経営者の給与(役員報酬)です。
通常の給与であれば生活に支障のない範囲での差し押さえになるのに対し、役員報酬については全額差し押さえ可能である点に注意してください。
ほかにも、会社の預貯金、会社が所有する土地や不動産、自動車、有価証券などが差し押さえの対象になります。
差押え予告が届いた場合の対処法

差押予告通知が届いた場合、以下で解決を図りましょう。
- 一括で納税
- 分割払い・減免の相談
- 納税の猶予の利用
- 換価の猶予の利用
- 滞納処分の停止の利用
- 債務整理の手続
それぞれ説明します。
一括で納税
一括納付により完済すれば差し押さえはされません。
仮に手続が進められている段階でも差押えはストップします。
しかし、税金を滞納している状態では完済のための資金が用意できないといったケースも多いため、適切な方法での資金調達が必要です。
分割払い・減免の相談
差押予告通知書を受け取ったら、通知書に記載されている連絡先または市役所に分割払いや減免の対応ができないか相談しましょう。
分割払いとは、分割が認められる期間にわたって滞納分を分割で支払うことで、減免とは、滞納している税金自体を減額してもらうことです。
支払いの意思があり、かつ徴収先が認める納付困難な状況にあれば、分割払いや減免が認められるケースもあります。
納税の猶予の利用
納税の猶予とは、徴収先によっては徴収の猶予ともいわれる制度です。
納付を待ってもらうことで、納付の猶予が認められれば差し押さえはストップされます。
病気や災害などで多額の負担があったとき、事業で著しい損失があったときなどに申請できます。
換価の猶予の利用
換価の猶予とは、差し押さえ実行後の換価(不動産の売却など)を待ってもらう制度です。
換価の猶予を申請するには納税の意思があることなど、一定の要件を満たして申請する必要があります。
滞納処分の停止の利用
滞納処分の停止は、あくまで債権者である税務署などの判断に基づいて行われる処分です。
滞納処分を実行すると生活に著しい支障を与えてしまったりするような場合は、税務署長などの判断で滞納処分の停止が実行されることがあります。
滞納処分の停止は、最終的には納税義務の消滅に移行するためハードルは高いといえます。
数々の厳しい要件を満たした上で行われる処分と認識しておきましょう。
債務整理を行う
差押さえを回避する方法としては債務整理もあります。
債務整理とは、借入金の返済期間の延長や減額、あるいは借金自体をゼロにする法的に認められた手続です。
滞納した税金の納税義務は免れませんが、税金以外の借入金については解決できます。
ただし債務整理は、今後の事業の継続にも影響を与えますので慎重に検討されることをおすすめします。
まとめ
税金の滞納に対する差押え予告は、差押え実行を滞納者に通知するために行われます。
差押え予告を無視すると滞納処分に移行して財産の差押えになることもありますので、予告を受けたら早期に対処することが望ましいでしょう。
中小企業経営者向け!