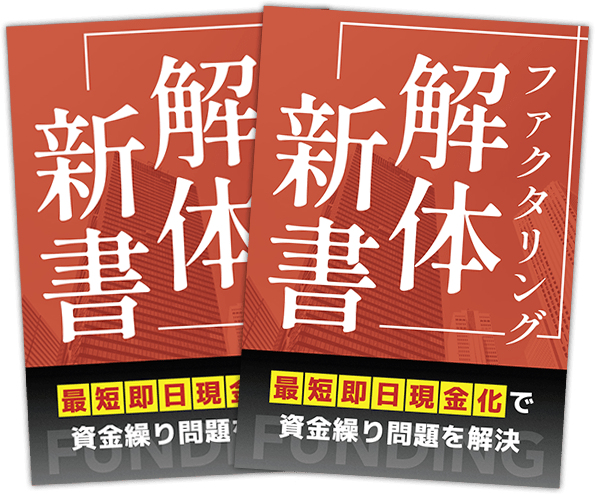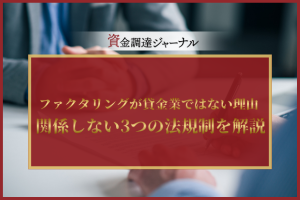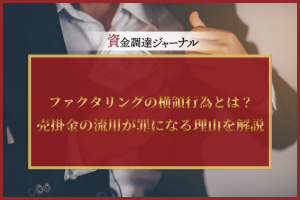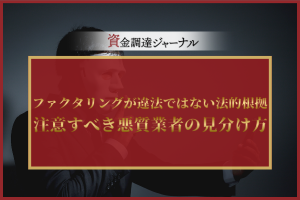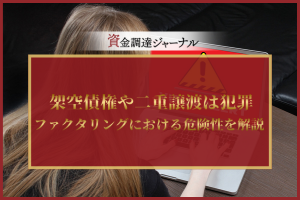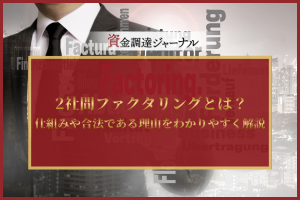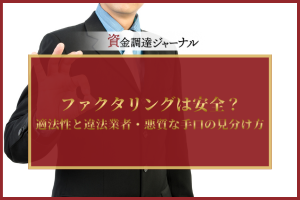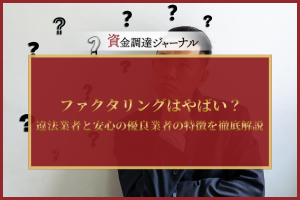中小企業などが資金調達に活用するファクタリングではなく、勤務先から受け取る給料を現金化する手法が給与ファクタリングです。
給与の前借りともいえる方法であり、再契約すれば手数料を引き下げられるなど、有利な条件に魅力を感じるケースも見られます。
しかし実際には、給与ファクタリング業者はヤミ金融業者であることが多く、騙されないように注意が必要です。
そこで、ファクタリングの再契約における注意点について、給与を扱うヤミ金融業者を回避する方法を解説します。
中小企業経営者向け!
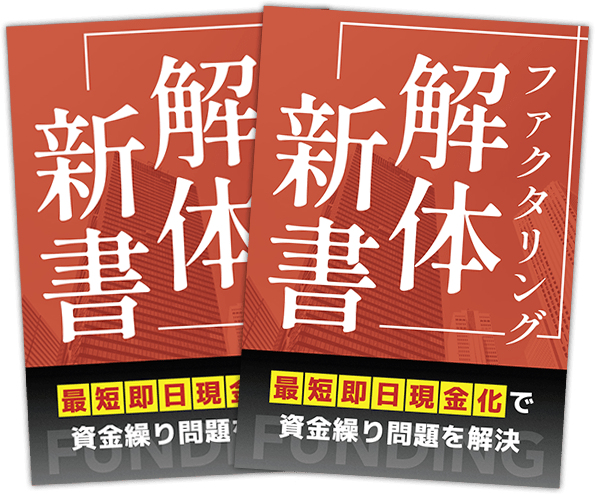
給与ファクタリングは貸金?
金融庁は、2020年3月、給与ファクタリングについて貸金業に該当する見解を発表しました。
東京地方裁判所でも、給料ファクタリングは貸金業であると判例が出されたことで、廃業・撤退に至った業者が続出しています。
2020年5月には、給与ファクタリング業者であるENZO(えんぞう)・AZABU(アザブ)・バイセル・トラストファクターなどがサービスを終了し、ビアペイなどは4月下旬からほとんどの方が審査に通らず否決の判断がされていました。
給与ファクタリングが貸金に該当するとされたきっかけは、給与ファクタリング業者である七福神(ZERUTA)を利用した男女9人が、業者に対し手数料を含め返還を求める訴えを東京地裁に起こしたことです。
判決により、契約は無効であり刑事罰の対象となる判決が言い渡されています。
貸金業を営む者が業とし金銭消費貸借契約を結ぶ場合、年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えた利息の契約は無効です。
仮に契約を結んでしまったとしても、利息については一切支払う必要はありません。
表向き手数料という名目でも、給与ファクタリングで契約したのなら利息の支払いとみなされます。
出資法・利息制限法に定めのある年20%を超える場合、民法90条の公序良俗により倫理に反するとされる行為自体が無効になるからです。
ヤミ金融業者は当然貸金業登録も行っておらず、法律に基づいた利息設定もしていません。
表向きファクタリングなのだから、貸金業法の縛りは受けないという言い分です。
しかし給与ファクタリングが貸金に該当するとされた以上、給与ファクタリング業者は貸金業登録を行っていなければなりません。
資金繰りのお悩みを解決!まずは相談してみる
簡単に契約・再契約が可能な場合のリスク

給与ファクタリング業者を装いうヤミ金融業者の手口として、電話やFAXなどを使い、手軽・簡単に初回契約または再契約を結ぼうとします。
特に遠隔地から電話やダイレクトメールなどを使い、給与ファクタリングで給料の前借りをしないかという誘いには十分に気を付けて下さい。
利息計算や返済の方法・期間、発生する手数料や遅延損害金などを問い合わせたとき、具体的な説明ができない場合はヤミ金融業者である可能性が高いといえます。
すでに再契約などを結んでしまっている場合、受け取った契約書の控えは必ず保管しておくことです。
契約書を渡してもらえない場合には、証拠を残そうとしないヤミ金融業者である可能性が高くなります。
また、契約・再契約を結んでいるわけでもないのに自分の住所や電話番号、銀行口座番号など個人情報を簡単に伝えないでください。
契約・再契約を断ったのに法外な手数料を取り立てられる、または銀行口座にお金が勝手に振り込まれ法外な金利の利息を請求されるなど、特定商取引法・貸金業法・出資法に抵触する行為も見られます。
仮に申し込みをした場合でも、インターネットを通して契約・再契約をしたため契約書面がないという場合など、特定商取引法に抵触するため支払う必要はありません。
現金書留で返済要求する業者も存在
給与ファクタリングの契約・再契約を行ったとき、業者に対する返済は従来までは法人名義口座に対して振り込みます。
最近では、給与ファクタリング業者が現金書留による支払い方法に変更してくるケースも見られます。
しかし、現金書留を利用してしまうと支払いの証拠として乏しくなってしまいます。
もし契約・再契約をしたことで現金書留の支払いを求められたときには、法的に支払いを履行したことを証明するため、弁済供託など検討してください。
銀行口座が凍結された理由
銀行の取引口座が凍結されるのは、給与ファクタリングが貸金業・出資法の高金利による「犯罪で得た収益に利用した口座」と金融庁が反対したからと考えられます。
捜査機関が犯収法に基づき、銀行口座を利用不可とする処置をとり犯罪による収益が市場取引に持ち込まれてしまうことを防ぐためでしょう。
そもそも銀行・信用金庫・保険会社・金融商品取引業者・仮想通過交換業者など特定事業者に対しては本人確認義務を課しており、犯罪で収益が移転されない行為は処罰の対象としています。
給与ファクタリングを契約・再契約した労働者がいた場合

会社員などが勤務先から受け取る賃金債権は、労働基準法で債権譲渡が認められてはいません。
自社の社員に給与ファクタリング業者と契約・再契約してしまったことで、業者から事業主に督促があった場合、「賃金支払い義務の原則」によって支払いはできないことを伝えましょう。
それでも強要や恐喝、強硬な取り立てなどが行われたときには警察に連絡し被害届を提出してください。
仮に債権譲渡通知書や債権譲受通知書などが送りつけられたとしても、契約・再契約そのものが無効なので拒否することが必要です。
民法による賃金支払いの原則
民法第466条では債権は譲り渡すことができます。
しかし、債権の性質がこれを許さないときはこの限りでないとされており、労働基準法第24条でも賃金について以下の規定があります。
- 通貨で
- 直接労働者に
- その全額を
- 毎月一回以上
- 一定の期日を決めて支払わなければならない
そのため、給与という債権を譲渡する契約・再契約などは、違法な取引に該当します。
賃金を労働者に支払う前に賃金債権が譲渡された場合でも、労働基準法第24 条の直接払い原則が適用されるため、事業者(使用者)は労働者に対し直接賃金を支払わなければなりません。
そのため賃金債権を譲受された相手(給与ファクタリング業者)が、事業者に対して給料の支払いを求めることは許されない行為といえます。
給与ファクタリングの再契約は危険?
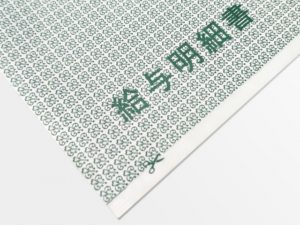
貸金業登録を行わず給与ファクタリングを行うことは違法な行為であり、無登録業者(ヤミ金融業者)と契約・再契約すれば、高額な手数料を支払わされてしまいます。
出資法では、登録業者・無登録業者を問わず、年20%を超えた利息による貸付契約・再契約は無効の扱いです。
利息制限法による上限金利も引き下げられ、以下と定められています。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利…年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利…年18%
- 元本の金額が100万円以上のときの上限金利…年15%
たとえ給与ファクタリング業者が貸金業登録を行っていたとしても、上記の範囲を超える金利で利息を請求することはできません。
また、総量規制により、個人が過度に借入れに依存しないように、年収などを基準としその3分の1を超えたる貸付けは原則禁止されています。
総量規制を無視した契約・再契約を結ぼうとする場合もヤミ金融業者の恐れが高いため、詐欺まがいの行為に騙されないようにしてください。
まとめ
過去の最高裁の判例により、著しく高利(年利数百~数千%)で金銭を貸し付けた場合、元本の返還を請求することはできないとされています。
また、返還義務は発生しません。
ヤミ金融業者に対し損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分の減額もされないとされています。
給与ファクタリング業者を装うヤミ金融業者と契約・再契約し、元本や利息を支払ったとしてもその全額を損害として請求することできます。
まずは被害に遭わないように、リスクの高い取引だと留意しておくことが必要です。
中小企業経営者向け!