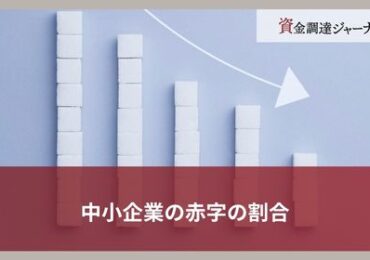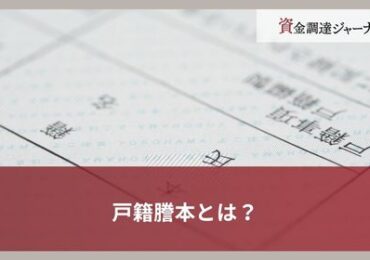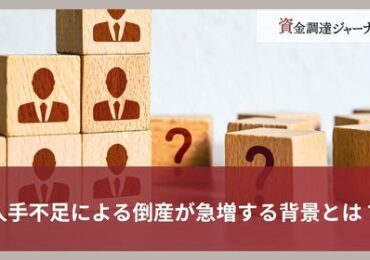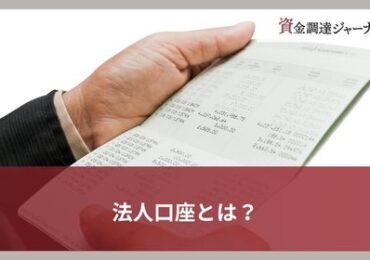銀行の繁忙日と呼ばれているタイミングに「五十日(ごとうび)」が挙げられます。
窓口付近には、いつ混みあうのかを事前に予想し、その日付を掲載して顧客の分散化を図っていることがあります。
掲載表示されている日付が、五十日(ごとうび)です。
そこで、五十日(ごとうび)とはいつのことを指しているのか、なぜ忙しいのかをご説明します。
中小企業経営者向け!

銀行の繁忙日の1つである五十日(ごとうび)

銀行の繁忙日は立地や客層によって異なりますが、個人・法人・両方の客層が足を運ぶ店舗の場合、以下が主な繁忙期とされています。
- 月末
- 月の5日、10日、15日、20日、25日など5の倍数に該当する日
- 月初
- 年金支給日
月末は、四半期末(3、6、9、12月)が特に多忙となり、月初は生活保護費が支給される1日や2日は窓口が混みます。
また、年金支給日は偶数月の15日と決まっているため、これらの日が銀行の営業日でなければ、前営業日が混むことがほとんどといえます。
そして5の倍数に該当する日が五十日(ごとうび)です。
事業所の給料日として設定されていることが多い25日や月末、10日や15日などは多くの人で窓口やATMが混雑します。
忙しくなる分、ATMでのトラブルが多く発生し、顧客から受け付けた処理で事務手続も増えます。
もともとは関西でできた言葉
30日も5の倍数に該当する日ですが、旧暦では月の長さに関係なく、月末日を五十日(ごとうび)としていることがほとんどです。
もともとは関西で生まれた言葉であり、関西では「ごとび」と読むことが多いとされ、正式には「ごとおび」と呼ばれています。
赤山禅院の五日講に由来した言葉であるという説もあります。
これは赤山明神の祭日である5日が由来しており、この日に参詣し集金を行えば、スムーズに取引ができる謂われからとされています。
五十日(ごとうび)は銀行以外でも多忙
日本では五十日(ごとうび)に決済を行うことを五十払いといいます。
銀行などの窓口が混みあうだけでなく、いろいろな企業の営業車で道路が渋滞する日です。
首都高速道路で道路が混雑するのは、毎月25日といわれているほどです。
証券市場でも五十日(ごとうび)は、アメリカドルなどの外貨の買い需要が高くなるなど、仲値も高めになる傾向がみられます。
取引は五十日(ごとうび)を避けたほうが無難
窓口やATMが混雑すると足止めになるため、五十日(ごとうび)に銀行に足を運ばなくてもよい日でのビジネスをおすすめします。
中小企業経営者向け!