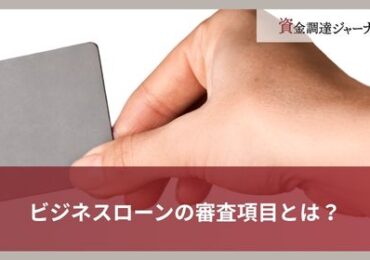設備投資とは、事業運営に必要な設備に対しお金を投じることです。
生産設備を新設することだけでなく、老朽化した設備を補強したり更新したりすることであり、省力化や合理化が可能となり生産性向上などにつなげます。
近年では現場に最新技術を導入することによるデジタル化が進んでおり、設備投資にお金をかけるケースも増えました。
しかし実際に設備投資するべきかを判断する基準がわからないケースや、投じる資金を調達する方法などに悩むこともめずらしくありません。
そこで、設備投資について、流れや必要性の判断基準、資金調達に活用できる補助金や優遇制度について解説します。
中小企業経営者向け!

設備投資とは

「設備投資」とは、事業を運営・維持・拡大するための設備購入に資金を投じることです。
資産性のある設備導入のための投資であり、たとえば次のようなものを購入します。
- 事業用不動産(土地・建物)
- 事業用車両
- 事業用機械・設備
- 情報システム
生産能力を増強するための最新設備導入や工場の増設、老朽化や陳腐化した機械設備の補強などで、資産性のある設備が対象です。
設備投資の目的
設備投資の「目的」は複数ありますが、主に次の3つが挙げられます。
- 売上拡大
- 生産性向上
- 経営合理化
それぞれ説明します。
売上拡大
設備投資の目的の1つ目は、「売上拡大」です。
売上・利益が順調に推移しており、既存の設備では増産に追いついていない場合に、設備投資で新たな機械などを導入し事業拡大を目指します。
生産性向上
設備投資の目的の2つ目は、「生産性向上」です。
長期に渡り使っていた機械や設備などが古くなり、以前ほど稼働できていないケースもあります。
修理・点検などで多くのコストが発生するのなら、新たに購入しなおすことで維持費用を削減しつつ、生産効率を高められます。
経営合理化
設備投資の目的の3つ目は、「経営合理化」です。
生産効率を高めるための人員削減など検討しているときには、人の手に頼らない設備などの導入が必要といえます。
そのため、省力化・合理化を図る目的で設備投資が行われます。
設備資金とは

「設備資金」とは、売上向上や生産効率を高めるための設備を購入するための資金です。
設備を購入しても、実際に効果が見られるまで一定の時間がかかります。
導入した設備購入資金を回収する売上を上げるまで、原材料を仕入れたり在庫が増えたりなど運転資金も多くかかります。
保守や点検などのメンテナンス費用もかかるため、将来的に発生し続けるコストの回収も必要です。
設備資金は設備購入にかかるお金だけでなく、その先に発生する維持費なども含めたものとの認識が必要であり、必要性の見極めが重要といえます。
設備投資の流れ

設備投資は、資産性の高い設備を購入し、長期間に渡り使用し続けることになります。
そのため投じる金額も大きいため、簡単に決断できることではありません。
中期計画や予算のプロセスを経て実行されることが一般的といえますが、主に次の4つの流れで実施されます。
- 金額の確定
- 再計算
- 設備投資の決定
- 資金調達
それぞれ説明します。
①金額の確定
設備投資の予算はあくまで概算であり、新機種など取得設備の見直しや相見積などによって、内容と金額を確定します。
②再計算
確定した金額や、計画を立てた売上・キャッシュフローなどから再計算を行います。
予算よりも悪化した場合、投資判断を再検討することも必要です。
③設備投資の決定
設備投資は税務調査でも調査する項目であるため、社内決裁書(稟議書)に内容や経済計算などを記載し、最終的な投資判断をします。
④資金調達
承認された設備投資案件について、内部資金を充てるだけでなく、金融機関から融資を受けるなどの資金調達を行います。
資産管理や減価償却計算においても、耐用年数や償却方法の決定に必要な情報を収集・整理が必要です。
設備投資額の確認方法

すでに設備投資を行っている場合、後でどのくらいの額を投じているのか確認したいこともあるでしょう。
上場企業の場合、有価証券報告書に「有形固定資産等明細表」の項目があるため、設備投資に関しては当期増加額の欄で確認できます。
「設備投資等の概要」に項目ごとの設備投資の額が記載されているため、一目で確認しやすいといえます。
しかし中小企業の場合、有価証券報告書を作成しないため、大手企業のような設備投資額の確認方法は使えません。
ただ、決算書に添付されている次の減価償却資産の明細書で確認できます。
- 別表十六(一)旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
定額法または定率法で償却している減価償却資産について、今期減価償却額・減価償却累計額を確認が可能です。
設備投資と減価償却の関係
設備投資を行った後は、毎年「減価償却」することが必要です。
「減価償却」とは、導入した設備や機械などの固定資産に対し、決められた法定耐用年数まで資産価値を減少させることです。
減少した価値分を費用として計上していく会計手続であり、使用や時間の経過などで損耗や劣化する減価償却資産に対して行います。
すべての資産が減価償却資産に該当するわけではなく、たとえば土地や骨とう品など、時間の経過と価値が関係しない資産は含まれません。
減価償却資産を取得したときには、取得時にすべて必要経費として計上せずに、使用可能とされる法定耐用年数で分割して必要経費に計上します。
たとえば次の流れで減価償却が行われます。
|
実際にお金の支出があったのは初年度のみで、次年度以降は支出なしで経費計上のみです。
なお、資産を購入した場合の取得金額によって、税務上は次の方法を用います。
| 取得金額が10円以上20万円未満の場合 | 一括償却(一括して3年で償却)または減価償却の選択が可能(資産計上) |
| 取得金額が10万円未満の場合 | 損金として費用計上・一定償却・減価償却のいずれも可能 |
設備投資で購入する資産は、機械・車両など様々ですが、年数が経過すれば傷んだり消耗したりします。
それぞれ決められた法定耐用年数があるため、その年数に応じて減価償却資産を当初取得した価格より差し引いた処理が必要です。
長期に渡り事業を成長させるため、資金を使って設備投資を行うことになりますが、固定資産の購入であるため経費計上は行いません。
購入当初は固定資産の増加となるものの、決算ごとに減価償却費として一部が経費計上されるため、設備投資と減価償却は密接に関係するといえます。
設備投資の判断基準

設備投資には多額のお金が必要ですが、実際に導入したときの費用対効果の分析や計画も重要です。
金額が大きいほど、自己資金だけで賄うことはできず、金融機関から融資を受けるなど資金調達に頼ることになります。
設備資金を借入れで賄う場合、導入後に計上した売上の代金回収分を返済に充てるため、具体的な売上見込みなど返済計画を立てることが必要です。
その上で、次の3つの観点から設備投資の必要性について判断するとよいでしょう。
- ROIによる観点
- ミクロの観点
- マクロの観点
それぞれ説明します。
ROIによる観点
設備投資の判断基準として、「ROI」による観点を目安にすることが挙げられます。
「ROI」とは「Return On Investment」の頭文字の略称であり、投じたお金に対して上げることができた利益を示します。
数値が高いほど投資効率が高いと判断できますが、さらに詳しく次の3つを解説します。
- ROIの計算方法
- ROI活用のメリット
- ROI活用のデメリット
ROIの計算方法
ROIを計算するときには、以下の計算式を用いります。
|
ROI(%) = 利益 ÷ 投資額 × 100
|
注意したいことは、計算する際に「利益」と「投資額」に関する定義です。
利益については、設備投資で実現した利益なのかなど、どこまでを範囲として含めるか決めておく必要があります。
また、投資額についても、設備を購入する上でかかった金額だけでなく、以下の費用を含めるか定義が必要です。
- 関連コスト
- 保守点検などのメンテナンス費用
- 増員分の人件費や広告宣伝費
定義の考え方は企業で異なるため、それぞれ判断すれば特に問題はありません。
ROI活用のメリット
ROIを活用する「メリット」として、主に次の2つが挙げられます。
- 異なる事業の費用対効果の評価が可能
- 施策レベルで費用対効果の測定が可能
ROIを活用すると、規模が異なる事業であっても、投資効果に関する比較や評価が可能です。
たとえば売上は高いものの収益性に問題のある事業や、反対に収益性は高いものの売上が低めである事業などを、同じ基準で評価できます。
また、事業単位ではなく、施策レベルでの評価・比較も可能です。
事業やマーケティング施策単位で測定することや、利益と投資額の定義を変化させることで日常的なタスク評価にも使えます。
売上・費用・収益性など、それぞれの課題を施策レベルで細かく洗い出せるため、改善策を立案したり撤退判断したりなどの場面でも活用できます。
課題を抽出することで、原材料を変えたり生産ラインを見直したりなど、改善策を立てることにもつなげられます。
ROI活用のデメリット
ROIを活用する「デメリット」として、主に次の2つが挙げられます。
- 長期的な視点で評価することは困難
- 数値化できない施策評価に向かない
計測時点での利益に基づいた評価はできるものの、長期的な視点での成長性の評価はできないことがデメリットです。
実際に成果があらわれるまで数か月や年単位でかかる事業の場合、最初の数か月間はコストのみ計上されることでROI数値は悪化します。
そのため、どの期間で比較するかなど、時間軸の観点が重要になるといえるでしょう。
また、定量的な利益と投資額が基準になった指標であるため、成果を数値化できない取り組みを評価することも難しいといえます。
たとえば知名度や認知度などを向上させることを目的としたブランディング施策に関する評価は、ROIで行うことは困難です。
あくまでも利益を数値化できる取り組みを対象とした評価に活用できる指標と認識しておくことが必要といえます。
ミクロの観点
設備投資の判断基準として、「ミクロ」による観点を目安にすることが挙げられます。
「ミクロ」とは、「微小」「小さい」という意味であり個別に捉えることを意味します。
経済を構成する企業や家計の動きをもとに、経済全体を把握する経済学の手法です。
ミクロによる観点として、取引先の将来を考えることが必要といえます。
組織(再編)・設備投資・人事(求人情報)・最近の発注傾向などの情報を収集し、営業担当者からのヒアリングも含め、やり取りなどに重要な情報が含まれていないかチェックしましょう。
また、取引先が上場企業の場合、投資家向け情報にも目を通し、経営ビジョンや戦略なども確認してください。
単年ではなく複数年の資料を比較することで、どの部分に変更があったのか、戦略の修正点なども確認できます。
取引先との将来の取引や関係を、高い確度で分析することが可能です。
マクロの観点
設備投資の判断基準として、「マクロ」による観点を目安にすることが挙げられます。
「マクロ」による分析は、経済分析の対象を経済社会全体とするものです。
巨視的分析とも呼び、GDP成長率などの経済成長率、消費者物価指数などの物価指数などの経済指標で数値的に経済を捉えて景気動向などを判断します。
ミクロの観点で情報収集することも大切ですが、マクロによる観点での情報収集も重要です。
おおよその傾向をつかむために、国が発表している各種景気動向に関する指数をチェックしましょう。
景気動向指数は主に次の3つの系列に分類できます。
| 系列名(内容) | 代表的な指数 |
| 先行系列(景気動向に先行し指数が変化) |
|
| 一致系列(景気動向と指数傾向がほぼ一致) |
|
| 遅行系列(景気動向に遅れて指数が変化) |
|
それぞれの指数の特徴を押さえることにより、景気動向が上昇または下降のどちらかある程度判断できます。
設備投資の分析方法

設備投資により、本当に投じた金額に見合う収益が上がっているのか分析するときには、次の3つの考え方を参考しましょう。
- 回収期間法
- 現在価値法
- 内部収益率法
それぞれ説明します。
回収期間法
設備投資を分析する方法として、「回収期間法」が挙げられます。
「回収期間法」とは、設備資金にかかったお金をどのくらいの期間で回収できるか分析するときに用いる方法で、次の計算式で算出できます。
|
回収期間 = 設備投資額 / 各期の平均キャッシュフロー
|
単純で簡単に回収までの期間を確認できることがメリットである反面、設備資金を回収後のキャッシュフローは考慮されません。
また、時間による貨幣価値の変化なども考慮されないこともデメリットといえます。
現在価値法
設備投資を分析する方法として、「現在価値法」が挙げられます。
「現在価値法」とは、将来的な価値を現在の貨幣価値に置き換えて計算した金額が、設備投資に投じた金額を上回っているか判断する方法です。
回収期間法と異なり、貨幣の時間的価値も含めた判断ができることはメリットといえます。
ただし、毎年の利回りについての設定や判断が難しいことはデメリットです。
内部収益率法
設備投資を分析する方法として、「内部収益率法」が挙げられます。
「内部収益法」とは、設備投資で将来的に生み出せる内部利益率(キャッシュフロー利回り)を計算し、想定していた内部収益率が上回っているか判断する方法です。
設備投資に対し求める利回りの設定がポイントとなるものの、表計算ソフトでIRR関数を使用すればスムーズに計算できます。
設備投資の税制優遇制度

中小企業が一定の要件を満たした上で設備投資を行う場合、次の税制優遇制度を活用できます。
- 中小企業経営強化税制
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
- 中小企業投資促進税制
それぞれ説明します。
中小企業経営強化税制
設備投資の税制優遇制度の1つ目は、「中小企業経営強化税制」です。
「中小企業経営強化税制」とは、経営力向上計画に沿って実施された一定の設備投資に対し、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税制優遇を受けられる制度です。
対象となる設備は、経営力向上計画に従って実施した一定の設備投資であり、生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であることなどが必要とされています。
また、経営力向上計画の申請には工業会などの証明書が必要など、複数の要件があります。
2025年3月31日まで適用される制度なので、該当する場合には節税対策に活用するとよいでしょう。
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
設備投資の税制優遇制度の2つ目は、「先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例」です。
「先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例」とは、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業が設備投資する場合の支援制度です。
先端設備等導入計画に沿って取得した先端設備などに対する固定資産税が、新しく課税される年から3年間に渡り2分の1に軽減されます。
さらに、従業員に雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを表明した場合には、次の軽減措置の対象となります。
- 令和6年3月末までに取得した設備について5年間に渡り3分の1に軽減
- 令和7年3月末までに取得した設備について4年間に渡り3分の1に軽減
対象となるのは、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市町村の「導入促進基本計画」に基づいて認定を受けた中小企業などです。
対象となる設備は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備とされています。
市町村により異なる場合があるため、事前に確認するようにしてください。
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※ただし家屋と一体で課税されるものは対象に含まれない
生産・販売活動などで直接使用することが必要であり、中古資産ではないことも求められます。
適用期限は2025年3月31日までとなっているため、要件を満たす場合には活用するとよいでしょう。
中小企業投資促進税制
設備投資の税制優遇制度の3つ目は、「中小企業投資促進税制」です。
「中小企業投資促進税制」とは、中小企業などが機械導入など行った場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人・個人事業主のみ)の優遇措置が適用される制度です。
対象となる設備は、指定事業で使用する以下の設備となっています。
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(120万円以上または30万円以上かつ複数台計120万円以上)
- 一定のソフトウェア(70万円以上または複数合計70万円以上)
- 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
- 内航船舶(対象は取得価額の75%)
適用期限は2025年3月31日までとなっているため、要件を満たすときには活用するとよいでしょう。
設備投資の補助金

中小企業が一定の要件を満たした上で設備投資を行う場合、「IT導入補助金」を活用できます。
「IT導入補助金」とは、生産性向上に向けたIT機器導入などの設備投資において、かかった経費の一部が補助される補助金制度です。
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的に、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア・サービス等)の導入を支援します。
ただし前もって事務局の審査を受け、公開(登録)されているものであることが対象のITツールになる要件とされています。
相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれます。
なお、申請者は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とのパートナーシップを組んだ上での申請が必要であるため、詳しくは公式サイトから確認が必要です。
まとめ
設備投資は、会社や事業を成長させることや、生産性を向上させるためには欠かせません。
そのため設備投資の必要性に関する適切な判断するため、しっかりと情報収集を行い投資の可否を判断することが必要です。
補助金制度など活用する場合においても、手元に入金されるのは対象事業を運営した後です。
補助金は後払いでかかった経費が支払われる制度であるため、先に立て替えて費用を支払うことが必要となります。
手元のお金が足らずに補助金活用できなくなることや、設備投資を中断しなければならない状況に追い込まれることは避けなければなりません。
一時的なつなぎ資金の調達に、売掛金を現金化して資金調達できるファクタリングなどをうまく活用することをおすすめします。
中小企業経営者向け!