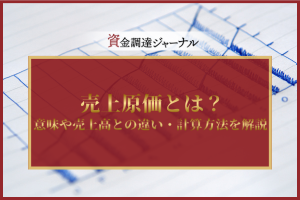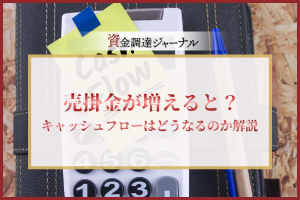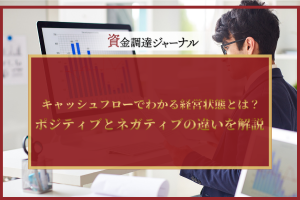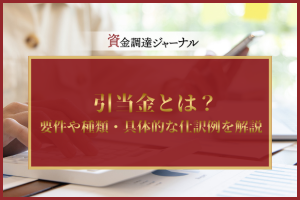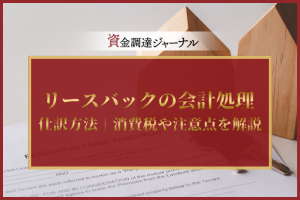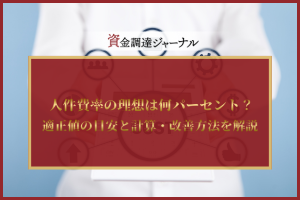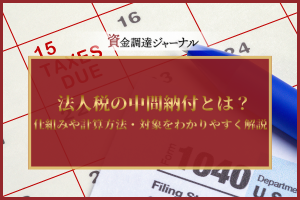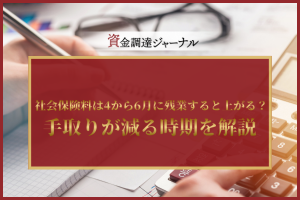売上原価は自社の利益計算や価格設定、在庫管理など、経営判断をする際に非常に重要な指標なので、会社の経理や会計担当、経営者は理解しておくべき基礎知識です。
この記事では売上原価の計算方法や、主な業種別売上原価の特徴、売上原価の低減策などについて解説しています。
中小企業経営者向け!

売上原価の基本
売上原価とはどのような費用を指すのでしょうか?
売上原価の考え方や、売上原価と混同しがちな費用について解説します。
売上原価とは?
売上原価とは、ある期間内に提供した商品の生産・製造に直接的にかかった費用のことです。
具体的には、販売した商品を製造するために仕入れた原材料費、製造にかかった人件費や外注費、減価償却費、水道光熱費などが売上原価に当たります。
例えば仕入価格が500円、販売価格が1,000円の商品が10個あり、10個すべて期中に販売できたとすると、このときの売上原価は「500円×10個=5,000円」です。
ただし、例えばサービス業は外注費が売上原価で計上できますが、自社の管理部門の人件費は販売費および一般管理費に計上するなど、業種によって売上原価に含める原価の範囲が異なる場合もあります。
売上原価は、主に粗利(売上総利益)を計算する際に用いられ、決算書のうち、損益計算書の費用の部に計上されます。
売上原価に含まれないもの
売上原価は今期売れた商品に対する仕入価格のみ含まれます。したがって今期売れずに、在庫となった商品の仕入額は売上原価に含まれません。
例えば仕入価格が500円、販売価格が1,000円の商品が10個あり、10個中に期中に5個しか販売できなかった場合、売上原価は「500円×5個=2,500円」です。
売上原価は製造原価と混同されがちですが、売上原価が商品の仕入れや製造にかかった費用のうち「期中に実際に売れた商品にかかった費用」であるのに対し、製造原価は「期中に製品を製造するためにかかった費用」を指し、売れたかどうかは問わないという違いがあります。
また売上原価は販売管理費(以降、販管費)と見分けがつきにくい費用です。販管費とは商品や製品、サービスなどの販売にかかる費用を指します。
したがって製品を製造する際にかかった人件費は売上原価に該当しますが、広告宣伝費や間接部門(経理部や人事部など売上に直接結びつかない常務を担う部門のこと)にかかった費用などは販管費であり、こちらは売上原価には含まれません。
業種別の売上原価の特徴

売上原価は業種によって算出方法に特徴があります。ここでは製造業と建設業、サービス業の売上原価の特徴について解説します。
製造業の売上原価
製造業の場合、工場で生産のみ行っているか、あるいは工場で生産から販売まで行っているかなど、最初に業務の範囲を確認します。なぜなら売上原価は商品を販売したときの費用であり、生産(製造)にかかった費用は製造原価に分類されるためです。
工場で生産のみを行っている、あるいは自社で在庫を持たない受注生産のような場合は、製造原価イコール売上原価となります。
また製造業は、材料の仕入れや加工費、労務費、光熱費など製造にかかった費用を、製造原価報告書にまとめるのが一般的です。
製造原価報告書とは、期中でどれくらい商品を作ったか、どのような経費がかかったのかを計算した書類のことを指します。
一方、製造から販売まで行っている会社の場合は、製造原価だけでなく売上原価も計上が必要です。
また製造業の売上原価はさまざまな費用がありますが、大きく直接費と間接費に分類できます。
直接費とは商品を販売する上で直接かかった費用のことです。
例えば、製造を担当する従業員に支払った人件費や、製造に必要な材料費などが該当します。
間接費とは、製造工場のメンテナンス費用や人件費など、どれだけかかったのか直接把握することが難しい売上原価を指します。
建設業の売上原価
一般的な会計では1年を区切りにしますが、建設業の場合、建築物の着工から完成まで1年以上かかることも珍しくありません。
そのため建設業では、独自の収益計上、費用計上の基準がある建設業会計が用いられます。
一般会計における売上原価は、建設業会計における完成工事原価に該当します。参考までに一般会計と建設業会計の対応表を紹介します。
|
建設業会計 |
一般会計 |
|
完成工事未収金 |
売掛金 |
|
未成工事支出金 |
仕掛品 |
|
工事未払金 |
買掛金 |
|
未成工事受入金 |
前受金 |
|
完成工事高 |
売上高 |
|
完成工事原価 |
売上原価 |
|
完成工事総利益 |
売上総利益 |
一般的な小売など、物を仕入れて販売する業種であれば、売上原価は仕入価格のうち当期の売上高に対応する部分が計上されます。
しかし建設業は、物を仕入れて販売する業種ではありません。
そのため完成工事原価に含まれるのは、建設収入を得るために要した労務費・材料費・外注費・経費です。
【完成工事原価を構成する4つの要素】
|
労務費 |
工事に要した人員の賃金や給料、福利厚生費、手当など、現場作業員や技術者、現場監督などの賃金のこと。
人事など管理部門の賃金などは完成工事原価に算入しない。 |
|
材料費 |
木材、鉄筋、ガラスなど特定の工事に直接使用される材料のこと。
特定の工事に使用しない、接着剤や塗料、ドライバーといった工具などは完成工事原価に算入しない。 |
|
外注費 |
工事を他の業者に外注して、代金を支払ったときの費用など。外注費として完成工事原価に算入可能。 |
|
経費 |
工事をする際に要した、通信費、交通費、器機などの減価償却費、設計費、保険料など。直接的に工事に振り分けることが難しく、間接費に算入するべきと判断されることも多いため注意が必要。 |
サービス業の売上原価
売上原価とは販売した商品やサービスを生み出すために、直接かかったコストを指しますが、サービス業の場合、ノウハウなどで売上を得られます。
そのためサービスの提供により新たに発生するコストは、外注費のみです。
つまりサービス業の場合、売上原価として計上できるのは外注費に限られます。
ではサービス業の人件費は、売上原価に計上できないのでしょうか?
サービス業の場合、人件費は通常、固定的に毎月発生するもので、サービスの提供により新たに発生するものではありません。
例えばサービス業の従業員は、サービスを提供している時間もありますが、会議や研修などでサービスを提供していない時間もあるでしょう。
したがってサービス業の人件費は、提供したサービスと紐付けできるコストとはいえず、売上原価ではなく販管費に計上されます。
サービス業では、外注せずに自社のみでサービスを提供している場合、売上原価は発生しないと考えられます。
売上原価の計算方法
売上原価は販売した商品を製造するため仕入れた費用を指しますが、実務ではどのように計算すれば良いのでしょうか?計算式と計算の具体例を紹介します。
売上原価の基本計算式
売上原価の計算式は以下の通りです。
|
【売上原価の計算式】 売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
|
小売業のケースを想定して、実際に計算してみましょう。
- 売価1,000円
- 仕入価格500円
- 期首の商品在庫数 200個 期首商品棚卸高は200個×500円=10万円
- 当期に仕入れた商品数 1,000個 当期商品仕入高 1,000個×500円=50万円
- 期末に売れ残った在庫 300個 期末商品棚卸高 100個×500=3万円
10万円 + 50万円 - 3万円 = 57万円
売上原価は、当期中に販売した商品に対して発生した費用です。
同じ期中に仕入をしても、在庫になった分は売上原価に含まれません。
期中に売れ残った商品の原価は資産として計上します。
また期首に在庫として残っていた商品も、販売したのが当期であれば、当期の売上原価とします。
ここでは小売業の事例を紹介しましたが、業種によっては商品の仕入価格ではなく、外注費や労務費などで売上原価を計算する場合もあります。
売上原価の仕訳と会計処理
売上原価には4つの仕訳方法があり、業種や取り扱っている商品によって適性があります。
ここでは売上原価の仕訳と会計処理について具体例を用いて解説していきます。
売上原価の4つの基本仕訳
売上原価の仕訳方法には以下の4つがあります。
- 三分法
- 売上原価対立法
- 分記法
- 総記法
各仕訳方法について詳しく紹介します。
三分法
仕入(費用)、売上(収益)、繰越商品(資産)の3つの勘定科目を使って仕訳をする方法です。実務ではもっともポピュラーな記帳方法といえるでしょう。
三分法は販売時点で売上原価を記帳する手間がないため、仕入れや販売が多い企業などに幅広く採用されています。
ただし、期中の原価管理ができないというデメリットがあります。
具体的な仕訳例を紹介します。
【商品を仕入れたとき】
3万円の商品を仕入れて、代金を現金で支払った。
|
借方 |
貸方 |
||
|
仕入 |
30,000円 |
現金 |
30,000円 |
仕入を費用として計上し、同額の現金や買掛金といった資産を貸方に記入します。原価は売価ではなく、仕入れたときの金額で記入します。
【商品を売り上げたとき】
5万円の商品を販売して、代金を現金で受け取った。
|
借方 |
貸方 |
||
|
現金 |
50,000円 |
売上 |
50,000円 |
現金という資産が増加したため借方に記載、収益が増加したため貸方に売上を記載します。
【決算時の仕訳】
期末時点で期首商品残高が5万円、期末商品残高が1万円だった。
|
借方 |
貸方 |
||
|
仕入 |
50,000円 |
繰越商品 |
50,000円 |
|
繰越商品 |
10,000円 |
仕入 |
10,000円 |
三分法では売上時に売上原価を処理しません。
そのため期首に在庫があるときは売上原価を仕入に加算し、期末に在庫があるときはその分の売上原価を仕入から差し引く必要があります。
売上原価対立法
売上原価勘定で、売上原価を直接管理する方法です。
三分法では期中の原価管理ができませんが、売上原価対立法では期中でも売上原価が確認できます。
ただし売上を計上するたびに売上原価を算定するため、仕訳数が多くなる点はデメリットといえます。
売上原価対立法で使用する勘定科目は商品・売上・売上原価の3つで、以下のステップで仕訳を行います。
- 仕入時に商品勘定の借方に原価で記入
- 販売したときに売上勘定の貸方に売価で記入
- のタイミングで、その商品の原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替える
具体的な仕訳例を紹介します。
【商品を仕入れたとき】
3万円の商品を仕入れ、代金は掛けとした。
|
借方 |
貸方 |
||
|
商品 |
30,000円 |
買掛金 |
30,000円 |
商品勘定の借方に原価で記載します。
【商品を売り上げたとき】
原価3万円の商品を5万円で掛けで売り上げた。
|
借方 |
貸方 |
||
|
売掛金 |
50,000円 |
売上 |
50,000円 |
|
売上原価 |
30,000円 |
商品 |
30,000円 |
販売時に売上を計上するとともに、商品の原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替えます。
決算時は商品勘定が期末の商品在庫、売上原価勘定がそれぞれ期末商品、売上原価の金額となるため決算処理をする必要がありません。
ただし、棚卸減耗損や商品評価損を売上原価に含めるようなときは、別途決算整理仕訳が必要になる可能性があります。
分記法
商品と商品売買益の2つの勘定科目を用いて、仕訳を行う方法です。
期中に仕入れた商品を商品勘定で資産として計上し、販売時に商品勘定と売価の差額を商品売買益勘定で収益として計上します。
三分法のように決算整理をしなくても、リアルタイムで取引ごとの仕入原価や売買益がわかるため、現在の粗利をすぐに知ることができる点がメリットです。
ただし取引ごとの記帳が複雑になるため、商品の種類が多い企業にとってはデメリットとなります。
分記法は宝石商や不動産業など、少量で高額な商品を扱う業種が選ぶ方法です。
具体的な仕訳例を紹介します。
【商品を仕入れたとき】
3万円の商品を仕入れ、代金を現金で支払った。
|
借方 |
貸方 |
||
|
商品 |
30,000円 |
現金 |
30,000円 |
【商品を売り上げたとき】
原価3万円の商品を5万円で現金で売り上げた。
|
借方 |
貸方 |
||
|
現金 |
50,000円 |
商品 |
30,000円 |
|
商品売買益 |
20,000円 |
||
30,000円で仕入れた商品を50,000円で売り上げたので、20,000円の利益が出ます。貸方に商品原価と売買益を記載、現金50,000円を借方に記載します。
分記法では商品の購入と販売の差額が分かるため、取引ごとにいくら利益が出たのかが把握できます。
また分記法も商品を販売するたびに売買益を計算するため、決算時に仕訳は行いません。
総記法
仕入と販売、どちらにも商品の勘定科目を使って仕訳を行う方法です。
商品勘定のみを使用するため記帳方法としてはシンプルですが、売価と原価が混在するため、期中の商品勘定の残高には何の意味もなく、決算整理が不可欠になります。
具体的な仕訳例を紹介します。
【商品を仕入れたとき】
3万円の商品を仕入れ、代金を現金で支払った。
|
借方 |
貸方 |
||
|
商品 |
30,000円 |
現金 |
30,000円 |
まず商品勘定の借方に仕入価格を記載して資産計上します。
【商品を売り上げたとき】
原価3万円の商品を5万円で現金で売り上げた。
|
借方 |
貸方 |
||
|
現金 |
50,000円 |
商品 |
50,000円 |
次に商品勘定の貸方に販売価格を記載して資産計上します。
【決算時の仕訳】
総記法の場合、決算時には当期の商品売買益を別途計算して、利益を商品勘定から商品販売益勘定に振り替えます。
この結果、商品勘定の借方残高が期末商品棚卸高を表すことになります。
3万円の商品を仕入れて、5万円で販売したときの仕訳は以下の通りです。
|
借方 |
貸方 |
||
|
商品 |
20,000円 |
商品販売益 |
20,000円 |
総記法は期中で売り上げ原価を直接示す勘定科目がありません。
そのため記帳は簡易ですが、財務分析をしたり経営成績を把握したりする目的には利用できないことから、あまり実務で利用されるケースが少ない記帳方法です。
損益計算書における売上原価
売上原価は損益計算上、売上の次に表示されている項目です。
企業の売上高から売上原価を引いた金額は売上総利益または粗利益といわれ、本業部分で稼ぎ出した利益を表します。
粗利益を売上高で割って計算する売上総利益率で、企業の業績把握や同業他社との比較が可能です。
また売上原価は「期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高」の式を使って計算するため、期末商品棚卸高が増加すると売上原価が減少することで利益が増え、法人税額も増えてしまいます。
このように売上原価は法人税額にも大きな影響を与えるのです。
期末商品棚卸高は「期末の在庫数量×単価」で計算しますが、仕入価格は材料の高騰や品薄などの理由で変動することがあります。
そのため法人税法では、自社にとって有利な単価を使って企業が利益操作をしないよう、単価の計算方法が定められています。
単価の計算方法は以下の6つです。税務署に届出をしない場合は、最終仕入原価法で単価を計算します。
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 最終仕入原価法
- 売価還元法
原価計算が適切に行われていないと、税務調査で棚卸資産の計上漏れや原価計算誤りを指摘され、追徴やペナルティが課される可能性があります。
売上原価管理の重要性と手法

売上原価は企業の損益に大きな影響を与えます。売上原価管理が企業の損益に影響を与える理由や、主な問題点に対する解決策を紹介します。
売上原価管理が利益に与える影響
売上原価管理をして企業の製品やサービスの原価が把握できれば、さまざまな場面で無駄が生じていることに気付ける可能性があります。
コストの見える化を図り、無駄が生じているプロセスに対して改善策を講じれば、利益率アップが狙えるでしょう。
赤字が出ている場合も、売上原価管理により損失が出て非効率が生じている箇所を特定し、対象となる箇所を改善することで赤字幅縮小あるいは黒字転換が図れます。
原価計算を誤ってしまうと、実際は利益率が悪いにもかかわらず問題点に気が付かなかったり、十分な利益が出ているにもかかわらず不要なコストカットをしてしまったりと、誤った経営判断をしてしまう可能性があります。
効果的な原価低減策
売上原価管理で問題点を探すことができたら、原価低減策を検討しましょう。主な原価低減策として労務費や光熱費の削減が挙げられます。
労務費とは従業員の給与や賞与、法定福利費、福利厚生費などがあります。
労務費は業務フローを見直して、不要な業務を減らす、IT化やAI化によって効率化する、奨励制度などで社員のモチベーションアップさせる、業務配分の割り振りを見直すといった方法で、削減が可能です。
また電気代やガス代を削減することで、経費を抑えられます。
例えば電気をLED照明にする、古い空調設備を見直して電気代を節約する、節水弁の設置で水道代を節約する、都市ガスに変更することでガス代を節約するといった方法で、削減が可能です。
リースで利用している設備がある場合は、今のプランが利用実態と合っているかを見直してみるとよいでしょう。
ただし安易に従業員の福利厚生費を削減したり、空調温度の設定を強制したりすると従業員の反発を招き、逆効果になる可能性もあるため、慎重に進める必要があります。
仕入れコスト削減のテクニック
仕入れコストを削減も、売上原価低減につながります。仕入れコスト削減は、さまざまな方法がありますが、主に以下の通りです。
仕入方法の検討
複数社から仕入れていたものを1社に絞り、価格交渉をする。少量よりも大量に仕入れたほうが輸送費や人件費が抑えられる場合がある。
内製化・外製化を再検討
これまで外注していたものを内製化できないか、あるいは自社生産していたものを外製化できないかを再度検討してみましょう。
見直した結果、コストが削減できる可能性があります。
また手間のかかる工程のみ、一部内製化あるいは外製化するという方法も考えられます。
量産品の原価低減交渉
同じものをずっと仕入れている場合、仕入先の工程が改善されてコストが下がっている可能性があります。
量産品や仕入先のおすすめ品を仕入れているときは、仕入先に仕入価格を下げられないか交渉してみましょう。
現地で査定する
見積もりだけで判断せず、仕入先の工程もチェックしてみましょう。
仕入先に非効率な工程があれば、改善を要請すれば結果的に仕入価格の低減につながる可能性があります。
仕入れコスト削減は、仕入先に交渉するのがもっとも一般的ですが、過度な交渉をすると仕入先との関係が悪化してしまう恐れがあります。
交渉する際は、極力双方にメリットがあるような案を検討するようにしてください。
また原材料を見直した結果、商品のクオリティが低下すると売上が下がる恐れもあります。
価格だけでなく、仕入れる商品の品質も入念にチェックしましょう。
生産効率の向上による原価低減
生産効率の向上とは、保有している資源を最大限活用することで、少ない資産でも大きな利益を生み出すことを指し、「アウトプット(成果)÷インプット(コスト)」で計算をします。
アウトプットには生産量や生産額、付加価値が、インプットには従業員数や労働時間が挙げられます。
例えば1,000人で10万個の商品を作り出しているのであれば、生産性は「100,000個÷1,000=100」です。
しかし業務改善により500人で10万個の商品が作り出せれば、生産性は「100,000個÷500=200」にアップします。
ここでは生産効率をアップさせるための施策を5つ紹介します。
業務の標準化
業務のマニュアル化を図り、製品や商品の品質にばらつきが生じないようにします。
ばらつきがなくなれば、返品やクレーム対応などが減り、顧客対応に費やす時間も減少します。
また使用する書類のフォーマットを統一することで、書類の作成作業や確認作業、手続が簡素化できるでしょう。
人員配置の見直し
多くの従業員がいるにもかかわらず、業務内容に応じた能力や適性を持っていない従業員が配置されているといった非効率が生じている場合があります。
各従業員が持っている資格やキャリア、業務経験などの情報を収集して管理しておくと、個々の性格や能力を踏まえた人材選定ができるようになります。
過剰品質になっていないか確認
製品・商品のクオリティは重要ですが、限られた中で最大限の成果を出す上で、過剰品質は生産性を阻む要因となり得ます。
品質・コスト・納期・リスク・セールスという5つの還元の中に、過剰品質になっている部分がないか確認しましょう。
従業員のコミュニケーション促進
コミュニケーション促進も生産効率アップに有効です。例えば仮に誰かが急に休んだ場合、情報共有していれば代わりの従業員がスムーズにリカバリーできます。
またトラブルがあったときも、情報共有をしてアイデアを出し合ったほうが、妙案が生まれやすいでしょう。
従業員のスキルアップ
コストはかかりますが、特定の日に研修やセミナーなどを開催して従業員のスキルアップを図ることで、これまでできなかった技術が身に付いたり、より高度な業務に取り組めるようになったりと、結果的に生産効率アップにつながります。
サプライチェーンの最適化
サプライチェーンの最適化とは、原材料の調達から顧客への配送までのプロセスを効率化し、改善を図ることです。
サプライチェーンは自社だけではなく、プロセスに関連する仕入先、販売先すべてを含めて検討します。
サプライチェーンを最適化する手法のうち代表的なものを紹介します。
仕入先との関係強化
仕入先に対して安定した発注を保証することで価格交渉力を高める、在庫情報などを共有することで仕入先にも無駄な在庫を極力持たせないことでコスト低減を図る
リードタイムの短縮
配送方法、配送経路、配送先の見直しなどで、最短・最安のルートを構築し、リードタイム短縮を図る
複数の調達ルートの確保
災害や急なトラブルに備え、複数の調達ルートを確保しておく
共同購入による調達コスト削減
複数の企業で原材料を共同購入することで価格交渉力を高め、コスト削減を図る
在庫管理の適正化
在庫管理の適正化により、何がどの店舗・工場にあるかが明確になるため、適時・適配が可能になる、売上が減少している商品の生産終了決定判断や、製品の販売ペース予測などが容易になる
そのほか、在庫の保管コストが減少するメリットもあります。
在庫回転率と売上原価の関連性
在庫回転率とは、一定期間内に在庫がどれだけ入れ替わったかを示す指標です。
在庫回転率が高ければ、その商品は頻繁に在庫が入れ替わっている、すなわち売れていることを表し、在庫回転率が低ければその商品は売れていないことを表しています。
また在庫回転率を見れば、商品がどれくらいのペースで売れているかも把握できるようになります。
在庫回転率は以下の計算式を使って計算をしますが、金額ベースでも個数ベースでも計算が可能です。
|
【在庫回転率の計算方法(金額ベース)】 在庫回転率 = 期間中の出庫金額 ÷ 期間中の平均在庫金額 期間中の出庫金額 = 売上原価 期間中の平均在庫金額 = (期首在庫高+期末在庫高) ÷ 2 |
上記計算式のうち、期間中の平均在庫金額は仕入価格を使って計算をします。
そのため分子である期間中の出庫金額は、同じく仕入値である売上原価を使用することで、より実態に合った値が得られます。
|
【在庫回転率の計算方法(個数ベース)】 在庫回転率 = 期間中の出庫数 ÷ 期間中の平均在庫数 期間中の平均在庫金額 = (期首在庫数+期末在庫数) ÷ 2 |
よくある質問と実践的なアドバイス
売上原価に関するよくある質問をまとめました。経理や会計担当の方、経営者の方はぜひ参考にしてください。
売上原価が高すぎる場合はどうする?
業種によって売上原価は異なりますが、同業同規模の競合と比べても売上原価が高すぎる場合、どのような対策があるのでしょうか?
ここでは主な対策を4つ紹介します。
1つ目は在庫管理の見直しです。
在庫管理ができていないと欠品を恐れるあまり、過剰在庫を抱えがちになります。
結果的に管理コストが増加し、売上原価を上昇させてしまいます。
在庫管理方法を見直して在庫を圧縮することで、売上原価を低減させることができるでしょう。
2つ目は仕入先の見直しです。
同じ商品を仕入れるのであれば、より安い仕入先から仕入れたほうが、売上原価は下がります。
また現在利用している仕入先から、まとまった数量を仕入れることで調達コストや輸送コストが下がり、売上原価の低減につながる可能性があります。
現在の仕入先に交渉してみるとよいでしょう。
ロス率の改善も売上原価低減につながります。ロス率とは売上原価のうち、売上につながらなかった金額の割合のことです。
原因としては食品の廃棄ロスや、余剰在庫の値引き販売などが挙げられます。
先に紹介した在庫管理は、在庫圧縮だけでなくロス率の改善にも効果があります。
また製造工程を見直して、無駄な工程を省く、材料費を圧縮するなどの方法でも売上原価を低減させることが可能です。
経営者が押さえるべき売上原価管理のポイント
企業の利益を確保する上で、経営者が売上原価管理することは非常に重要です。
経営者が押さえるべき売上原価管理のポイントを紹介します。
まずは全体のコスト構造を把握して、どの部分に問題があるのか課題を特定します。課題が見つかったら無駄なコストを削減するための対策を講じましょう。
インフレや為替レートによって仕入価格が変動する可能性もあるため、価格変動などのリスク管理も経営者は考えておかなければなりません。
自社のコスト構造は定期的に点検することも大切です。また対策を講じたら、それで終わりではなく、もっと良い売上原価低減策を見つけるよう動きましょう。
全体のコスト構造は定期的に点検し、常により優れた改善策を追求し続ける必要があります。
そのため適切なツールやソフトウェアを使用し、売上原価管理の効率化を図りましょう。
まとめ

売上原価は提供した商品の生産・製造に直接的にかかった費用を指しますが、今期売れた商品に対する仕入価格のみに含まれるため注意が必要です。
売上原価は業種によって、含める原価の範囲が異なります。経営者は自社の売上原価の特徴を把握しておきましょう。
原価計算を誤ると、非効率なプロセスにも気が付かずに企業の利益を圧迫したり、不要なコストカットで業務に支障をきたしたりと、誤った経営判断をしてしまう可能性があります。
また正しい原価計算が行われていないと、税務調査で指摘を受け追徴やペナルティが課されることもあり得ます。
このように経営を行う上で、売上原価を算出するのはとても大切です。
適切な売上原価計算を行って、自社の課題解決やさらなる利益改善を目指しましょう。
不安なときは無料ではありませんが、実務経験豊富な税理士法人などに監修してもらうことをおすすめします。
中小企業経営者向け!