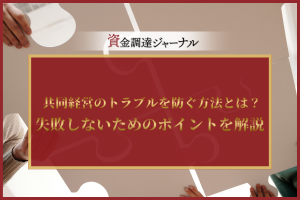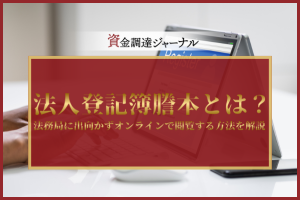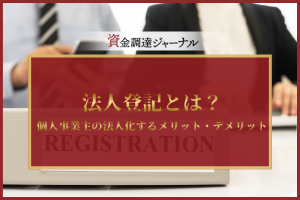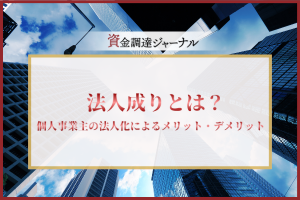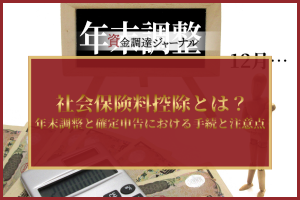「事業再生」とは、債務超過などで資金繰りが悪化している事業を再建し、企業経営を健全化していくことですが、コンサルタントに依頼し再建を図るケースもめずらしくありません。
なぜなら経営者独自で事業の再生を図ろうとしても、スムーズに手続を進めることは容易とはいえず、コンサルタントに頼ったほうがよい場合もあるからです。
事業再生のため金融機関に相談するケースも少なくありませんが、経営再建の経営陣の右腕としてコンサルを行う会社なども存在します。
そこで、事業再生とはそもそも何を行うのか、コンサルタントに相談するときのポイントなどについて解説していきます。
中小企業経営者向け!

「コンサルタント」と「コンサルティング」の違い
「コンサルタント」と「コンサルティング」は、どちらも似た言葉なので混同されることが多いといえます。
しかし「コンサルティング」は相談業務のことなので、業務そのものを指す言葉です。
「コンサルタント」はコンサルティングをする人を指しています。
個人事業主として、コンサルティングサービスを提供することもあれば、会社の一員として業務を提供する活動を行うこともあります。
「コンサルタント」の3つの種類
多様化するビジネスに合わせて、様々な業界や業種に対応できる「コンサルタント」が増えてきました。
数多くのコンサルタントの種類がありますが、大きく分けると次の3つに分類されます。
- 総合コンサルタント
- 専門コンサルタント
- システムコンサルタント
それぞれ説明します。
総合コンサルタント
「総合コンサルタント」とは、特定の分野において広範囲に渡り知識や経験のあるジェネラリストとして、総合的にコンサルティングを行うコンサルタントのことです。
該当するコンサルタントには、以下が挙げられます。
- 経営コンサルタント
- 店舗コンサルタント
- マーケティングコンサルタント
幅広い領域で対応可能となることが特徴といえます。
ただ、コンサルティングの対象となる範囲が広ければ、単独で対応することが難しくなります。
専門チームを結成し、プロジェクト単位で課題へと取り組むことがほとんどです。
専門コンサルタント
「専門コンサルタント」とは、特定業務やサービスなど、一定の分野に特化してコンサルティングを行うコンサルタントのことです。
経営コンサルタントを中心として、プロジェクトチームを形成するコンサルタントが該当します。
種類としては、以下が挙げられます。
- 財務コンサルタント
- 人材コンサルタント
- マーケティングコンサルタント
また、特定の業界やサービスに特化したコンサルタントも含まれるため、以下も該当します。
- 医療系・ヘルスケア系コンサルタント
- イベント系コンサルタント
- 飲食店系コンサルタント
- ISOコンサルタント
- 資金コンサルタント
システムコンサルタント
「システムコンサルタント」とは、ITシステムをメインに専門知識を活かし、システム面から業務改善をサポートするコンサルタントです。
経営コンサルティングの1つとしてチーム業務として行うケースも少なくありませんが、単独で課題解決に取り組むといったケースもあります。
新規で事業を行うときにWebサービスなども必要なときには、システム開発会社やWeb制作会社などがコンサルタントとしてコンサル業務を行うこともあるようです。
「事業再生」とは

「事業再生」とは、経営不振に陥っている企業の事業再建を目指し、経営を健全化していくことを目的に色々な施策を立て実践することです。
国も事業再生に向けた様々な支援を行っていますが、たとえば次のようなことが挙げられます。
- 税理士・会計士・弁護士・中小企業診断士など認定支援機関の「経営改善計画の策定支援」
- 中小企業再生支援協議会に専門家を派遣して経営改善を目指す「再生支援協議会の強化」
- 企業再生支援機構を改組した「地域経済活性化支援機構による事業再生等」
「事業再生支援施策」が強化されている背景と目的
国が事業再生支援施策を強化しているその背景には、2013年に「中小企業金融円滑化法」が終了したことが関係します。
経済不況で中小企業が倒産してしまうことを防ぐことが必要です。
「中小企業金融円滑化法」では、中小企業や住宅ローン利用者の返済条件変更などにも柔軟に対応するよう、金融機関に対する努力義務が定められていました。
リ―マンショック後、現在は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中小企業の資金面の厳しさは変わっておらず、むしろ以前よりも苦しい状況となっています。
中小企業金融円滑化法が終了しても、金融機関は引き続き円滑な資金供給や貸付条件変更などの対応に努力するべきとしています。
しかし実際には、スムーズに資金を調達できていると言い切れません。
経済状況がますます厳しくなった中で事業再生に対する支援を求める中小企業は増えているため、国も様々な施策を立てて倒産させないことが必要となったといえます。
そして色々な要因が関係し、事業を継続することが将来的に見て困難だと予測されたとき、検討できるのが「事業再生」です。
「事業再生」により事業継続を可能とする状態へもっていくことができれば、会社だけでなく雇用も守り、社会的な損失なども最小限に抑えられます。
「事業再生」の流れ
「事業再生」を行うときには、経営の立て直しを図るためにも現況を把握することから始めましょう。
綿密な財務診断で、企業に残された経営資源や負債を明確にすることが必要です。
現状の把握ができたら、次に事業を継続するために行うべき「再生計画」を策定していきます。
状況によって、債務を返済するため金融機関にリスケジュールを交渉することも必要になることもあれば、支払項目の精査や社員や事業のリストラなども必要になる可能性もあります。
また、スポンサーを見つけ支援してもらうことが必要となるケースもあり、投資してくれる企業など募ることもあるでしょう。
いずれにしても金融機関などステークホルダーから再生計画を認めてもらうことができ
なければ、策定した再生計画を実行する段階へと移行することは難しくなります。
「事業再生」の必要性
そもそも「事業再生」が必要となる背景には、たとえば後継者がいないという悩みを抱えている場合や何をすればわからないなどの理由で、事業の再建をあきらめる営者もいます。
しかし日本の9割以上が中小企業といわれており、再建を諦めた企業が次々に倒産や廃業してしまえば、それに伴い取引先なども連鎖倒産するなど日本経済は衰退します。
色々な事業再生を検討したものの、やはり事業譲渡や会社分割、清算などがもっともよい選択というケースも見られます。
ただしまずは事業再生を検討するべきといえますが、単独では難しくても専門家からアドバイスを受けることで、可能になるケースも少なくありません。
会社の清算を検討している場合でも、債務の一部免除や弁済期繰延など、債権者と交渉を重ねながら事業の収益力・競争力を取り戻し経営危機から脱出するケースもあります。
そのため、もし事業再生で悩んでいるのなら、専門的な知識を保有したコンサルタントの力を借りるのも方法の1つといえるでしょう。
「事業再生」の種類とそれぞれの方法
「事業再生」を大きく分けると、以下の2つです。
- 法的整理
- 私的整理
まずは「私的整理」を目指し、それでも再建できない場合には「法的整理」を検討したほうがよい場合もあります。
なお、法的整理には、以下の2つが挙げられます。
- 会社更生
- 民事再生
それぞれ説明します。
私的整理
債権者と話し合いや交渉を行うなど、自主的な協議で債務を整理することを「私的整理」といいます。
専門家に依頼することで比較的円滑に合意を得ることができ、事業規模や実態に合わせた柔軟・迅速な再建に向けた取り組みが可能となります。
また、裁判所など通さず手続できるため、倒産した企業というレッテルを貼られることなく、取引先との取引維持も可能となり、事業価値を毀損もされにくいといえます。
ただし再建計画に反対する債権者がいても、法的に対象となる債権者を拘束することはできないことがデメリットです。
会社更生
経済的に厳しい状況に陥った株式会社が、裁判所の選任した更生管財人の主導の下で、債権者など利害関係者から同意を得て更生計画を策定・遂行し事業再建を図る方法が「会社更生」です。
株式会社のみに与えられた強力な手続であり、無担保債権者だけでなく担保権者や株主の権利も制約することとなり、更生計画でこれをカットすることが可能です。
合併・減増資など組織再編も簡易に行うことができることはメリットですが、経営権や財産の処分権は管財人に移ります。
法的倒産処理を開始したことが公になれば、信用不安を引き起こすことも考えられます。
手続に時間もかかるため、比較的規模の大きな企業などで選択される事業再生の手続といえます。
民事再生
経済的に行き詰まった企業が、現経営者の主導の下で債権者など利害関係者から同意を得て、再生計画を策定・遂行し、会社の事業の再建を図る手続が「民事再生」です。
無担保債権者の権利は制約されることなりますが、担保権者は権利行使が可能となります。
再生計画でカットできるのも無担保債権のみなので、会社更生と比較すると効力が弱い反面、低廉・迅速に手続が進むため、中小企業には適した方法といえます。
「事業再生」のうち私的整理は自己破産よりもメリットが高い理由
「私的整理」とは、民事再生・会社更生・破産などの法的倒産手続を行わずに債務を整理することです。
株式会社など法人の他、連帯保証債務で苦しむ経営者なども利用できる方法といえます。
債権者との交渉を行いながら、事業計画や返済案を策定し同意を得た返済案に従い弁済します。
法的整理よりも前に、まずは私的整理を検討したほうがよいといえますが、法的倒産手続よりも次のようなメリットがあります。
- 一定程度成功したときには、事業停止するときよりも債権者に多く弁済できる
- 事業継続が可能となれば収益を生み出し、経営者の生活・従業員の雇用・サービス提供などが継続できるようになり、事業の社会的価値維持にもつながる
- 取引先との取引は正常に維持しつつ債務を整理できるため、経営者や事業の社会的信用を維持することができ、取引先が負う被害も最小限に抑えることが可能
「事業再生」を検討するなら知っておきたい5つの言葉
独自で事業再生を行うことは容易ではないため、コンサルタントに依頼しようと考える経営者もいます。
しかしどの専門家に依頼すればよいかわからず、どのように判断するべきか悩んでいるケースも少なくありません。
そこで、まずは事業再生に関連するワードを知っておくと、専門家に相談するときにスムーズに会話が成立しやすくなります。
事業再生の際に知っておきたいワードは主に5つありますので、それぞれ説明していきます。
ハンズオン
「ハンズオン」とは「手を触れる」という意味であり、ファンドやコンサルティングファームなどが、投資先やコンサルティングの対象となる企業の経営に深く関与することです。
たとえば投資会社が社外取締役を派遣し、経営の舵を取って企業価値を上げるためのサポートを行うケースなどが該当します。
ターンアラウンドマネージャー
「ターンアラウンドマネージャー」とは、経営破綻しそうな企業の再生を請け負う人のことで、組織編成などの観点から企業を再生させる重責を担います。
たとえば債務超過で経営破綻リスクの高い企業に、企業価値を高めることを目的として陣頭指揮を執る責任者として登用され、経営の立て直しを図るスペシャリストが該当します。
事業再生ADR
「事業再生ADR」では、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与しながら、過大な債務を負った企業などが債権者から協力してもらいつつ、事業再生を図る取り組みを円滑化します。
会社更生や民事再生、破産など法的整理は行わないため、裁判所の強制力はなく、あくまでも債権者との話し合いをベースに事業再生していきます。
サービサー
「サービサー(債権回収会社)」とは、金融機関からの債権の委託や譲渡で、特定金銭債権の管理回収を行う専門業者です。
債権回収だけでなく個別に法務大臣の許可を受けることで、事業再生業務など債権回収に関わるサービスも提供します。
従来までは弁護士法により、弁護士や弁護士法人以外が委託を受け他人の債権を管理・回収をする業務はできませんでした。
しかし平成11年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」により、民間債権回収会社を設立することができるようになりました。
リスケジュール
リスケジュールとは、借入金の返済が困難になったときに、一定期間の約定返済額を減額させるなど返済条件を変更することです。
新規で融資を受けることができないとき、資金繰り改善に向けた方法として使われています。
月額返済額を減額してもらったり返済期間を延長してもらったりなど、返済条件を変更することで経営の立て直しを図る手段といえます。
「事業再生コンサルタント」とは

「事業再生コンサルタント」は、経営環境の変化や競争激化により事業継続が厳しい状況にある企業を、健全な経営状態に導くためのコンサルティングを行う専門家です。
ここ数年は外資系再生コンサルティングファームや監査法人系アドバイザリーファームなどが人員を増やすなど、積極的に活動しているといえます。
企業をV字回復させるコンサルタントとも言えますが、収益性や資金繰りなどで問題を抱えている企業を、事業・財務・組織・人材など多方面から改革していきます。
一時的に有事な状況にある企業でも、コア事業は高い収益力を保有していることもあり、市場競争力のある高い技術は保有したままというケースもあります。
そのため、企業の負の部分と効率の悪い部分を取り除き、事業価値を蘇らせることを仕事とするのが事業再生コンサルタントと言えます。
事業再生コンサルタントは、主に以下をコンサルティング業務として行います。
- 経営診断・予備調査
- 事業計画・再生計画の立案
- M&A・PMI
- 売上向上に向けた商品・価格最適化
- オペレーション変更による収益改善
- 運転資金のマネジメント
- 設備投資リターンを最大化する
- 利害関係者の合意形成
「事業再生コンサルタント」の役割と業務内容
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、経営環境は日々変化しているといえます。
コロナ禍で資金繰りが悪化してしまい、経営危機に瀕している企業もあれば、不採算事業で財務状況が悪化している企業もあります。
どのような場合でも財務諸表を分析した上で、事業構造や業務あり方など多角的な視点から現状を分析することが必要です。
そして事業を続けるために必要なアクションなどを検討し、計画を立てていくことが必須となります。
具体的に行うこととして挙げられるのは以下のとおりです。
- 金融機関とリスケジュールなど交渉を行う
- 不採算事業を縮小または整理する
- 組織構造の再編など検討する
事業再生コンサルタント自らが経営の一員となり、企業再構築を先頭に立ち実行することもあります。
課題を解決するまでの間は、プロジェクトに対して推進する力も必要となるため、信頼できるコンサルタントに依頼することが重要です。
他のコンサルティングとの違い
一般的な事業再生に向けたコンサルティングは、半年から1年または2年程度の期間をかけることになります。
コンサルティングの内容は、以下など多方面に改革が及ぶこともあるといえます。
- 業務改善
- 収益改善
- キャッシュフロー改善
- コスト削減
- バランスシート最適化
- 経営戦略の見直し
- 組織改編
戦略系ファームでは、成長戦略を策定するサポートを行い、新規事業を開発するための支援も行うため、時間をかけて調査・分析し報告書にまとめることになるでしょう。
しかし事業再生コンサルティングでは、迅速に対応できるオペレーションを改善することや、短期的にキャッシュフローを改善させるなどを重視します。
戦略に紐づき、改革を実行しステークホルダーから合意を得て改革を実行させることに重きをおきます。
企業や事業の売上や利益など収益性を向上させることや、キャッシュフローを改善させるなど、直接的な働きかけによるコンサルティングがメインとなります。
そのため、目に見える成果を追求することになると考えられます。
事業再生をコンサルタントに依頼したほうがよい理由

事業再生は独自で行うよりも、コンサルタントに依頼したほうがスムーズです。
ただ手続を迅速に進めることができるだけではなく、コンサルタントに依頼したほうがよい理由は他にもいろいろありますので説明します。
専門的な知識など獲得できる
事業再生コンサルタントと呼ばれる専門家は、これまでも色々な経験から様々な企業を再建してきたといえます。
数多くの企業が再生することをサポートしてきたからこそ得ることのできる、高い専門的な知識や独自のメソッドが存在しており、それらのノウハウを自社で使うことが可能となるのは大きなメリットです。
客観的な判断ができる
100%客観的な意見を聞きたいという場合でも、取引先や顧問契約を結んでいる税理士などからは得られるとは限りません。
しかし事業再生コンサルタントは完全に外部の第三者のため、余計な私見や忖度など排除した客観的な意見を聞くことができ、公平な判断が可能となります。
迅速・正確に遂行できる
事業再生を顧問の税理士や弁護士に相談したくても、事業再生自体がメイン業務ではないことが多いといえます。
しかし事業再生コンサルタントなら、再建に向けたサポートが本業なのでスピードや正確性なども満足できるサービスを受けることができます。
事業再生コンサルタントの見極め方と選び方

信頼できるコンサルタントを見つけたとしても、経営者や役員などもすべてをコンサルタントに丸投げするのではなく、当事者意識を捨てずに一緒に事業再生に臨むことが必要です。
ともに当事者となり事業再生に向けて親身に取り組んでくれる優秀なコンサルタントを見つけるためには、次の特性を確認した上で決めましょう。
自社に必要な知識を保有していること
事業再生コンサルタントを選ぶときには、自社が必要としている知識など保有している専門家を選ぶことが必要です。
たとえばキャッシュフローが問題となり事業が傾いているのなら、資金調達やコストカットなどに詳しいコンサルタントを選ばなければなりません。
コンサルタントをサービスとしている会社やコンサルタント個人が得意とする分野を把握し、自社の事業再生に注力してくれるか判断しましょう。
また、コンサルティングは人と人で行うもののため、コンサルタントの人柄や相性の良さなども重視しつつ見極めることが必要です。
当事者意識を持って事業再生に向け取り組んでくれること
コンサルタントの中には、たとえば顧問の弁護士や税理士など総入れ替えすることをすすめるケースもあるのに対し、士業を尊重し協力しながら再生を目指すコンサルタントもいます。
顧問契約を結んでいる弁護士や税理士に不満を抱えているときには総入れ替えすることも方法の1つといえます。
そうでない場合には、すでに契約している専門家とも協力しながら事業再生に取り組んでくれるコンサルタントの方がよいでしょう。
互いに協力しながらプロジェクトを遂行してくれなければ、どれほどよい計画を立てたとしても成功にはつながりません。
高いマネジメント能力を保有していること
事業再生コンサルタントには、メンバーを纏めるリーダーシップ能力とコミュニケーション能力が高いこと、そして迅速に対応できる能力も必要です。
たとえば会社にとって好ましくない話があれば、早めに次の対応を検討し軌道修正できることが必要になります。
特に事業再生では、早期に業績を回復することが必要となるため、長々と時間をかける暇はなく、限られた時間でコンサルティングすることが必要です。
何事にも謙虚な姿勢で取り組んでくれる専門家のほうがより望ましいといえます。
空気を読む力やきめ細やかな対応力があること
抱える悩みや現状の把握をする能力と、プロジェクトを進行するだけでなくきめ細やかな対応など、気遣いができるコンサルタントであれば何でも相談しやすいといえます。
そもそも事業再生のコンサルティングにおいては、経営状況が急変することもめずらしくありません。
マニュアルに沿った対応を行うコンサルタントでは、窮地を乗り切ることは難しくなるでしょう。
臨機応変な対応が可能で、常に最新の情報を入手でき、その場の空気を読む力や対応能力の優れたコンサルタントこそ、自社の事業再生を任せるのことのできる専門家といえます。
事業再生の豊富な実績があること
事業再生を専門とするコンサルタントなら、これまでもすでに多くの企業の再建に携わってきたはずです。
経験が豊富で高い実績があれば、実力や知見も身についており、信頼性も高いコンサルタントと判断できます。
さらに顧問先の事業に関しての知識なども保有しているコンサルタントなら、より的確な再生案などを作成し実行することが可能となるでしょう。
これまでどのような企業をサポートし、実際に再建を成功させたのか過去の実績なども参考にしながら、信頼できる事業再生コンサルタント選びをしてください。
まとめ
餅は餅屋といわれるように、事業再生を図るなら専門のコンサルタントに相談したほうがよいといえます。
コンサルタントに相談した上で、弁護士や税理士などにも支援してもらうことにより、様々な分野でそれぞれの強みを発揮したサポートを受けることができます。
そして事業再生コンサルタントは誰でもよいわけではなく、それまでの実績や専門的なスキル、人柄なども見極めた上でパートナーとして選ぶことが必要です。
国内企業のほとんどが中小企業であり、その4割近くは10年間で5回以上営業赤字を経験しているといわれています。
経営に余力にある場合でも、早期の段階で事業再生を検討し、今自社が抱えている課題が何か把握しておけば、窮地に陥ったときに改善しやすくなります。
中小企業経営者向け!