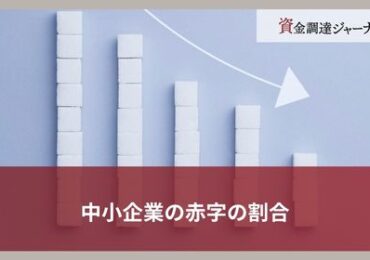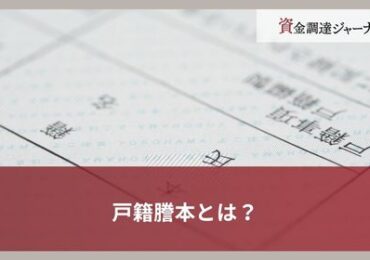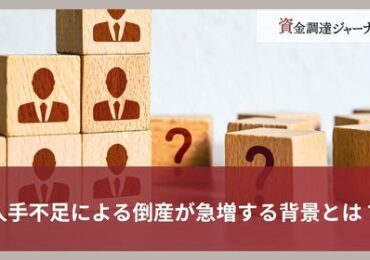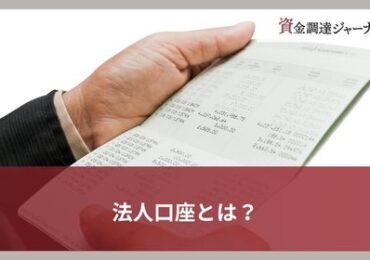単独で会社を経営しているけれど、トラブル続きで不安を感じている経営者の中には、「共同経営」を検討したことがある方もいることでしょう。
一人ではなく二人または複数人の経営者が共同で事業を運営・維持しながら、一緒に経営を行う共同経営なら、経営にかかる負担やリスク・トラブル等を防いだり解決したりしやすいと考えられるからです。
有能なビジネスパートナーとともに力を合わせて行う共同経営なら、相乗効果でトラブルを解消させ好転できる可能性も考えられます。
さらに事業開発や拡大など事業を展開させることにつなげることができる可能性も広がります。
しかし、当初は意気投合して一緒に事業を盛りたてていこうと共同経営を始めたものの、何らかのトラブルなどをきっかけとして「やめたい」と感じてしまうこともあるようです。
そこで、共同経営を行うメリットやデメリット、ありがちなトラブルを防ぎ失敗しないためのポイントについて説明していきます。
中小企業経営者向け!

共同経営とは

「共同経営」とは、複数の経営者や企業が経営責任・資金等を共有し、共同で事業運営を行う経営形態です。※必ずしも対等な立場ではありません。
資金や経営に関する知識、業務のスキルやノウハウなど、互いに足らない部分を補いながら経営できるため、相乗効果が期待できる経営形態といえます。
共同経営といってもそれぞれが同じ負担をするのではなく、出資金の割合や立場、業務などで役割や負担の分け方は異なります。
そこで、次の3つの分担の違いによる共同経営について理解していきましょう。
- 資比率の分担
- 立場の分担
- 業務の分担
それぞれ説明していきます。
資比率の分担
株式会社の場合、出資比率が同じであれば、出資者の持つ経営権も平等になりますが、出資割合が異なる場合は、割合が大きい経営者が意思決定の権限を持つ事になります。
このように、出資比率に応じて、意思決定の権限が異なる事から、一見平等の方が良く見えますが、意見が割れた際などは、かえって迅速な意思決定ができないケース等もあり、事前にお互いの相談が必要です。
立場の分担
共同経営者同士で、一方が出資者(実質オーナー)でもう一方が、実務を行うケースもあります。
日常業務の実務に関しての意思決定は実務担当の経営者が行い、最終決定権は出資者が行うといった、形の関係性で経営していく事もあります。
業務の分担
営業・開発・経理など、会社経営において必要な業務は多岐に渡りますが、担当する分野を分けて行う共同経営です。
担当する分野でそれぞれの経営者が意思決定権を持つ事で、職責の明確化が行われます。
共同経営のメリット
共同経営することによるメリットとして、主に次の5つが挙げられます。
- 互いに不足する部分を補いあえる
- 人脈が活かせる
- 責任を分担できる
- 意思決定の相談ができる
- 役割分担できる
それぞれ説明していきます。
互いに不足する部分を補いあえる
資金や経営に関する知識、営業ノウハウなど、一人では満たすことのできなかった部分を共同経営であれば補いあうことができます。
それぞれが得意な分野などを担当することで、事業成長にも良い影響を与え効率よく仕事を進めることができるでしょう。
人脈が活かせる
それぞれの共同経営者が持つ人脈を最大限に活かす事で、ビジネスの広がり方が変わります。
様々な人脈形成を活かす事で、相乗効果が生まれます。
責任を分担できる
単独経営では一人が責任を負わなければならなかったことでも、共同経営なら立場に応じた意思決定権を持つこととなるため、責任を分担できます。
意思決定の相談ができる
経営者は常に孤独であると言われることが多く、意思決定の場面で迷いを感じても、誰にも相談できず決断を強いられることも少なくありません。
そのような場面においても、共同経営なら一人で悩まず同じ目線や立場の相手に相談することができます。
役割分担できる
共同経営でどの分野や役割を担当するか決めておけば、一人ですべての負担を抱えることがありません。
効率的に仕事を進める上でも、役割分担することで業務効率化や生産性向上につながり、仕事の質も高めることができます。
共同経営でトラブルが起きる理由

もともとは一緒に事業を成功させたいという夢や目標を持って始めたはずなのに、トラブルに繋がってしまうのはお金が関連することが多いようです。
そのほとんどが閉店の際の金銭トラブル、次に出資に関するトラブル、また、意見の食い違いや気持ちのすれ違いなどがきっかけとなり、共同経営者のうちの誰かやめたいと脱退するケースもみられます。
その背景には次のことが関係していると考えれます。
- 意思決定まで時間がかかる
- 人間関係の不満がたまりやすい
- 責任の所在が曖昧
それぞれ説明していきます。
意思決定まで時間がかかる
仮に個人事業主であれば、すべて事業主本人が決定していくことになりますが、共同経営なら経営者間で合意を取りながら決めていくことが必要です。
相談できる相手がいることはメリットですが、意見が一致しなかったときには決定まで時間がかかる場合もあります。
本来、個人事業主や中小企業などはスピード感のある意思決定が可能であることがメリットといえますが、決定まで時間をかけすぎてしまえばビジネスチャンスを逃すことになりかねません。
単独経営のように、思う通りの経営ができないこともあることは留意しておきましょう。
人間関係の不満がたまりやすい
会社の経営状況が良好で、事業も順調に進んでいるときには、経営者同士が互いに協力しあいながら良い関係を継続できるでしょう。
しかし業績が悪化したときや何らかのトラブルが発生したときなど、そのことをきっかけに関係が悪化する可能性もあります。
相手のせいで経営が悪化しているのではないかといった不満がつのることや、業績が悪いのは相手の判断に誤りがあるのではと疑うなど、不信感が大きくなれば人間関係にもヒビが入ってしまいます。
共同で経営しているという近い関係だからこそ、何かをきっかけに信頼関係が崩れやすいことはデメリットといえます。
責任の所在が曖昧
経営者が複数いれば責任の所在が曖昧になりやすいため、業績が悪化しているときやトラブルが発生したときに、誰の責任か明確にできず重大な決断などもできないまま弱い組織を作ってしまう可能性があります。
責任の所在を明確にするためには、各経営者の役割と責任範囲を具体的に定めておくことが重要です。
共同経営は金銭トラブルに発展しやすい
共同経営なら、単独で会社を経営するよりもビジネスの幅を広げることができますが、共同経営だからこそといえるトラブルも発生してしまう可能性もあるといえるでしょう。
複数が一緒に経営を行う形のため、成功すれば事業拡大に繋がりやすいですが、不満などが蓄積され失敗してしまいやすいともいえます。
中でも利益の分配方法など、金銭面でのトラブルや不満が後になって問題になるケースがつきません。
共同経営で出資する配分は、等しい場合もあれば、共同経営者のうちの誰かがその大半、または全額という場合もあります。
たとえ出資比率や意思決定権を平等にしていたとしても、何らかのきっかけで歯車が噛み合わなくなってしまい、人間関係にヒビが生じて事業をやめたいと言いだす経営者が現れればトラブルに発展しやすくなってしまいます。
いざ共同経営を解消しようと考えたとき、企業の所有権や事業の権利などが配分されていれば、協力関係を解消することで事業を存続させることができなくなるリスクも発生します。
そのため共同経営を始めるのなら、事前に様々な取り決めをしておくことが大切です。
共同経営する前に決めておきたいこと
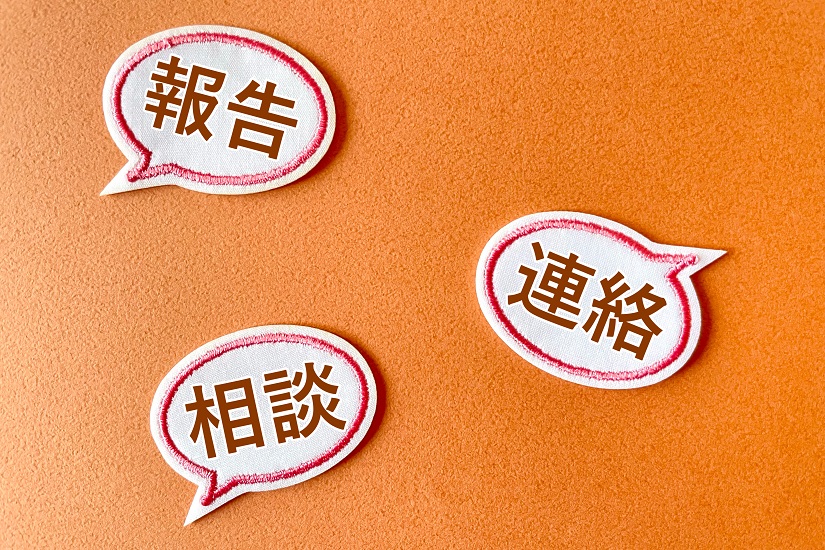
共同経営者の仕事内容がまったく同じであるということはほとんどなく、役割分担ができているようでも金銭が絡むことで、不満や不公平感が増すことに繋がります。
事業に対するビジョンも、本来は同じだったはずなのに、事業を営む上でだんだんと方針を貫き通せなくなることも出てくるようです。
また、事故や病気、家庭族の事情などの環境変化により、事業を続けなることができなくなることもあるかもしれません。
もし共同経営を継続できなくなるだけでなく、他の事情によりお金が必要になれば、やめたいと考えた経営者はできるだけ多くの資金を取り戻したいと考えてしまうでしょう。
そこで、共同経営をやめたいと感じてしまったときのために、事前に次のことを取り決めしておくことが必要です。
- 出資金の負担割合
- 報酬金額
- 肩書
- 担当する分野
- 責任・権限
- 利益分配方法
- 意思疎通の方法
- 相違がある場合の対応方法
- 事業承継に関すること
- 契約解除するときの手続
この中で特に注意したいのが、出資金の負担割合と責任・権限に関する取り決めです。
共同経営を始める前に、万一解消するときにトラブルに発展しないためにも、その後問題になりやすいのが金銭や権限に関することのため、事前に取り決めをおこなっておくことをおすすめします。
共同経営の基本的ルールを共同経営契約書などに記しておき、金銭と権限をどのように割り振るのか明確にしておくことが望ましいでしょう。
経営者は、事業から脱退すること、さらに過去の投資額を払い戻してもらうことを請求する権利があります。
そのため、脱退する場合には、投資した金額のうち戻される部分を取り決めておくとトラブルを回避することに繋がります。
共同経営で失敗しないためのポイント
共同経営で失敗しないためポイントとして、信頼できるパートナー経営者を見つけることが大前提となります。
足りない部分を互いに補いあうことができ、同じビジョンを持ち会社を経営していけるパートナーを選ぶことが必要です。
また、共同で経営することになっても、出資金や支払う報酬などをすべて平等にしようとせず、それぞれが負担する役割や実績・貢献度などで無理なく決めたほうが互いに納得しやすくなります。
長く一緒に経営を続けたいのなら、最初に取り決めをしっかりとしておき、後でトラブルが発生しないようにしておくことも大切です。
信頼できるパートナーに恵まれれば、共同経営により単独経営では得られなかった可能性やメリットを開くことができるでしょう。
経営者の立場が複数人になれば失敗しやすいと考えられがちな共同経営ですが、未然にトラブルを防ぐためポイントを押さえておくだけでも成功確率を高めることができるはずです。
まとめ
共同経営すれば、単独経営ではできなかったことが可能になることや、事業拡大の可能性が広がりやすいといえます。
信頼できるパートナーと一緒に会社を盛り立てていくことができれば、大きな可能性を切り開くことができるでしょう。
しかし、何らかのトラブルで手元のお金が足らなくなり、共同経営を解消しなければならなくなってしまうこともあるかもしれません。
資金ショートすれば共同経営を続けたくても会社は倒産してしまうため、すぐに何らかの方法で資金調達することが必要ですが、保有する売掛債権を売却し現金化するファクタリングなども検討できます。
既に資金繰りが悪化している場合や赤字経営の状況では、銀行融資を断られてしまう可能性が高く、借入の審査も時間が掛かります。
ファクタリングであれば短時間でまとまった資金の準備が可能であり、借金を増やす事なく資金ショートを回避できます。
共同経営を行う中で、手元のお金が不足し、トラブルになった際はご利用を検討してみて下さい。

エンサイドコンサルティング株式会社 代表取締役
「財務会計を経営にリンクさせ、行動変化を起こす」ことをモットーに活動中。財務面では経営状況に応じた資金調達ノウハウ、企業のキャッシュフロー改善に定評あり。
中小企業経営者向け!