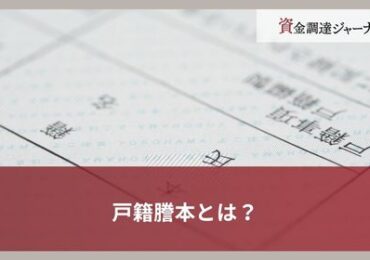MBOとは「Management Buyout(マネジメントバイアウト)」の頭文字の略称です。
M&A手法の一つであり、企業の経営陣が自社株などを買い取ることで、既存株主から経営権を取得できます。
主にMBO(マネジメントバイアウト)は、経営体制の見直しや上場廃止などを目的として実施するといえますが、後継者不足の中小企業などの事業承継にも活用できます。
MBO(マネジメントバイアウト)は買収資金が必要となるため、財務面でのリスクが伴うことや既存株主と対立する恐れがあることは理解しておきましょう。
そこで、MBO(マネジメントバイアウト)とはどのような手法なのか、メリット・デメリットや成功するためのコツをわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

MBO(マネジメントバイアウト)とは
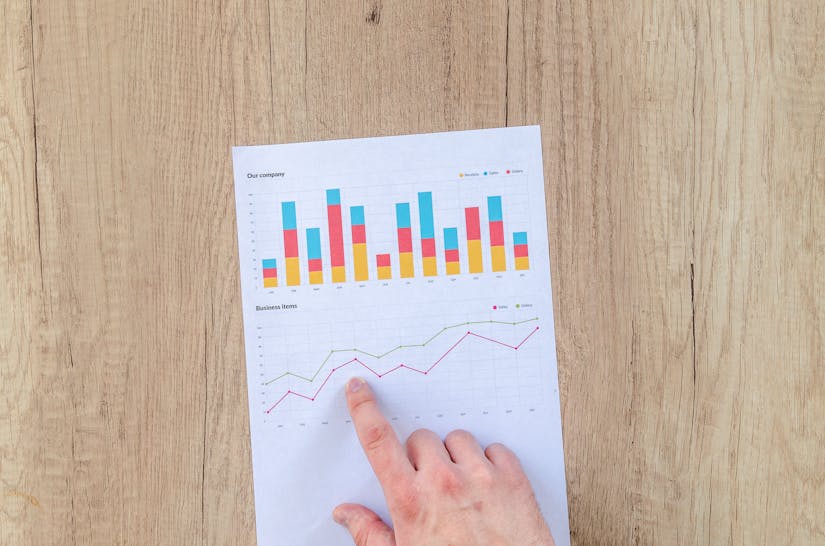
「MBO(マネジメントバイアウト)」とは、会社の経営陣が自社株式や事業部門を買い取ることで、経営権を取得する手法です。
M&A手法の一つであり、金融機関や投資ファンドの支援のもとで、会社の株式や事業を買い取ります。
通常のM&Aでは、誰が買主かにとらわれることなく、株式や事業の取得で買収契約を結びます。
しかしMBO(マネジメントバイアウト)では、買主が経営陣であることが特徴です。
企業が経営のスリム化を目指して事業を切り離すときに、既存役員などが主体となってMBO(マネジメントバイアウト)を進めるケースが多く見られます。
MBO(マネジメントバイアウト)の目的
MBO(マネジメントバイアウト)の「目的」は、経営権を完全取得することです。
IT技術が進歩したことや国の補助などの影響で、株式売買の知名度が高くなりました。
しかし短期で利益を得たい株主が増えたことで、長期的な経営戦略は受け入れられにくくなったといえます。
この場合、MBO(マネジメントバイアウト)により経営の決定権を自社へ戻すことができ、株主からの影響を受けにくくなります。
また、経営状態や自社の情報は株主に公開や報告することが必要です。
関わる者が増えれば企業機密や情報などの漏えいリスクも高まるものの、MBO(マネジメントバイアウト)により情報を厳格に管理できます。
MBOとその他手法との違い

MBO(マネジメントバイアウト)とは、企業の経営陣が株式や事業部門を買い取って経営権を取得することですが、理解を深める上で混同しやすい以下の用語を説明します。
- M&A
- TOB
- MBI
- MEBO
- EBO
- LBO
M&A
「M&A」は「Mergers and Acquisitions」の頭文字の略称であり、企業の合併と買収のことです。
合併と買収の手法には、吸収合併や新設合併、株式買収などがあり、MBO(マネジメントバイアウト)と次に説明するTOBは株式買収の手法に含まれます。
一般的なM&Aは、買い手が外部の第三者であるのに対し、MBO(マネジメントバイアウト)では経営者が株式の買主になります。
TOB
「TOB」は「Takeover Bid」の頭文字の略称であり、上場企業を対象に株式市場外の取引で株式取得を行う手法です。
MBO(マネジメントバイアウト)の対象は、上場と非上場を問いませんが、TOBは上場企業が対象となります。
また、MBO(マネジメントバイアウト)の買主は現在の経営陣であるのに対し、TOBの買主は外部の第三者である場合もあるといった違いも見られます。
そのため、MBO(マネジメントバイアウト)とTOBは、株式の買主である主体が異なります。
MBI
「MBI」は「Management Buy In」の頭文字の略称であり、外部から経営陣を呼び寄せるときの手法です。
MBO(マネジメントバイアウト)では、経営陣が株式や事業部門を買い取って経営権を取得します。
対するMBIは、内部から外部の経営陣へ経営権を渡すため、通常は投資家主導で専門家に経営権を交代させる手続を進めます。
MEBO
「MEBO」は「Management Employee Buyout」の頭文字の略称であり、経営陣と従業員が協調してEBOを行う手法です。
企業の経営陣と従業員が一体となり、ファンドや金融機関などの支援を受けて、企業の株主・親会社・オーナーなどから株式等を買収します。
事業継続を前提とするケースにおいて実施されることが一般的であり、MEBOに参加する従業員はその後も経営へ参加することになります。
従業員が出資しているかが、MBO(マネジメントバイアウト)とMEBOの違いです。
EBO
「EBO」は「Employee Buyout」の頭文字の略称であり、MBO(マネジメントバイアウト)を従業員主導で実践する手法です。
従業員が企業の株式を取得することで経営権を得ます。
企業存続・事業承継・後継者不足などの問題解決に向けて、経営者から従業員に事業承継の目的で活用されることが多い手法です。
経営陣のみが金融機関などと協力して企業の所有者から株式買収する取引がMBO(マネジメントバイアウト)であるのに対し、従業員のみで同様の取引を行うことをEBOといいます。
LBO
「LBO」は「Leveraged Buyout」の頭文字の略称であり、買主が売主の資産などを担保に、金融機関等から融資を受けて資金調達する手法です。
企業買収において金融機関などから資金を借入れ買収する手法であり、てこを効かせた買収を意味します。
LBOは企業やファンドが他社買収の際に、将来のキャッシュフローや資産などを考慮して外部資金(借入金)の調達により買収する手法です。
そのためLBOとMBO(マネジメントバイアウト)の違いは買収手法と誰が譲受主体となるかであり、MBOでは経営陣が引き続き経営権を主導で握ります。
MBO(マネジメントバイアウト)の流れ

MBO(マネジメントバイアウト)は、以下の流れで手続を進めます。
- 対象企業の価値算定
- 株式の受け皿の新会社設立
- 株式取得資金の調達
- 株主からの株式買取
- 対象企業との合併する
それぞれ説明します。
対象企業の価値算定
MBO(マネジメントバイアウト)では、まず対象企業の価値を算定することが必要です。
算定した企業価値に基づいて、株式を取得する金額を決めるため、準備する資金にも影響を及ぼします。
そのため複数の算定方法のうち、どれを選択するのかなど、現状などを踏まえた専門的な判断が必要です。
著しく安い金額で取得してしまうと税務上の課税リスクも発生する恐れがあるため、専門家に相談した上で企業価値の算定を行いましょう。
株式の受け皿の新会社設立
対象企業の価値を算定した後は、経営陣だけで資金調達することが難しいケースが多いため、特別目的会社(SPC)を設立することが一般的です。
特別目的会社の役割は主に株式の受け皿となる新会社であり、株式を買い取る目的のみに設立することが多いといえます。
株式取得資金の調達
設立した新会社が金融機関から株式取得資金を借入れ、必要なお金を準備します。
経営陣自身が金融機関からお金を借りるのではなく、新会社を通す理由は以下のとおりです。
- 個人の資金とは別で管理できる
- 新会社名義にすれば経営陣が負債を負わなくてよい
株主からの株式買取
新会社は借入れが資金で、既存の株主から株式を買い取ります。
取得方法は、たとえば上場会社ではTOBを用いることが多いといえます。
対象企業との合併する
新会社が株式を取得した後は、MBO対象企業を子会社化する流れです。
MBO対象企業との合併により、経営陣が株主として経営権を獲得します。
MBOのメリット

MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、主に以下の7つです。
- 独立経営を実現できる
- 中長期で経営できる
- 自由に経営できる
- 従業員から理解を得やすくなる
- TOBを回避できる
- コストを削減できる
- 円滑な事業承継につながる
それぞれ説明します。
独立経営を実現できる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、独立経営を実現できることです。
もともと大株主や親会社の影響をなくし、自由に経営したいときに選ばれやすい手法といえます。
そのため、経営陣が株主になった後は、第三者の株主の意見は取り入れる必要はありません。
独立した経営の実現が可能となることがメリットです。
中長期で経営できる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、中長期での経営が可能になることです。
多数の株主や投資家などが存在すると、いろいろな意見を取り入れた上で経営を進めなければなりません。
短期的な業績や利益を求める株主が多ければ、中長期的な視点は無視した経営判断を求められてしまいます。
MBO(マネジメントバイアウト)を実践すれば、経営陣が株主になります。
そのため、両者の考え方で埋められないギャップや隙間をなくし、短期的な業績などにこだわらない中長期的視点で事業展開が可能です。
自由に経営できる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、自由に経営できることです。
複数の株主が存在していると、経営意思決定では株主総会の開催・決議を経ることが必要になり、決定・実行まで一定の時間がかかります。
MBO(マネジメントバイアウト)で経営陣が株主になれば、経営判断の自由度を高め、迅速に意思決定できます。
従業員から理解を得やすくなる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、従業員から理解を得やすくなることです。
一般的なM&Aでは、外部の第三者に経営権が取得されてしまうため、従業員の雇用継続や雇用条件に不安が生じます。
しかしMBO(マネジメントバイアウト)によるM&Aなら、今の経営陣が経営権を得るため、従業員に大きな変化があらわれることはないため理解も得やすいでしょう。
TOBを回避できる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、TOBを回避できることです。
TOBは外部の第三者が株式を取得するため、企業にとって望ましいといえない買主があらわれる恐れもあります。
しかしMBO(マネジメントバイアウト)の株主は現在の経営陣であるため、TOBの対抗策として有効です。
コストを削減できる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、コストを削減できることです。
たとえば上場企業の場合、ブランディング・人材確保・資金調達の多角化など様々なメリットがある反面、企業情報開示に伴う社内体制整備が必要など維持コストが多額に発生します。
上場によるメリットと維持する費用を比較したとき、上場するメリットが大きくないのであれば、MBOで非上場化することでコストを削減できます。
円滑な事業承継につながる
MBO(マネジメントバイアウト)のメリットは、円滑な事業承継につながることです。
中小企業では親族に後継者候補がいない場合もあるといえますが、MBO(マネジメントバイアウト)では現在の経営陣に会社を引き継ぎます。
後継者の資金力が足らず、株式取得資金を調達できないときでも、新会社(特別目的会社)を設立したスキームを使えば円滑な事業承継につながります。
既存の組織風土や文化の分断もなく、よりよい再構築も可能です。
MBOのデメリット
メリットの多い手法であるMBOは、実践する上で以下の4つのデメリットに注意が必要です。
- 株主と対立する恐れがある
- 主観的な経営になりやすい
- 資金調達の選択肢を失う恐れがある
- 財務状況が悪化する恐れがある
それぞれ説明します。
株主と対立する恐れがある
MBO(マネジメントバイアウト)のデメリットは、既存の株主と対立する恐れがあることです。
既存の株主から株主と買い取る手法であるため、できるだけ安く買いたい経営陣と、高く売りたい株主では価格が決まりません。
対立が激化すれば、取得金額が想定していたより高額になる場合や、売却に応じない株主の残存といった問題が起こる場合もあるため注意してください。
主観的な経営になりやすい
MBO(マネジメントバイアウト)のデメリットは、主観的な経営になりやすいことです。
すべての株式を取得すれば、経営陣主導による意思決定がスムーズになり、大胆な施策を打つことも可能となります。
ただし経営陣のみが先走れば、外部から客観的意見を取り入れることはなくなり、従業員の退職や顧客離れが進む恐れも否定できません。
資金調達の選択肢を失う恐れがある
MBO(マネジメントバイアウト)のデメリットは、資金調達の選択肢を失う恐れがあります。
たとえば上場企業のMBOは上場廃止を意味するため、株式発行で外部からの資金調達は難しくなるでしょう。
そのため主な資金調達手段は、金融機関から融資を受けることや、経営陣による増資となり、選択肢が狭くなりがちです。
金融機関の借入れでは債務増加につながり、多額の負債によるキャッシュフロー悪化などが懸念されます。
資金面に大きな影響がでることは踏まえた上での検討が必要といえます。
なお、資金調達には、融資や増資以外にもファクタリングを使うなど、選択肢の幅を広げる手段としての検討をおすすめします。
ファクタリングとは?意味や仕組み・メリットと注意点をわかりやすく解説
財務状況が悪化する恐れがある
MBO(マネジメントバイアウト)のデメリットは、財務状況を悪化させる恐れがあることです。
潤沢な資金があれば特に問題はないものの、資金不足で新会社による借入れを頼り資金調達すれば、融資を受けたことにより負債が増えます。
MBO後に返済負担が重くなれば、財務状況を悪化させる恐れもあるため、利子の支払いも考慮した上で経営を行うことが必要です。
MBO(マネジメントバイアウト)を成功させるコツ

MBO(マネジメントバイアウト)を成功させるためには、以下の3つを押さえた上で実践するとよいでしょう。
- 将来のビジョンを明確にしておく
- 株主との対立を避ける工夫をする
- 専門家へ相談する
それぞれ説明します。
将来のビジョンを明確にしておく
MBO(マネジメントバイアウト)を成功させるためには、将来のビジョンを明確にすることが大切です。
企業を存続・成長させるためには、実施後の将来像を明確にしておきましょう。
MBO後の施策や株式取得で調達した借入金返済が滞りなくできるかなど、実施前から入念に計画することが重要といえます。
株主との対立を避ける工夫をする
MBO(マネジメントバイアウト)を成功させるためには、株主との対立を避ける工夫をしましょう。
経営陣は株式をできる限り安く購入したいと考えるのに対し、既存の株主はできるだけ高く売りたいと考えることが多いといえます。
この場合、利害対立が生じることになり、対立激化によって計画以上の株式取得資金が発生したり一部の既存株主の残存問題が起こったりして不成立になる恐れもあります。
スムーズにMBOを成功させるためには、株主との交渉方法や金額などを含めた対立を発生させない準備と交渉が欠かせません。
専門家へ相談する
MBO(マネジメントバイアウト)を成功させるためには、専門家への相談も欠かせません。
既存株主への交渉や、実施後の資金繰り計画、価格決定などは専門的な知識が必要です。
不足する知識は必要に応じてコンサルタントなどの専門家を頼り、アドバイスやサポートを受けたほうが安心しといえます。
まとめ
MBO(マネジメントバイアウト)により、中長期的視点で会社を経営でき、企業経営の自由度やスピードを高められます。
ただし既存の株主と利害対立が発生することや、資金調達での負債発生などが起こる恐れもあるため、現状を踏まえた検討が必要です。
MBOは企業の存続や成長の手段であり、経営方針や計画の事前検討が欠かせません。
実施における事業計画・企業価値算定・資金調達・既存株主との交渉などは、専門的な知識を必要とする部分でもあります。
そのため、マネジメントに詳しいコンサルタントに相談することも検討しましょう。
中小企業経営者向け!