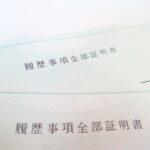DX人材育成が経営課題である企業は少なくありません。
少子高齢化により、人材不足が深刻化する業種や業界は増えつつあるといえます。
しかし、解消の手段として、外部やアウトソーシングの活用ではなく、既存の従業員をDX人材に育成することの検討も増えています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術の活用により業務プロセス・企業文化・ビジネスモデルなどを改革して、競争力維持や強化などを目的とした取り組みです。
デジタル化は業務効率化が目的であるのに対し、DX化は新しい価値の創造や顧客体験の革新などを目的としており、推進過程でデジタル化を推進します。
デジタル化もDX化のフローの1つであり、取り組みを支えるために必要なことがDX人材育成です。
そこで、DX人材育成の方法について、デジタル化の課題やメリット、注意点を徹底解説します。
中小企業経営者向け!

目次
DX人材とは

「DX人材」とは、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に必要な知識や技術、考え方を持つ人材のことです。
特に明確な定義はないものの、以下の能力や素養が求められます。
|
「DX」とは、ビジネス環境の激しい変化への対応や競争上の優位性を確立するために以下を行うことです。
|
役割によって、求められるスキルの濃淡・内訳が異なります。
DX人材の職種
DX人材の職種として、以下が挙げられます。
|
上記の業種においては、どの事業に注力するべきか、重視するべき技術領域などを発掘し、担当者からの提案を適切に判断できるスキルが求められます。
ビジネス・サービス設計・データサイエンス・エンジニアリングの領域でも、事業理解や技術動向を把握できる能力が最低限必要といえます。
求められる能力が高いため、現場のDX人材は足りていない状況です。
人材不足を解消するために、採用や外部リソースの活用以外にも、従業員のDX人材育成を検討することが必要と考えられます。
DX人材不足が深刻化している背景
DX人材は、みずほ情報総研株式会社が2019年3月に発行した「IT人材需給に関する調査」によると、2030年に最大79万人不足すると想定されています。
さらにIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「DX白書2023 第4部 デジタル時代の人材」を見ると、DX人材について「大幅に不足している」と回答した割合は2021年の30.6%から2022年49.6%へと大幅に増えています。
経済産業省もDX化を推進する上で、DX人材不足を大きな課題としているため、解消に向けた取り組みが急務といえます。
足りていないDX人材は採用活動で確保すればよいと考えがちであるものの、転職市場でもDX人材が慢性的に不足しており、優秀なDX人材採用は困難です。
そこで、内部の人材に必要な能力を獲得させて、DX人材育成を進めることが注目されています。
会社と従業員の双方が、変化の激しいビジネス環境で生き残るためにも必要な戦略といえます。
DX人材育成の課題

DX人材育成が急務の中、実施する上では以下の課題が障壁になることも少なくありません。
- 求める能力や経験が曖昧である
- 自主性を促しにくい
- 学習方法が定まっていない
- 実務に活かしにくい
- 売上拡大まで繋がりにくい
それぞれ解説します。
求める能力や経験が曖昧である
DX人材育成の課題として、求める能力や経験が曖昧であることが挙げられます。
最近できた概念であるDX化に関して、方向性を定められていない会社も存在します。
その中でDX人材育成に取り組みたくても、どのような能力が必要なのか、何を学んでもらい身につけてもらうべきか曖昧で決められないことも少なくありません。
自主性を促しにくい
DX人材育成の課題として、自主性を促しにくいことが挙げられます。
企業側がDX人材育成に前向きでも、教育を受ける従業員に自主性がなければ、求められる人材に育ちにくくなります。
DXの重要性への理解や、デジタルへの興味、ビジョン達成へ意識などが足らない人材の場合、自主性は促しにくいと考えられます。
学習方法が定まっていない
DX人材育成の課題として、学習方法が定まっていないことが挙げられます。
求める能力や経験が曖昧であることにも共通しますが、どんな内容を何で学んでもらうのかなど、学習を進める上でのフェーズが決まらなければ育成につながりません。
実務に活かしにくい
DX人材育成の課題として、DX関連の知識などが実務に活かしにくいことが挙げられます。
学習サービスなどを使った場合、学ぶことのできる内容は汎用的な知識などです。
どの部署に何を依頼するべきか、社内に存在しない必要なデータをどのように調達すればよいのかなど、方法がわからなければDX関連の知識を活かせません。
売上拡大まで繋がりにくい
DX人材育成の課題として、売上拡大までつながりにくいことが挙げられます。
デジタル人材の教育に成功しても、売上げや新規ビジネス創出へ絶対につながるとは言い切れません。
推進したいサービスが市場で受け入れてもらえないケースなどでは、個別の業務や製造プロセスのデジタル化にとどまります。
DX人材育成のメリット

DX人材を採用で補うのではなく、既存の従業員へのDX人材育成を進めることは、以下の6つのメリットがあるといえます。
- 現状把握につながる
- 事業内容の理解につながる
- システムの一貫性を保てる
- 既存システムと整合性が保てる
- 社内体制を構築できる
- 最適なDX化を実現できる
それぞれ説明します。
現状把握につながる
DX人材育成のメリットとして、現状把握につながることが挙げられます。
自社の内情に精通している従業員をDX推進の中心メンバーに迎えるため、部門ごとのキーパーソンも把握しており、誰に何を伝えれば物事が円滑に進むか理解できています。
部門や個人のデジタルリテラシー能力なども把握できていれば、相手に合わせて話をすることができ、摩擦を生まずにDX化を推進できます。
事業内容の理解につながる
DX人材育成のメリットとして、事業内容の理解につながることが挙げられます。
外部から人材を登用すると、自社ビジネスに対する理解が浅く、求める内容と異なる施策になる恐れがあります。
内部の従業員なら、取り扱う商品やサービス、顧客やマーケットなどをすでに熟知できているため、現状の問題点や優先課題を把握できています。
事業内容を理解しつつ、的を絞って効果的なDX化を推進できることはメリットです。
システムの一貫性を保てる
DX人材育成のメリットとして、システムの一貫性を保てることが挙げられます。
たとえば外部ベンダーに業務委託するとき、エンジニアの能力により既存システムとの互換性に問題が生じることや、一貫性のないシステムになる恐れもあります。
社内でDX人材育成を行えば、計画立案・開発・テスト確認まで一気通貫で実施できるため、システムの一貫性が保たれます。
既存システムと整合性が保てる
DX人材育成のメリットとして、既存システムと整合性が保てることが挙げられます。
社内の既存システムの現状を理解できている従業員がDX推進を担当すれば、既存システムの使いにくい部分や効率化を阻害する点を把握できているため、効果的な対策を検討しやすくなります。
新たなシステムを導入するケースでも、既存システムとの互換性を意識して選定できるため、結果的にコストを抑えられます。
社内体制を構築できる
DX人材育成のメリットとして、社内体制を構築できることが挙げられます。
社内で業務内容を深く理解している従業員からDX人材を選んで育てます。
そのため、組織変換や事業転換などにも迅速に対応できる人材育成にもつながり、万全の社内体制を構築しやすくなります。
最適なDX化を実現できる
DX人材育成のメリットとして、最適なDX化を実現できることが挙げられます。
既存業務の改善や新規事業の開発の際にDX化を検討することが多いといえます。
そのため、業務やシステムを熟知している従業員がDX人材を対応すれば、正しい企画の立案や開発が可能となります。
その結果、最適なDX化の実現につながるでしょう。
DX人材育成の注意点
DX人材育成を進めるときには、以下の2つには注意が必要です。
- 開発フェーズの導入が必要
- 育成の可視化と共有が必要
それぞれ説明します。
開発フェーズの導入が必要
DX人材育成の注意点として、開発フェーズの導入が必要であることは理解しておきましょう。
小規模なプロジェクトから取り組むために、計画・設計・実装・テストの4つのフェーズを繰り返し、開発を進めるアジャイル開発を取り入れます。
複数のプロジェクトへと細かく区切り、小単位で実装とテストを繰り返すため、それぞれの完了までの期間の短期化や難易度の引き下げにながり、育成段階のDX人材でも携わりやすくなります。
育成の可視化と共有が必要
DX人材育成の注意点として、育成の可視化と共有が必要であると理解しておきましょう。
全社にビジョンや育成における過程を伝えることで、他の部署からもサポートを得ることや失敗への寛容な環境をつくれます。
成功体験の共有も可能となるため、全体でのモチベーションを向上させて次のイノベーションにつなげることも可能です。
DX人材育成のポイント

既存の従業員をDX人材へと育成するのなら、まずは担当者の人選が需要です。
候補者を選定し適性を見極めることは欠かせませんが、以下のポイントを押さえた上で進めましょう。
- 能力と素養の可視化する
- 適した人材を選ぶ
- 人材育成計画を策定する
- 座学で知識をインプットする
- OJTで実務経験を育む
- 実務能力をアウトプットする
- 社内外でネットワークを繋げる
- 実践力を強化する
それぞれ説明します。
能力と素養の可視化する
DX人材育成のポイントとして、能力と素養の可視化することが挙げられます。
従業員の能力や素養を可視化し、現状把握からスタートすることが必要です。
能力ごとにグループ分けして、適切な人材配置や育成計画などにつなげます。
個人の育成プログラムを最適化することや、モチベーションアップにもつながるでしょう。
適した人材を選ぶ
DX人材育成のポイントとして、適した人材を選ぶことが挙げられます。
会社や業務の問題点に対する意識の高さや、深い探究心などが備わっていることが理想です。
DX化を推進するリーダー育成においても、部門の業務に精通していることだけでなく、リーダーシップやコミュニケーション能力を備えた人材を候補とすることが必要となります。
特定の部門や役職、年次などに制限せずに幅広い層から選ぶことが大切です。
人材育成計画を策定する
DX人材育成のポイントとして、人材育成計画を策定することが挙げられます。
何を目的として、いつまでにどのような人材を何人育成するのか、計画を策定しましょう。
そのためにも現状把握と求める人材要件、個人のスキルやマインド、目標に合わせた最適なプログラムを設計することが必要です。
座学で知識をインプットする
DX人材育成のポイントとして、座学で知識をインプットすることが挙げられます。
体験学習や社外講師による講義などが有効といえますが、デジタルのスキル以外の能力も必要です。
自発的な行動を促すためにリーダーシップスキルなども求められるため、変革を恐れず周囲を巻き込むスキルも必要と理解しておきましょう。
OJTで実務経験を育む
DX人材育成のポイントとして、OJTで実務経験を育むことが挙げられます。
OJTとは、実際に実務経験を通して人材を育成する手法です。
そのためにも社内に限定した小規模なプロジェクトから、少しずつ活用する方法や実行する術を身につけることが求められます。
実務能力をアウトプットする
DX人材育成のポイントとして、実務能力をアウトプットすることが挙げられます。
実務能力とは、知識・スキル・解決力などの掛け合わせであり、不足していれば業務での成果につながりません。
分析手法は理解できているものの、どこから対象のデータを準備すればよいかわからない壁にぶつかったときのために、インプット・アウトプット・プロのフィードバックを繰り返しましょう。
インプット後はアウトプットの数と質を高めることも必要です。
社内外でネットワークを繋げる
DX人材育成のポイントとして、社内外でネットワークを繋げることが挙げられます。
社外ともネットワークをつなげることで、最新の情報を得られる環境の構築につながります。
スピードのはやい市場の変化に対応するために、最新の知識や技術を常に学び、キャッチアップすることは欠かせません。
実践力を強化する
DX人材育成のポイントとして、実践力を強化することが挙げられます。
日々の業務で小さな実践を可能とする機会を創り出し、学んだことは短期間で多くの経験につなげることが必要です。
手元のデータを分析し、示唆を導き出す成功体験を積むことで、周りを巻き込みながら経験規模を少しずつ広げられます。
DX人材育成に活用できる制度

DX人材育成に限らず、人を育てるためには費用がかかります。
そこで、厚生労働省では人材育成やスキルアップに活用できる制度を設けていますが、その1つが「人材開発支援助成金」です。
人材開発支援助成金には以下の7コースが用意されています。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
それぞれ紹介します。
詳しい要件などは、厚生労働省の公式ホームページ内の「人材開発支援助成金」で公開されています。
人材開発支援助成金とは?人材育成の制度と支給額・申請の流れを紹介
人材育成支援コース
「人材育成支援コース」とは、従業員に職務関連の知識や技能を習得させる訓練を計画に実施したときの助成金制度です。
対象となる訓練として、以下が挙げられます。
|
訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成金として受け取ることができますが、1年度中に受給できる助成額は1000万円までとされています。
教育訓練休暇等付与コース
「教育訓練休暇付与コース」とは、教育訓練を目的に導入した休暇制度や短時間勤務制度を労働者が利用し、訓練を受けたときに受けられる助成金制度です。
対象となるのは、導入した有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を取得して受けた訓練で、支給額は30万円(賃金要件と資格等手当要件を満たせば36万円)とされています。
人への投資促進コース
「人への投資促進コース」とは、令和8年度までの期間限定助成制度であり、訓練にかかった経費や訓練期間中の賃金の一部などが支援される助成金制度です。
対象となる訓練として、以下が挙げられます。
|
1年度中に支給される金額は、成長分野等人材訓練を除き、人への投資促進コースで2500万円までです。
事業展開等リスキリング支援コース
「事業展開等リスキリング支援コース」は、知識や技能の訓練を労働者へ行ったとき、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が1年度中1億円まで助成されます。
対象となる訓練は、新規事業立ち上げや事業展開、DX・GXに伴って新たな分野で必要となる知識や技能の訓練を実施したときです。
建設労働者認定訓練コース
「建設労働者認定訓練コース」は、建設労働者に有給で認定職業訓練または指導員訓練を受講させたとき、建設関連の訓練でかかった経費の一部や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
建設事業主の雇用環境改善や、建設労働者の技能向上を図る取り組みが助成の対象となる制度であり、1事業所に対する1年度の支給額の合計は1000万円が上限とされています。
建設労働者技能実習コース
「建設労働者技能実習コース」とは、建設労働者の技能向上を目的に有給で研修や訓練を受講させたときの経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
建設労働者の雇用環境改善や、建設労働者の技能向上などの取り組みを支援するための制度であり、1事業所に対する1年度の支給額の合計は500万円が上限とされています。
障害者職業能力開発コース
「障害者職業能力開発コース」は、障害者の職業に必要とする能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続して行う施設の設置・運営にかかる費用の一部を支給する制度です。
事業主の負担する費用の一部を助成することで、障害者の雇用促進や雇用継続を図ることを目的とした制度といえます。
障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設、または設備の設置・整備・更新にかかった費用の4分の3が支給されます。
上限は、初めて助成金対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備で5000万円、訓練科目ごとの施設または設備の更新で1000万円とされています。
まとめ
DX化に向けたDX人材育成は、社外から新たな人材を採用するよりもメリットが大きいといえます。
ただし正しく取り組みを進めていくために、既存の従業員から最適な人材を選ぶことが需要です。
適性を見極めることはもちろんのこと、自社に最適な育成体制の構築を目指すことが必要となります。
中小企業経営者向け!