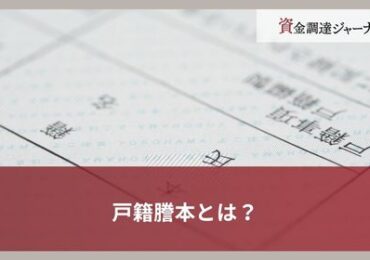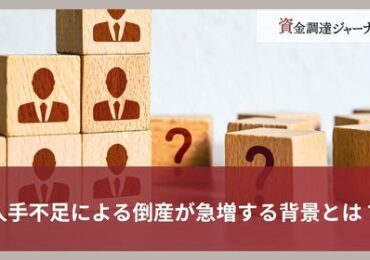「与信調査ってどうすればいいのだろう?」
「与信調査が難しい」
このようなお悩みはありませんか?
与信調査は、取引先の信用度を判断し、リスクを軽減するために重要です。
適切な方法で実施することで、安全な取引が可能になります。
この記事では、与信調査の基本から実践的な活用方法まで詳しく解説します。
取引先との良好な関係を築きながら、自社を守るための参考として、ぜひ最後までお読みください。
中小企業経営者向け!

与信調査とは
与信調査とは、企業が取引を行う相手の信用度や財務状況を評価するための調査です。
企業間取引においては、サービス提供後に代金を受け取る「掛取引」が一般的ですが、相手の経済状況が不明確だと未回収リスクが高まります。
与信調査を実施することで、取引先の財務状況や経営状態を把握し、リスクを最小限に抑えられます。
与信調査の必要性と分かること
与信調査は、企業が取引先の信用力を評価し、リスクを最小限に抑えるために必要不可欠です。
取引先の財務状況や経営状態を把握することで、未回収リスクを減少させ、健全なビジネス関係を構築できます。
具体的には、与信調査を通じて以下の点が明らかになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務状況 | 取引先の資産、負債、収益などの財務データを確認し、支払い能力を評価する |
| 経営状態 | 経営者の信用度や会社の経営方針、過去の経営実績を調査し、企業の安定性を判断する |
| 取引履歴 | 取引先の過去の取引履歴や支払い遅延の有無を確認し、信用リスクを評価する |
これらの情報をもとに、企業は取引先とのビジネス関係を継続するかどうか、または取引条件を見直す必要があるかを判断できます。
与信調査と信用調査
「与信調査」と「信用調査」は、どちらも取引先企業の支払い能力や経営状況などを調べることを指し、ほとんど同じ意味で使われています。
ただし厳密に区別すると、「与信調査」は取引先の信用力を数値化して評価する、より具体的な調査を指す場合もあります。
しかし、一般的には両者を区別せずに、同じ意味で使うことが多いです。
企業の与信調査の種類と特徴

企業の与信調査には、主に以下の4つの種類があります。
- 直接調査
- 外部調査
- 社内調査
- 依頼調査
それぞれ特徴が異なり、状況に応じて使い分けることが重要です。
企業規模や取引の重要性、必要な情報の深さなどを考慮し、適切な調査方法を選択することで、より正確な与信判断が可能になります。
ここでは、4種類の調査方法について、特徴やメリット・デメリットを紹介します。
直接調査
直接調査は、取引先企業に直接アプローチして情報を収集する方法です。
この方法の特徴は、最新かつ詳細な情報を得られることです。
直接調査の方法としては、訪問や電話による聞き取りが一般的に用いられています。
メリット:
- 取引先との直接のコミュニケーションにより、信頼関係を構築できる
- 財務諸表や事業計画など、最新の情報を入手できる
- 経営者の人柄や経営方針など、数字には表れない情報も得られる
デメリット:
- 時間と労力がかかる
- 相手企業の協力が得られない場合、十分な情報が得られないことがある
- 調査担当者の経験や能力によって、得られる情報の質に差が出る可能性がある
直接調査は、特に重要な取引先や大口の取引を検討している場合に有効です。
取引先と直接対話することで、財務情報だけでなく、経営方針や将来の展望などの情報も得られます。
ただし、取引先との良好な関係を維持しながら、必要な情報を適切に収集する技術が求められます。
外部調査
外部調査は、公開情報や外部機関が提供するデータを利用して情報を収集する方法です。
具体的には、インターネットでの情報収集や官公庁の公開情報の確認、業界団体の情報利用などが含まれます。法務局では、企業の基本情報が記載された商業登記簿や、資産状況を知るための不動産登記簿を確認できます。
メリット:
- 比較的低コストで実施できる
- 客観的な情報が得られる
- 取引先に負担をかけない
デメリット:
- 情報が古い場合がある
- 詳細な内部情報は得られない
- 情報の信頼性の確認が必要
外部調査は、新規取引先の初期評価や既存取引先の定期的なモニタリングに適しています。
特に、上場企業など公開情報が豊富な企業の調査に効果的です。
ただし、得られる情報の鮮度や深度には限界があるため、他の調査方法と組み合わせて使用することが望ましいでしょう。
社内調査
社内調査は、自社内の既存データや営業担当者の情報を活用する方法です。
過去の取引履歴や支払い状況、営業担当者の日々の取引先とのやり取りなどが情報源となります。
メリット:
- コストがかからない
- 迅速に情報が得られる
- 自社との取引に直結した情報が得られる
デメリット:
- 情報の客観性に欠ける場合がある
- 情報が限定的または偏っている場合がある
- 新規取引先の場合は情報が不足する
社内調査は、既存取引先の継続的な与信管理に適した方法です。
日々の取引を通じて得られる情報は、取引先の現状把握に役立ちます。
ただし、個人の主観や偏見が入り込む可能性があるため、他の調査方法と組み合わせて総合的に判断することをおすすめします。
依頼調査
依頼調査は、自社で十分な与信調査が難しい場合に、専門の調査会社などに依頼して行う調査方法です。
直接調査や社内調査と比較して、より詳細かつ客観的な情報を得られるという特徴があります。
メリット:
- 専門的かつ詳細な調査が可能
- 客観的な評価が得られる
- 自社のリソースを節約できる
デメリット:
- 高コストになる場合がある
- 調査結果の入手に時間がかかる
- 調査会社によって情報の質にばらつきがある
- 情報が外部に漏洩するリスクがある
依頼調査には大きく分けて「照会調査」と「依頼調査」の2種類があります。
| 調査の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 照会調査 | 取引先や取引先の関係先に対して取引の情報や経営内容について照会を行う方法。比較的簡便で費用も抑えられるが、得られる情報が限定的な場合がある。 |
| 依頼調査 | 企業調査を専門的に行っている調査会社に調査を依頼する方法。詳細な調査が可能だが、費用が高額になる場合がある。 |
依頼調査は、特に重要な取引先や大口の与信枠を設定する際に有効です。
ただしコストがかかるため、取引先の重要度や取引規模に応じて、適切に使い分けることが重要です。
これらの調査方法を組み合わせることで、より精度の高い与信調査が可能になります。また、定期的に調査を行い、取引先の信用状況を一覧で管理することで、リスクを早めに見つけ出し、適切な対策を講じられます。
与信調査は継続的な課題であり、常に最新の情報を収集することが重要です。
与信調査を行うべきタイミング

与信調査は、取引先の信用リスクを管理するために定期的に実施することが重要です。
特に以下のタイミングで行うことが推奨されます。
- 新規取引開始時
- 定期的な取引先の再評価時
- 取引条件変更時
- 業界動向や経済環境の大きな変化時
新規取引開始時の調査
新規取引を開始する際には、取引先の信用度を事前に確認することが欠かせません。
この段階での与信調査は、将来的なリスクを予防する上で重要な役割を果たします。
具体的には、取引先の財務状況、過去の支払い履歴、業界での評判などを総合的に評価します。
調査方法としては、信用調査会社のレポートを活用したり、直接取引先から財務諸表を取り寄せたりすることが一般的です。
また、業界内のネットワークを活用して情報収集を行うことも効果的です。
新規取引開始時の与信調査を適切に行うことで、売掛金が未回収になるリスクを最小限に抑え、健全な取引関係の基盤を築けます。
さらに、この調査結果をもとに適切な取引条件(与信限度額、支払い条件など)を設定することで、リスク管理の効率化にもつながります。
例えば、信用力の低い取引先には、少額の取引から始める、または前払いを要求するなどの対策を取ると安心です。
定期的な取引先の再評価
取引先の信用状況は時間とともに変化するため、定期的な再評価が重要です。
一般的には、年1回程度の頻度で実施することが推奨されますが、取引規模や業界の特性に応じて適切な頻度を設定する必要があります。
定期的な再評価では、取引先についての最新の財務状況や支払い履歴、経営者の変更などの情報を収集し、分析します。
また、自社との取引状況(支払いの遅延有無など)も重要な評価要素の一つです。
再評価の結果、信用状況に変化が見られた場合は、与信限度額の見直しや取引条件の変更を検討します。
例えば、信用状況が改善した取引先に対しては与信限度額を引き上げ、逆に悪化した取引先に対しては限度額を引き下げるなどの対応を取ります。
定期的な再評価を通じて、取引先の信用リスクを継続的に管理することで、適切な取引関係を維持できるのです。
また、再評価の過程で明らかになった課題を一覧にまとめ、優先順位を付けて対応することも効果的な方法です。
取引条件が変更したとき
取引条件の変更時には、取引先の経営状況や信用度を再確認することが不可欠です。
特に、取引額の増加や支払い条件の緩和など、自社のリスクが増大する可能性がある場合は、慎重な与信調査が必要です。
具体的には、取引先の最新の財務諸表を入手し、流動比率や自己資本比率などの財務指標を分析します。
同時に業界動向や市場環境の変化が取引先に与える影響も考慮しなければなりません。
必要に応じて、取引先への訪問や電話による直接確認も効果的です。
調査の結果、リスクが許容範囲内であると判断された場合は、新しい取引条件での取引を開始します。
一方、リスクが高いと判断された場合は、取引条件の再交渉や追加の担保設定などの対策を検討します。
取引条件変更時の適切な与信調査により、リスクを適切に管理しつつ、取引先との良好な関係を維持できるのです。
業界動向が大きく変化したとき
取引先の業界や経済環境に大きな変化があった場合も、与信調査を行うべきです。
例えば、取引先の業界に新技術が導入されたり、法規制が変更されたりした場合、その影響を評価する必要があります。
また、リーマンショックやコロナ禍のような急激な経済変化の際には、多くの企業の財務状況が悪化する可能性があります。
このような状況では、業界全体の動向を分析するとともに、個々の取引先がその変化にどのように対応しているか、調査が必要です。
具体的には、取引先の事業戦略の変更、新規投資の状況、財務への影響などを確認します。
調査方法としては、業界レポートや専門家の分析を活用したり、取引先との直接対話を通じて情報を収集したりします。
また、同業他社との比較分析も有効です。
業界動向の変化に応じた与信調査を行うことで、潜在的なリスクを早期に発見し、適切な対応策を講じられます。
これにより、業界変化に伴う取引リスクを最小限に抑えることが可能です。
具体的な与信調査会社と選び方

与信調査を効果的に行うためには、信頼性の高い調査会社を選ぶことが重要です。
主な与信調査会社には、信用調査会社と格付け会社があります。
これらの会社を適切に選択し活用することで、取引先の信用リスクを正確に評価し、適切な与信管理をすることが可能になります。
代表的な調査会社と、選び方のポイントについて以下にまとめました。
信用調査会社
信用調査会社は、企業の財務情報や取引実績など、幅広い情報を収集・分析します。
中小企業経営者が選ぶ際は、調査対象企業の規模や業種に強みを持つ会社を選ぶことがポイントです。
また、レポートの読みやすさや価格も重要な選択基準となります。
ここでは、代表的な信用調査会社をいくつか紹介します。
東京商工リサーチ
東京商工リサーチは、1892年に創業された老舗の信用調査会社です。
全国の調査員による直接ヒアリングと豊富な情報源を活用し、企業の財務状況や経営状態、業界動向など、与信管理に不可欠な情報を提供します。
特に注目すべきは、多角的な視点から企業を評価する「評点」と倒産確率を示す「リスクスコア」です。
新規取引先の評価や既存取引先の定期チェック、ライバル企業分析など、さまざまな目的に活用可能で、経営判断の重要な材料となります。
オンラインでの迅速な情報提供も行っており、多様なニーズに対応しています。
帝国データバンク
帝国データバンクは、1900年創業の信用調査会社です。
全国83カ所に拠点があり、金融機関や大企業から中小企業まで幅広い顧客に利用されています。
企業の財務情報や信用情報を提供するだけでなく、以下のような多岐にわたるコンサルティングサービスも展開しています。
- 投資先選定
- 市場分析
- ISO認証取得支援
- 人材育成
- リスクヘッジ
また、企業情報の一元管理や効率的なターゲットリスト作成など、顧客の業務効率化にも貢献しています。
リスクモンスター
リスクモンスターは、2000年設立の比較的新しい信用調査会社ですが、中小企業向けに特化したサービスで急成長しています。
独自のリスク評価システムを用いて、財務情報だけでなく非財務情報も分析し、企業の将来的なリスクを予測します。
他にも、オンラインツールを提供しており、リアルタイムでの情報更新と与信管理が可能です。
約14,000の会員企業に利用され、特に日々の与信管理業務や取引先のモニタリングに強みを持っています。
経営リスクを重視する企業やスタートアップ企業の評価に適した信用調査会社といえます。
格付け会社
格付け会社は、企業や金融商品の信用力を客観的に評価し、その結果を格付けとして提供する専門機関です。
特に中小企業の経営者にとって、取引先や投資先の信用状況を把握するための重要な情報源となります。
ここでは、代表的な格付け会社を紹介します。
日本格付研究所(JCR)
日本格付研究所(JCR)は、1985年に設立された日本を代表する格付け会社です。
国内外の企業や金融商品の信用格付けを行い、投資家に対して信頼性の高い情報を提供しています。
特に日本企業に強みを持ち、国内の経済・産業動向を踏まえた分析を提供しています。
ウェブサイトでは、格付け情報や経済レポートを無料で閲覧できるため、業界動向の把握にも有用です。
格付投資情報センター(R&I)
格付投資情報センター(R&I)は、企業や金融商品の信用格付けを行う大手の格付け会社です。
業界全体の動向を把握し、詳細なリサーチに基づいた格付けを提供しています。
特に、投資家向けに分かりやすい報告書を作成し、信用リスクを明確に示すことに力を入れています。
また、国際的な格付け基準を導入しており、国際的な投資家からも信頼されている会社です。
企業の財務情報だけでなく、業界のトレンドやマクロ経済の影響も考慮した総合的な評価もできることが特徴です。
ムーディーズ・ジャパン
ムーディーズ・ジャパンは、世界的な格付け機関であるムーディーズの日本法人です。
ムーディーズは、グローバルな視点から企業や政府、金融機関の信用力を評価し、投資家に対してリスク情報を提供しています。
ムーディーズの格付けは、世界中で広く利用されており、国際的な投資家から高い信頼を得ています。
国際的な金融市場での評価に強みを持っているため、海外展開を検討している企業におすすめの格付け会社です。
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン
S&Pグローバル・レーティング・ジャパンは、世界的な金融サービス企業であるS&Pグローバルを親会社に持つS&Pグローバル・レーティングの日本法人です。
企業や金融商品の信用格付けを行い、投資家に向けて信頼性の高い情報を提供しています。
特に、詳細な分析や予測をもとにした格付けが特徴であり、経営者がリスクを管理するための重要な指標となります。
また、国際的な視点からの評価も行っており、グローバルなビジネス戦略を考える際に有用です。
与信調査と合わせて行うべきこと
与信調査は取引先の信用リスクを評価する重要な手段ですが、それだけでは十分ではありません。
取引先との円滑な取引を継続するためには、与信調査と合わせて、以下の3つの取り組みを併せて行うことが重要です。
- 自社の与信管理体制の構築
- 与信限度額の設定と管理
- 反社チェック
自社の与信管理体制の構築
自社の与信管理体制を構築することは、企業のリスク管理において不可欠です。
まず、与信管理ポリシーを明文化し、全社員に周知徹底しましょう。
次に、取引先の信用データを一元管理するシステムを導入し、リアルタイムでの情報更新を行います。
また、定期的な与信審査会議を開催し、取引先の信用状況を評価・再検討することが必要です。
さらに、与信限度額の設定や取引条件の見直しを行い、特に信用リスクが高いと判断される取引先に対しては、然るべき措置を講じます。
これにより、売掛金の回収リスクを軽減し、健全な取引関係を構築することが可能になります。
与信限度額の設定と管理
与信限度額の設定は、「必要かつ安全な範囲内」を原則とします。
まず、必要な範囲とは、月間売上見込み額に回収サイト(売掛期間と手形期間の合計)を掛けて算出します。
次に、安全な範囲として、自社の財務体力や取引先のシェアを考慮することが必要です。
これにより、過度なリスクを避け、与信管理ルールに基づいた適切な限度額を設定します。
設定した与信限度額は定期的に見直し、取引先の状況変化に応じて柔軟に調整することが大切です。
反社チェック
反社チェックとは、取引先が反社会的勢力と関係がないかを確認する調査です。
これは企業が社会的責任を果たし、健全な経営を維持する上で重要です。
具体的には、新規取引開始時や定期的なタイミングで、取引先企業の役員や主要株主について、反社会的勢力との関連性をチェックします。
方法としては、専門の調査会社を利用したり、警察や暴力追放運動推進センターなどの公的機関に照会したりします。
反社会的勢力との関係が判明した場合は、速やかに取引の中止または見直しが必要です。
このチェックを怠ると、企業の信用や資産に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重に行います。
与信調査を行わないと生じるリスク
与信調査を行わずに取引を進めると、さまざまなリスクが伴います。
特に中小企業にとっては、これらのリスクが経営を圧迫する可能性が高いため、事前の調査は欠かせません。
リスクには、主に以下の4つがあります。
- 不良債権の発生
- 不適切な取引条件の設定
- 突然の取引停止
- 取引先との関係悪化
不良債権の発生
与信調査を行わずに取引を開始すると、支払い能力のない取引先に商品やサービスを提供してしまうリスクがあります。
その結果、代金回収が困難になり、不良債権が発生する可能性が高まるのです。
不良債権の増加は、企業のキャッシュフローを悪化させ、運転資金の不足や投資機会の損失につながります。
さらに、自社の信用力低下や金融機関からの融資条件の悪化など、経営全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
不適切な取引条件の設定
与信調査を行わないと、取引先の財務状況や信用力を正確に把握できず、リスクに見合わない緩い取引条件を設定してしまう可能性があります。
例えば、支払い期限を必要以上に長く設定したり、与信限度額を高く設定したりすることで、自社が過大なリスクを負うことになります。
これにより、資金繰りの悪化や売掛金回収コストの増加など、自社の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
適切な与信調査を行うことで、取引先のリスクに応じた適切な取引条件を設定できます。
突然の取引停止
与信調査を怠ると、取引先の経営状況の変化や財務悪化を見逃し、突然の取引停止に直面するリスクがあります。
取引先の経営破綻や倒産に気付かずに取引を継続していると、急な取引停止により、必要な商品やサービスの供給が途絶える可能性があります。
その結果、代替取引先の確保が間に合わず、自社の事業に重大な影響を与えかねません。
定期的な与信調査を行うことで、取引先の状況変化を早期に把握し、適切な対応を取れます。
取引先との関係悪化
与信調査を適切に行わないと、取引先との関係悪化につながる可能性があるため、注意が必要です。
例えば、取引先の実態を把握せずに過度に厳しい取引条件を設定してしまうと、取引先との信頼関係を損ないかねません。
一方で、リスクを過小評価して緩い条件を設定し、後から条件を厳しくすることも、取引先との関係を悪化させる要因となります。
適切な与信調査を行うことで、取引先の状況に応じた適切な条件設定が可能となり、長く良好なビジネス関係を構築できます。
まとめ
与信調査は、企業の経営を安定させるために欠かせないものです。
取引先の信用力を事前に評価することで、不良債権の発生や取引先の倒産による損失を未然に防げます。
また、適切な与信管理は健全な取引関係の構築にもつながり、安定した事業運営を可能にします。
与信調査を怠ると、企業の財務状況や事業継続性に深刻な影響を及ぼしかねません。
ぜひ本記事を参考に、自社の与信管理体制を強化してください。
中小企業経営者向け!