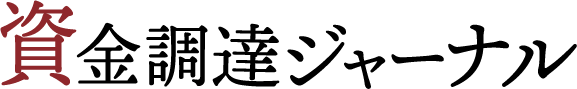法人税には中間納付の制度があり、基本的に事業年度の中間で法人税の一部を前払いする必要があります。
しかし、設立したばかりの法人は納付の計算の基礎となる前年の所得額が不明のため、1年目から納付を求められることは基本的にありません。法人税の中間納付はいつから必要になるのでしょうか。
この記事では、法人税の中間納付の概要や算出方法、法人税の中間納付で注意すべきことを解説していきます。
目次
法人税中間納付とは

法人税は、法人の事業年度終了後に計算されます。法人税中間納付とは、法人の事業年度終了日が訪れるまで、事業年度開始から6ヶ月を経過した日を基準として、おおむね納税額の半分を前払いする制度です。
中間納付の段階では法人税が確定していないため、予定で法人税額を計算して納付します。(算出方法は後述)
法人税の中間納付の対象にならない法人については後述しますが、基本的にはほとんどの法人が法人税の中間納付の対象となるでしょう。
このように法人税において中間納付が規定されているのは、1年分をまとめて納付することになると納税額が大きく、法人側の負担になると考えられるためです。最終的な納税額に変わりはありませんが、資金繰りがショートするリスクを軽減できます。
また、法人税を徴収する国にとっても中間納付のメリットは大きいです。企業の倒産による税収入の減少、滞納リスクの軽減により、財政収入の安定に寄与します。
法人税中間納付の対象にならない法人

法人は、原則として法人税の中間納付をする必要がありますが、中間納付の対象外になる法人もあります。
まず、法人設立1年目の法人です。法人税の中間納付は基本的に前年度の確定申告時の申告納税額をもとに計算されますが、設立初年度は前年の申告がないことから中間納付の義務が免れます。ただし、合併による設立の場合は必要です。
また、法人税中間納付の対象は、株式会社や合同会社などの普通法人に限られます。NPO法人などの公益法人は中間申告の義務がないため、法人税の中間納付を行う必要がありません。
さらに、上記以外の普通法人であっても、前年の確定法人税額が20万円以下(予定納税額が10万円以下)の場合は、中間納付の義務の対象外となります。なお、前年の確定法人税額が20万円を超える場合でも、仮決算の結果納付すべき額が10万円以下であるときは中間納付の必要はありません。
法人設立1年目の会社で、本年度の確定申告で法人税額が20万円を超えるような場合は、翌年以降中間納付の義務が発生する可能性がありますので注意しましょう。
法人税中間納付の算出方法
法人税の中間納付にともない、普通法人は原則として法人税の中間申告を行わなくてはなりません。中間申告により納付する予定税額の計算方法としては、「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。
- 予定申告
- 仮決算
法人税の中間申告の方法には継続要件がなく、法人は予定申告と仮決算のいずれかメリットの大きい方の選択が可能です。それぞれの計算方法を解説していきます。
予定申告
予定申告は、前事業年度の法人税額を基礎として納付する予定納税額を計算する方法です。以下の算式により納税額を計算します。
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6(100円未満切捨て)
前事業年度の月数は基本的に12ヶ月ですが、前事業年度に会社を設立するなどして前事業年度の月数が12ヶ月でないときは、その月数(前事業年度の月数)に従って計算することになります。
予定申告を選択すれば簡単な計算で予定納税額を求められるのがメリットです。多くの企業で採用されています。
仮決算
仮決算は、事業年度開始日から6ヶ月を経過する日までをひとつの事業年度と仮定して決算(中間決算)を行い、法人税の予定納税額を確定させる方法です。計算の方法は、決算日に法人税額を確定させるときと同じです。以下の計算式により予定納税額を求めます。
益金(税法上の収益)-損金(税法上の費用)=課税所得金額
課税所得金額×法人税率=法人税額(予定納税額)
仮決算を選択すると中間決算を行わなくてはならないため、法人の作業負担が増えます。そのため、前述のように予定申告を選択する企業も多いですが、直近で業績が悪化している場合は仮決算を選択した方が良い場合もあるでしょう。
仮決算は、現状に合わせて予定納税額を確定させる方法だからです。前事業年度と比べて急激に業績が落ち込んでいるときは、予定申告による予定納税額が現状とかい離してしまい、納税が難しくなることもあります。
前期よりも業績が落ち込んでいることが明らかな場合は仮決算の方が予定納税額を減額できるため資金繰りの悪化を防止できるでしょう。また、先述のように、仮決算で算出した法人税額が10万円以下のときは予定納付の義務自体も免れます。
【ケース別】法人税の中間申告に関して把握しておきたいこと

法人税の中間申告や中間納付について、注意しておきたいことをケース別に取り上げます。
- 中間申告書を提出しなかった場合
- 納税の期限を過ぎてしまった場合
- 法人税額が0円の場合
- 吸収合併を行っている場合
中間申告書を提出しなかった場合
法人税の中間納付の対象となる法人は法人税の納付が義務付けられますが、中間申告は必須事項ではありません。
中間申告書を管轄の税務署に提出しなかった場合は、予定申告により中間申告したもの(みなし申告)として取り扱われます。
予定申告で問題ない場合は作業負担が少ないため効率的ですが、前年度よりも業績が落ち込んでいるときは仮決算よりも予定納税額が大きくなる可能性がありますので注意しましょう。
納税の期限を過ぎてしまった場合
法人税の中間納付の期限は、事業年度開始から6ヶ月が過ぎた日から2ヶ月以内です。納付期限を過ぎると延滞税が発生するほか、無申告加算税などの追徴課税の対象になることがあります。
延滞税や追徴課税を受けないためには、納付期限内にしっかり納付を済ませることが重要です。納税資金が不足していて資金調達方法を模索されている事業者様は、PMGまでご相談ください。PMGでは、売掛債権の早期資金化を軸に、幅広い金融支援で事業者様の資金調達をサポートいたします。
法人税額が0円の場合
業績悪化などが理由で仮決算を行った結果、中間申告で納付すべき法人税額が0円になることがあります。
納付すべき予定納税額がない場合でも、仮決算で中間申告をしない場合は、予定申告(みなし申告)により申告したものとして取り扱われますので注意しましょう。
仮決算の予定納税額を適用したい場合は、仮決算による中間申告書や添付書類を管轄の税務署に申告期限(中間納付の期限に同じ)までに提出します。
吸収合併を行っている場合
吸収合併とは、他方の法人格を消滅させ、もう一方の法人格と合併させることで会社を承継する方法です。吸収合併後の事業年度開始日から6ヶ月を経過しているときは中間納付の対象となります。
吸収合併の場合、予定申告の計算基準となるのは、適格合併(合併時に法人税が課されない合併)による被合併法人(存続している法人)の前事業年度の法人税額です。
吸収合併では、適格合併か適格合併でないかで中間納付の額が変わってきますので、専門家に相談されるのが確実でしょう。
まとめ
創業1年目で設立したばかりの法人に法人税の中間申告や中間納付の義務はありません。しかし、法人設立から2年目以降は中間納付が原則として必要になります。まずは中間納付とは何か押さえておきましょう。
中間申告については、予定申告と仮決算の2種類の方法があります。どちらの方法で申告すべきかは状況によって異なるでしょう。
業績悪化が見込まれる場合は仮決算により中間申告を行った方がメリットは大きいです。仮決算の場合は税務署への中間申告書の提出が必要になりますので、納付と合わせて申告漏れがないようにしましょう。