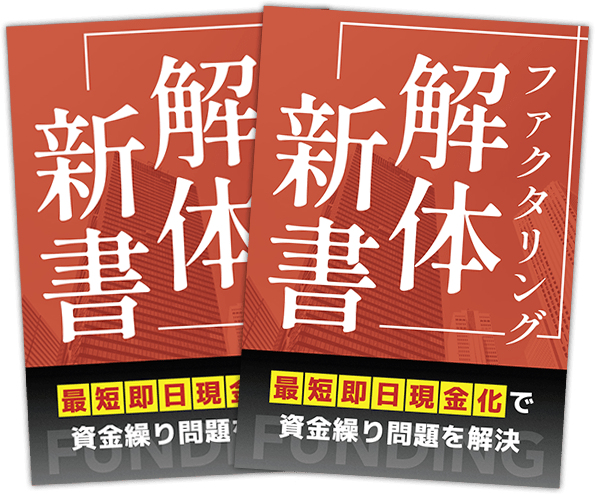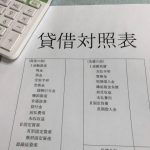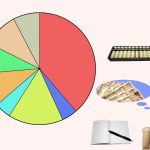ファクタリングを利用するときに注意したいのが損金です。
損金というのはファクタリングを利用したときに発生する手数料のことで、この手数料に対して適切な知識を身につけなければ税務処理ができなくなってしまいます。
ファクタリングを利用するときには手数料を欠かす事ができません。
しっかりとファクタリングを利用できるように、手数料に関する知識を身につけるようにしましょう。
中小企業経営者向け!
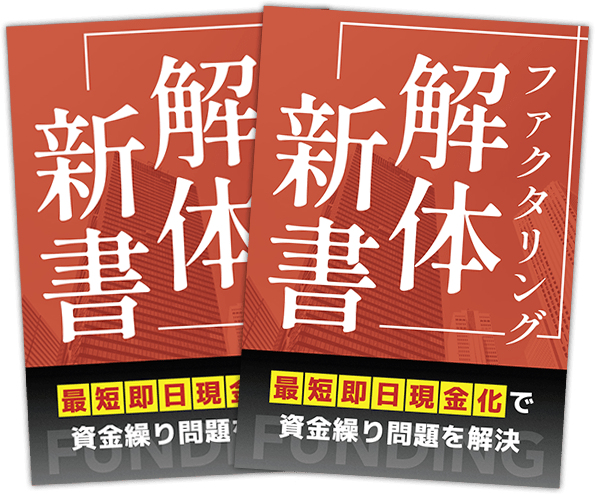
目次
ファクタリングと手数料
ファクタリングを利用するときには手数料を欠かす事ができません。
ファクタリングは売掛債権を現金に早期に変える仕組みのことで、ファクタリング企業に売掛債権を売却します。
売掛金をファクタリング企業に売却することで現金が手に入るのですが、この際に手数料が差し引かれてしまうので、どうしても手に入る資金が目減りしてしまい、いわゆる損金に該当する金額が発生してしまうのです。
ファクタリングを利用して資金調達を行うのは多くの企業で取り入れられているものですが、損金の取り扱いを税務上しっかりと理解しておかなければ適切な知識を得る事ができません。税務上の知識を把握し、経営にも活かしてみましょう。
損金の取り扱いについて
まず、ファクタリングサービスを利用した場合には会計上の損金の取り扱いを理解する事が非常に重要です。
ファクタリングを利用したからといって会計処理が複雑になり、取り扱いが難しくなるというわけではないのですが、損金に対する税金の知識がなければ処理がわからなくなってしまいます。
ファクタリング手数料は法的には損金という区分になり、法人税に影響を与えることはありません。
このため、税務申告を行う際にファクタリングを利用したからといって特別に書類を作成する必要はありません。
一般的には金銭債権の取引は非課税になっているので、消費税などは控除されます。
しかし、ファクタリングで得た売掛債権の売却は課税売上となることに注意する必要があります。
ファクタリング を頻繁に利用することで、課税売上割合が95%以下になってしまうと消費税の控除を受ける事ができないので、ファクタリング の支払いのような非課税売上高が増えすぎると消費税の控除を受けられない可能性があることに注意しましょう。
税務処理では大きな問題は起こらない
ファクタリングを利用したとしても会計処理でファクタリング手数料を損金に算定し、譲渡の対価を非課税としないという点にさえ注意しておけば大きな問題は起こりません。
ファクタリングは企業負担の少ない資金調達の代表です。
しっかりと税務処理や会計処理の基本を身につけ、ファクタリングを有効活用するようにしましょう。
中小企業経営者向け!