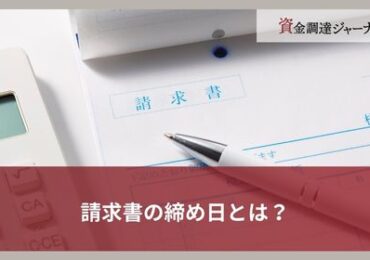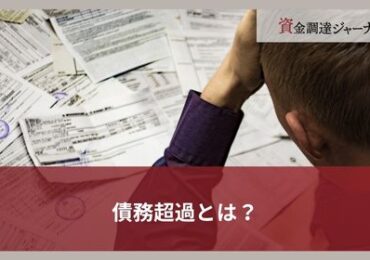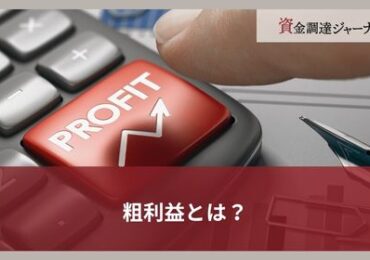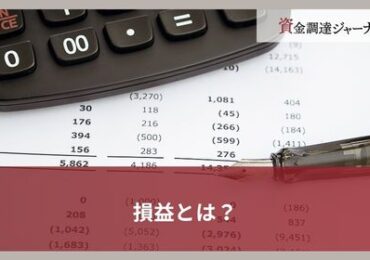請求書の締め日とは、商品やサービスを納品・提供する期間の区切りとなる最終日のことです。
商品やサービスを納品後にその対価を受け取るため支払いを確定させるため、請求書を発行します。
そのため請求書には、締め日や支払期日を記載するものの、支払日等の決め方に注意が必要です。
そこで、請求書の締め日について、支払日の決め方や遅延した場合の対応方法を解説します。
中小企業経営者向け!

請求書の締め日とは

請求の締め日とは、商品やサービスを納品・提供する期間の区切りとなる最終日のことです。
1か月の間に商品やサービスを納品・提供し、1か月分を取引相手に請求することが多いといえます。
たとえば月末締め翌月末払いなどの場合、1か月で締め日を迎えることになります。
会社経営では収益を管理する事務処理が必要です。
試算表なども1か月を1つのサイクルとし、請求する区切りも1か月のほうがわかりやすいといえます。
ただし締め日は会社によって様々であり、互いの合意で決めることができます。
区切った期間の最終日が締め日となり、その期間の支払いを定めた日付が支払日です。
請求書の支払期日とは
請求書を発行するときには、いつまでに代金を支払ってもらうのか支払期日も記載します。
1か月を請求期間とした場合において商品やサービスの代金を支払ってもらう日が支払日です。
下請代金の支払期日は「下請代金支払遅延等防止法」では、商品・サービスの納品・提供を受けた日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めることとされています。
支払期日までに支払わなかった場合、納品・提供を受けた日の60日後から支払った日までの日数に対し、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払うことも義務付けられています。
一般的に支払期日は、月末締め翌月末払いや月末締め翌々月末払いなどが多いものの、自由に決めることができます。
会社ごとの支払サイトによって異なる場合が多いため、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
取引先の決算期前後で請求書のやり取りが発生するときには、期ズレを防ぐために修正を依頼されることもあるため、より注意が必要です。
請求書の発行日とは
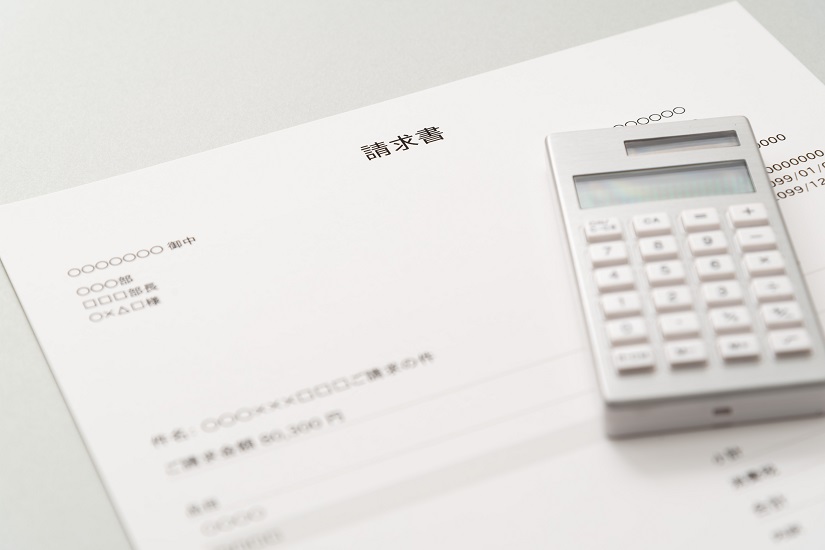
請求書の発行日とは、商品やサービスを販売・提供した代金を請求するための請求書を作成する日です。
請求書の発行自体は法律で義務付けられているわけではなく、契約内容に相手が合意すれば書面がなくても問題ないとされています。
しかし事務処理上、請求書がなければ代金の回収漏れが起こりやすくなり、取引先も支払いを忘れる恐れがあります。
取引や金額に対する認識にズレが生じないためにも、請求書は発行しておいたほうが安心です。
請求書は商品やサービスを提供し終えたタイミングで発行するため、発行日をいつにするか悩んだときには次の2つを参考にしましょう。
| 都度方式 | 商品・サービスの販売・提供が終了したタイミングで請求書を発行 |
| 掛売方式 | 1か月など決まった一定期間に繰り返し取引があるときにはまとめて請求書を発行 |
請求書を発行する日は、取引が実際に行われた日です。
都度方式の場合には、取引終了日が請求書の発行日で、掛売方式なら実際に取引が終了して一定期間後に請求書を発行します。
請求書にいつ発行されたのか日付が記載されていないと、どの取引に対する何の請求か不明瞭となり、仕入税額控除の対象になりません。
また、代金を回収する上で支障をきたすリスクも高くなったり架空請求と疑われたりするため、必ず請求書に発行日を記載してください。
発注側:請求書の支払期日を過ぎた場合の対応
請求書の支払期日を過ぎてしまった場合、すぐに取引先に連絡を入れましょう。
うっかり忘れてしまうことや、送金したと思い込んでしまうこともあるかもしれないとはいえ、期日が守られないことは信頼関係を崩す行為です。
早急に連絡することと、いつ入金できるか確実な入金日を伝えることが大切といえます。
受注側:入金されない場合の対処法

取引先に請求書を送付したのにもかかわらず、記載していた期限を過ぎても入金がないときには、まずは請求書が届いているか確認が必要です。
手違いにより届いていない場合もあれば、紛失の可能性も考えれます。
そのため未入金のケースでは次の3つで対処してください。
- 取引先に連絡する
- 内容証明で支払い督促する
- 法的手段を行使する
それぞれ説明します。
取引先に連絡する
取引先に対し、メールや電話で支払期日を過ぎても入金がないことを伝えましょう。
仮に請求書が届いていない場合には、再度発行が必要です。
先方の手違いで経理担当者に請求書が届いていないケースなどは、早急に入金してもらうことと、支払日を確認することが必要になります。
注意したいのは、納品した商品や提供したサービスに何らかの不具合などがあり、意図的に入金されていないケースです。
何に問題があるのか伝えてもらい、交換・返品・値引きなどで対応しましょう。
請求書を再発行する場合
請求書を再発行する場合、一度発行した請求書を同じ内容のものを再度作成します。
たとえば請求書の内容にミスがあったときなども、再発行が必要です。
1通目の請求書と混同しないために、「再発行」と記載しておきましょう。
再発行した請求書の発行日は、訂正前の請求書と同じ発行日で問題ありません。
契約の際に延滞利息を取り決めていた場合、延滞利息が追加されることを記載した上で支払期日を延ばす場合もあります。
この場合における延長の目安は、2週間から1か月程度が望ましいとされます。
内容証明で支払い督促する
取引先にメールや電話で連絡し、早急に支払ってもらうように伝えても入金が確認できない場合は、内容証明郵便を使って支払い督促をしましょう。
内容証明郵便とは、どのような内容の文書を誰にいつ送ったのか、日本郵便が証明する郵便です。
普通郵便で請求書を送っても、郵便事故などで届いていないといわれてしまう可能性もあります。
間違いなく手元に届けられていることを証明するためにも、内容証明郵便が有効です。
法律による請求書の有効期限は5年とされているため、請求書を発行し送っていても支払いがないまま5年経過すれば消滅時効が成立します。
しかし内容証明郵便は、民法上の時効を中断させる自由の催告に該当するとされ、消滅時効までの有効期限を6か月延長できます。
内容証明郵便で請求書を送っても支払いがない場合には、この延長された有効期限の6か月間に、裁判上の請求や差押さえ、仮処分などの手続を行います。
また、内容証明郵便が届いたという心理的なプレッシャーを与えることにもつながるため、催促には有効です。
法的手段を行使する
内容証明郵便を送っても入金がない場合には、裁判所から督促状を送付してもらう「支払督促」を検討しましょう。
請求を裁判所に代行してもらうため、取引先には精神的な圧力をかけることができ、請求者の立場も守られます。
支払督促を送付し、2週間以内に異議が申し立てられた場合には、訴訟に移行します。
訴訟を起こすことで、訴状や答弁書催告状などが取引先に通達される、これらの書類が届いたことにより時効が中断されます。
勝訴すれば債務名義を取得し、強制執行を申し立て、財産の差押えで取り立てができます。
まとめ
会社経営において、請求業務は重要な仕事の1つです。
請求書の締め日や支払期日をどのように決めればよいか迷いがちであるものの、複数の取引先の日付を統一すればミスを防ぎやすくなります。
ただし月末締め翌々月末払いなど支払期日までが長めに設定されれば、資金繰りは悪化しやすくなってしまいます。
入金はできるだけ早く、支払いは遅くすることがキャッシュフローを円滑にするために必要です。
請求する側とされる側のどちらの立場になったとしても、取り決めを守って期日を守るようにしましょう。
中小企業経営者向け!