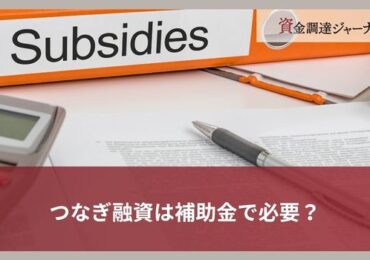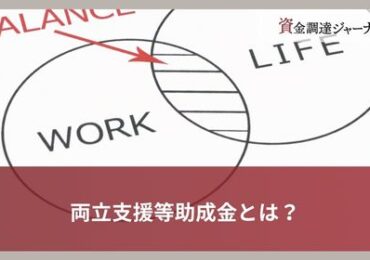軽貨物事業者の資金調達において、うまく活用したいのが助成金や補助金です。
助成金と補助金は、どちらも国や地方自治体の政策に沿って事業を行う事業者に対し支給される資金であり、返還する必要がありません。
そのため軽貨物事業者もうまく活用したい資金調達の方法といえます。
事業拡大や設備投資などにおいて、資金調達が必要であれば活用したい方法といえます。
そこで、軽貨物事業者向けの助成金や補助金について、その内容なども紹介します。
中小企業経営者向け!

助成金とは

「助成金」とは、国の政策に沿って労働環境改善などに取り組む事業者に支給される資金です。
主に労働環境改善や雇用・人材育成を支援することを目的とした制度が多いといえます。
法人だけでなく、個人事業主でも従業員を雇用していれば活用できる制度もあり、雇用に関する助成金の主な管轄は厚生労働省です。
財源は雇用保険料と税金の一部であるため、雇用や能力開発で必要な経費を数十万円から100万円程度までが補助されます。
金額は少ないものの、厚生労働省の助成金は年間通して受け付けしていることがメリットといえます。
補助金とは

「補助金」とは、国の政策目標に沿って事業を運営する事業者に支給する資金であり、スモールビジネス事業の資金調達に活用しやすい制度です。
主に補助金は、新規事業・起業促進・研究開発などで必要となる資金支援する制度であり、管轄は経済産業省やその管轄の独立行政法人や中小企業庁とされています。
財源は主に税金であることと、経済活性化に向けた研究開発などを支援するため、支給額は数百万円以上や数億円規模など規模が大きいことが特徴です。
ただし補助金の公募期間は、特定の時期の1週間から1か月のみなど限定されていることが多いため、常に情報入手していなければ申請のタイミングを逃す恐れもあります。
また、助成金は要件を満たせばほぼ支給されるのに対し、補助金は採択されなければ支給対象となりません。
軽貨物事業者向けの補助金

軽貨物事業者が活用できる補助金は、次の4つです。
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
それぞれ説明します。
事業再構築補助金
「事業再構築補助金」は、ポストコロナ時代の経済社会の変化への対応に向けて、思い切った事業の再構築をする事業者を支援する制度です。
たとえば、次の取り組みを通じて事業規模を拡大したり新事業展開したりなど、事業再構築に意欲的に取り組み事業者を支援します。
- 新分野展開
- 業態転換
- 事業・業種転換
- 事業再編など
たとえば軽貨物事業者であれば、次のような事業への展開の際に活用できる制度と考えられます。
- 流通加工業・倉庫業・半導体トレイ運送への展開
- 買い物疎過疎地域に対する衣料品などの移動販売
予算総額1兆円と大変規模の大きな制度であり、支給金額上限も1億円など多額の資金調達が期待できます。
ただし事業再構築補助金では次のように複数の枠を設けているため、それぞれ補助額などが異なる点に注意しましょう。
IT導入補助金
「IT導入補助金」とは、中小企業や小規模事業者が、労働生産性の向上を目的にITツールを導入などの資金を支援する制度です。
かかった費用の一部が補助されます。
軽貨物事業者の場合、たとえば以下のケースでかかった費用の一部が補助されます。
- 送迎バス管理業務DX化による管理スタッフ業務の改革
- 売上集計処理短縮に向けた販売管理システム導入
なお、対象となるITツール(ソフトウェア・サービスなど)は、前もって事務局の審査を受け、IT導入補助金の公式サイトに公開(登録)されているものです。
相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれます。
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金」とは、2050年カーボンニュートラルおよび2030年温室効果ガス削減目標(2013年度比47%減)達成に向けて、商用車を電動化することに対し支援する補助金制度です。
日本全国では数えきれないほどの軽貨物自動車が走っていますが、電動化導入を加速させれば産業競争力強化・経済成長・温室効果ガス排出削減などが実現されると考え設けられた制度といえます。
「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金」の概要は以下のとおりであり、申請期限まである程度時間はありますが、予算により抽選になる可能性もあることは留意しておきましょう。
軽貨物事業者向けの助成金

軽貨物事業者の活用できる助成金は、「トラック協会」の会員企業向けの以下の制度です。
- 安全装置等導入促進助成事業
- ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
- トラック運転者の「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」スクリーニング検査助成事業
- 血圧計導入促進助成事業
- アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業
- 若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業
- 中小企業大学校講座受講促進助成制度
- 自家用燃料供給施設整備支援助成事業
- 自動点呼機器導入促進助成事業
- 「働きやすい職場認証制度」認証取得費助成事業
それぞれ説明します。
安全装置等導入促進助成事業
「安全装置等導入促進助成事業」は、事業用トラックの交通事故ゼロを目指すために、安全運行に次の装置導入を普及させるための支援を行っています。
- 後方視野確認を支援するバックアイカメラ
- 側方視野確認を支援するサイドビューカメラ
- 飲酒運転を防止するアルコールインターロック装置
- IT機器を活用した遠隔地での点呼に使用する携帯型アルコール検知器
- 車輪脱落事故の防止を図るトルク・レンチ
対象装置ごとに機器取得価格の2分の1まで(上限2~4万円)が補助対象です。
ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
「ドライバー等安全教育訓練促進助成制度」は、全日本トラック協会指定の研修施設に⾃社のドライバーまたは安全運転管理者などを派遣し、所定の研修を受講させた際の費⽤の全部または⼀部を支援しています。
一般研修なら1泊2日1万円、特別研修であれば2泊3日で受講料の7割助成(Gマーク認定事業所の場合は全額助成)されるため、うまく活用するとよいでしょう。
トラック運転者の「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」スクリーニング検査助成事業
トラック運転者の「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」スクリーニング検査助成事業は、ドライバーの睡眠の質を確認するスクリーニング検査に対する支援を行っています。
助成の対象は、指定検査・医療機関が実施するSASスクリーニング検査のうち健康保険適用外なる第1次検査と第2次検査で、以下の費用が助成されます。
- 第1次検査費用の半額(上限1人あたり500円)
- 第2次検査費用の半額(上限1人あがり2千円)
- 第1次検査及び第2次検査を同時に実施している場合は合計費用の半額(上限1人あたり2千500円)
血圧計導入促進助成事業
「血圧計導入促進助成事業」は、ドライバーの過労や事故につながる脳・心臓疾患発症につながる高血圧を予防するための事業を行っています。
高血圧予防に欠かせない血圧計を乗務前点呼で活用できるように、管理医療機器かつ特定保守管理医療機器である業務用全自動血圧計を導入した際に、機器取得費用の2分の1(上限5万円)が助成されます。
アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業
「アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業」では、トラックドライバーが休憩や荷待ちのエンジン停止時において、相当時間連続使用できるエアヒータまたは車載バッテリー式冷房装置を取得した価格の2分の1以内(上限6万円)を助成しています。
若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業
「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」では、若年労働者をドライバーとして採用したときの特例教習受講・準中型免許取得への支援を行っています。
助成の対象は、事業者が負担した次の教習または準中型免許取得の指定教習所における費用です。
- 特例教習の講習
- 準中型免許のうち、準中型免許の新規取得(普通免許取得後の取得含む)または5トン限定準中型免許の限定解除
助成条件・助成額・申請方法などについては、所属している都道府県トラック協会に問い合わせて確認するようにしてください。
中小企業大学校講座受講促進助成制度
「中小企業大学校講座受講促進助成制度」では、中小企業経営者・後継者・管理者が、「中小企業大学校」の経営戦略講座など受講したときに助成金が支給されます。
自家用燃料供給施設整備支援助成事業
「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」では、指定数量(千リットル以上)の軽油専用タンク設置を伴う自家用燃料供給施設の新設・増設・増設を支援する制度を行っています。
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに、市町村または地区消防組合などの消防で危険物取扱所の「完成検査済証の交付」を受け、支払いを完了するものが対象で以下の金額が助成されます。
- 軽油タンク新設(設置1か所分のみ)100万円
- 軽油タンク増設または増設を伴う代替は30万円
自動点呼機器導入促進助成事業
「自動点呼機器導入促進助成事業」では、運行管理の安全性向上や、労働環境改善・人手不足解消に向けた自動点呼機器導入費用の一部を支援しています。
助成対象となるのは自動点呼機器の導入費用で、周辺機器・セットアップ費用・契約期間中のサービス利用料などを含み上限10万円までです。
ただし所属協会域内で安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有していれば、2台分(上限20万円)まで助成対象となります。
「働きやすい職場認証制度」認証取得費助成事業
「働きやすい職場認証制度」認証取得費助成事業は、国創設の「働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)」の認証を新規また継続で申請した際の費用の一部を支援しています。
助成対象となる費用は以下のとおりです。
- 新規認証取得(上位認証取得を含む)にかかる審査料・登録料(上限3万円)
- 同位認証継続にかかる審査料・登録料(上限2万円)
まとめ
軽貨物事業者でも、助成金と補助金の要件などを確認し、満たす場合には積極的に資金調達に活用しましょう。
助成金と補助金は、どちらも実際に支払った諸経費が支援対象であり、後払いで支給されます。
軽貨物事業者の助成金や補助金による資金調達においては、実際に手元に支給されるまでのつなぎ資金を準備することも忘れないでください。
中小企業経営者向け!