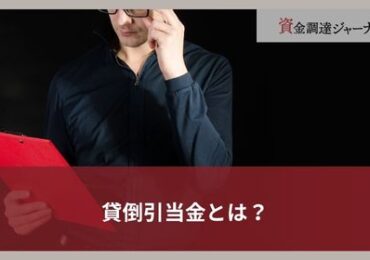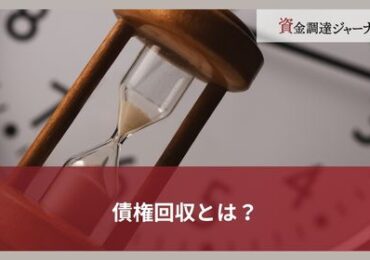与信管理とは、文字通り取引先に信用を供与するための管理です。
取引相手としてふさわしいか、取引額や取引方法などを設定・見直します。
掛け取引の場合、将来的に後払いとなった代金を回収できるか確実とはいえず、代金が未払いとなる不確実性リスクが伴います。
この不確実性リスクを回避・低減させるためにも、取引先の情報収集や信用力・動向などの予測が不可欠です。
そこで、与信管理について、プロセスや調査方法、業務の流れをわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

与信管理とは

与信管理とは、与信に伴う信用リスクを管理することです。
商品やサービスを掛け取引で販売したとき、その代金は後日払いで受け取ります。
代金を受け取る債権者は、発生した売掛債権を確実に回収するために、取引先の支払能力など調査・管理することが求められます。
与信管理で行うことは、未払い代金の与信限度額の設定や、信用力に応じた回収期間の調整などです。
仮に取引先が倒産すれば、発生した売掛債権は貸し倒れとなり回収できなくなります。
取引額が大きければ大きいほど、未回収のダメージも大きくなるため、自社の連鎖倒産リスクを回避するためにも与信管理を徹底しましょう。
与信管理で承認するまでの流れ
新規の取引先と契約を結ぶ前段階の与信管理において、与信承認までの流れは主に次の4つです。
- 取引先の情報収集
- 取引先の信用力評価
- 取引開始の申請と与信限度額の設定
- 契約条件の交渉
それぞれ説明します。
①取引先の情報収集
新規の取引先となる候補先に対し、契約を結んでよい相手か、まずは営業部門で調査します。
取引先を直接訪問して行う調査と並行し、管理部門でも信用調査会社など第三者機関を利用する方法などで情報を集めます。
②取引先の信用力評価
収集した情報から、取引先の信用力を評価します。
社内格付制度を導入し、統一的な基準で分けて与信リスクを算出しましょう。
これから取引を開始してもよい相手か評価する方法は次の3つです。
- 定量分析
- 定性分析
- 商流分析
それぞれ説明します。
定量分析
「定量分析」とは、決算書の数値により分析する方法です。
取引先の経営状態を把握するための確実な手法であり、財政状態は「貸借対照表(B/S)」、営業成績は「損益計算書(P/L)」でそれぞれ確認し、分析します。
上記を直接入手できない場合は、調査会社などを経由して間接的に手に入れる方法や、公開している資料を使う方法で決算数値を分析できます。
定性分析
「定性分析」とは、質的データに基づいた分析です。
定量分析で使った数値ではなく、単純に数値であらわすことのできない以下の情報を分析します。
- 経営者の資質
- どのような大株主か
- 備わっている技術力
- 構築されている販売体制
上記の定性情報を分析することで、より詳細な与信管理が可能となります。
商流分析
「商流分析」とは、流通の中の1つである商流の分析です。
- 商品の仕入れ先
- 売買取引
- 最終的な需要者
- 決済条件
- 納品の場所・方法
上記により、取引の全体像を把握し、トラブルの恐れやリスクはないか確認していきましょう。
③与信限度額の設定
取引相手となる候補先の信用力を評価し、与信限度額を設定します。
与信限度額とは、取引する限度額であり、過度に与信リスクを負わないための上限金額です。
発生する売掛金の上限を設けることで、設定した額を超えた掛け取引は行わないルールとします。
④契約条件の交渉
与信限度額を設定したら、その契約条件でよいか取引候補先と交渉を行います。
交渉がまとまれば契約を取り交わして取引を開始します。
まずは基本契約を締結し、個別取引は注文書・注文請書などに契約条件を記載して取引を行います。
与信管理で契約内容を見直す流れ

与信管理のうち、既存の取引先との取引内容を見直す場合の流れを説明します。
この場合、それぞれの営業部署・支店・子会社・関係会社など含めた債権・債務の残高と、担保状況などを管理します。
その上で定期的に与信限度を見直し、債権回収状況なども管理することが必要です。
信用力が低下しているとされる取引先については、取引量や与信限度額の引き下げや決済方法の変更などを検討します。
与信管理で契約内容を見直すときの流れは、主に次の4つです。
- 債権・限度額の確認
- 取引先の情報収集
- 問題案件の洗い出し・信用力評価
- 与信限度額等の見直し
- 回収・事故管理
それぞれ説明します。
①債権・限度額の確認
すでに取引を開始している取引先の債権と限度額を確認します。
売掛金が期日通りに支払われているか確認し、遅れがあれば危険なシグナルであると判断します。
与信限度額を超えた取引の場合や、与信限度が設定されていない取引先、与信限度期限が切れている取引先など抽出して適正な運用へ見直すことが必要です。
②取引先の情報収集
取引先の情報を多面的に収集していきます。
直接入手できる情報もあれば、信用調査会社など第三者機関を通じて間接的に入手できる情報があります。
また、これまでの取引履歴など内部情報も必要です。
当初は信用力の高い取引先だった場合でも、業況や財務内容は日々変化しているため、一定ではありません。
一度取引条件を取り決め、実際に取引をスタートしている場合でも、一定期間ごとに確認や見直しをしなければリスクを高めます。
営業部門・管理部門がそれぞれ情報を収集し、その情報をもとに分析・蓄積して、重要な変動が見られたときには条件の見直しが必要です。
③問題案件の洗い出し・信用力評価
売掛金の支払いが遅れている取引先など、問題案件は洗い出して信用力を再評価しましょう。
ネガティブな情報があるときや取引先の異変などが見られる場合、担保取得など対策が必要です。
特に支払いの遅延が常態化している取引先や、経営状況が極端に悪化している取引先などは、他の取引先と区別して集中した徹底管理が求められます。
④与信限度額等の見直し
一旦決めた与信限度額や取引条件も、1年に1度は経営内容や担保価値などの分析により見直しが必要です。
基本的な見直しの期間は、取引先の決算期の半年以内とするものの、異変を察知したときには臨時的な見直しも必要となります。
⑤回収・事故管理
取引先が倒産した場合は、保有する債権のポジションを明確化し、保全・回収・届出などの手続を遅滞なく行います。
ただし実際は、取引先の倒産後に未回収の売掛債権を回収することは困難といえます。
被害に遭わないためにも、与信管理を徹底して行うことが求められます。
与信管理に必要な情報の収集方法
与信管理するためには、取引先の現状を知るための情報収集が欠かせません。
情報収集の方法として、主に次の3つが挙げられます。
- 従業員からの聞き取り
- 外部機関の利用
- 調査会社に依頼
それぞれ説明します。
従業員からの聞き取り
取引先の情報を収集する方法として、従業員からの聞き取りが挙げられます。
商談や雑談から従業員の得た情報や、訪問したときの社内の様子、代表者の印象などを伝えてもらいましょう。
外部機関の利用
法務局などの外部機関を利用し、商業謄本などの情報を確認して、怪しい変更の有無などをチェックしましょう。
また、同業他社からの評価や、周辺地域の人などから得られる情報にも耳を傾けることが必要です。
調査会社に依頼
帝国データバンクや東京商工リサーチなど、調査会社に依頼する方法もあります。
企業情報データベースを保有する調査会社を使って、必要な情報を照会することで最新情報を得ることができます。
与信限度額の設定方法

売掛債権の与信限度額を取引先ごとに設定し、過度の与信リスクを負わないことが大切です。
そこで、定期的な与信管理により、取引先との与信限度額も見直しましょう。
与信限度額は、収益と与信リスクのバランスを見ながら設定します。
このとき、次の3つを基準にした設定が望ましいといえます。
- 自社が保有する売掛債権
- 取引先が保有する純資産
- 取引先の仕入債務
それぞれ説明します。
保有する売掛債権
十分な売上があり、売掛債権も回収できていれば、手元の現金が足らない状態にはなりにくいと考えらえます。
この場合は、保有する売掛債権に一定割合を掛け、与信限度額の基準としましょう。
|
与信限度額 = 売掛債権 × 一定割合 × 格付けウェイト
|
取引先が保有する純資産
取引先が保有する純資産が十分ある場合、倒産リスクは抑えられます。
この場合、取引先の純資産に一定割合を掛け、与信限度額の基準しましょう。
|
与信限度額 = 取引先の純資産 × 一定割合 × 格付けウェイト
|
取引先の仕入債務
取引先の仕入債務を多く保有している状態は、支払能力が高いことを示します。
この場合、仕入債務に一定割合を掛けて、与信限度額の基準としましょう。
|
与信限度額 = 取引先の仕入債務 × 一定割合 × 格付けウェイト
|
まとめ
取引先に対する与信限度額は、必要額でありつつも安全な範囲内で設定することが必要です。
今後の債権残の推移を予想し、季節や繁閑の差なども踏まえた上で、余裕のある設定が望ましいといえます。
売掛金の管理は、期日までに回収することを徹底しましょう。
期日までに回収できなかった場合は、取引先に対して請求していくことが必要であり、次の支払期日に未入金が発生したときは与信枠の見直しが必要です。
中小企業経営者向け!