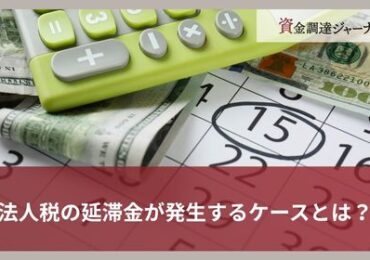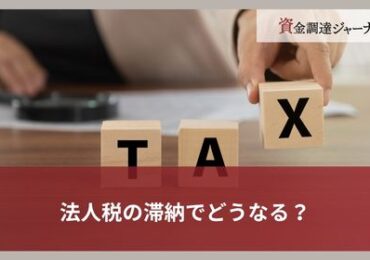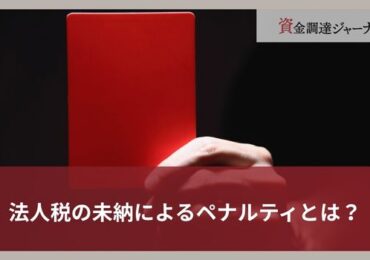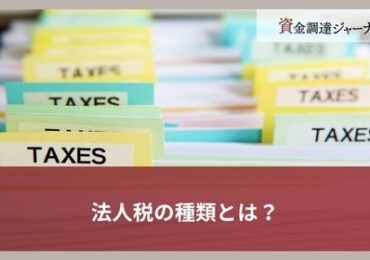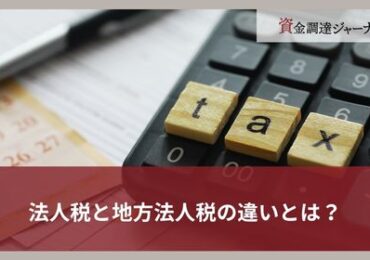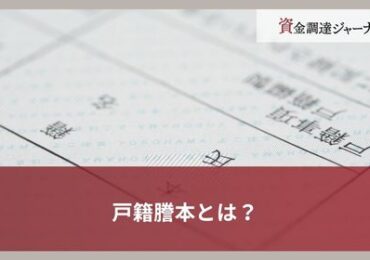法人税は、法人の事業活動で得た所得に対する税金であり、還付を受けられる場合もあります。
そこで、法人税が還付されるケースについて、青色申告の繰戻し還付の仕組みなどを解説します。
中小企業経営者向け!

法人税が還付されるケース

法人の事業活動で得た所得に対して納める税金が法人税です。
ただし以下のケースでは、納めた法人税を還付してもらえる場合があります。
- 中間納付で納め過ぎていた場合
- 見込納付と確定額が異なる場合
- 納付額より預金利息等の源泉所得税が多い場合
- 更正の請求をした場合
- 過誤納金があった場合
- 災害で損失が発生した場合
- 欠損金が発生した場合
それぞれ説明します。
中間納付で納め過ぎていた場合
法人税には、「中間納付」といって事業年度の開始日から6か月経過した日を基準とした納税額の半分を納めておく制度があります。
そもそも納税者の負担軽減を目的とした制度ですが、この中間納付で税金を納め過ぎていた場合にも法人税は還付されます。
中間納付には次の2種類があります。
- 前期の納税額の半分を納める方法
- 事業年度の中間に中間決算を行った納税額に基づいて納める方法
上記どちらの方法で納めた場合でも、最終的な確定申告で計算した納税額よりも中間納付した税額のほうが多ければ、払いすぎた法人税を還付してもらえます。
見込納付と確定額が異なる場合
法人税の確定申告の期限は、決算日から2か月以内ですが、申告期限は延長手続を取ることで3か月以内へと引き延ばすことができます。
しかし税金の納付期限は引き延ばすことはできません。
申告期限の延長で納税額が確定していない状態では、見込納付で概算額を納めることになります。
見込納付で納めた金額が確定した納付額よりも上回るときには、払いすぎた法人税が発生するため、還付してもらえます。
納付額より預金利息等の源泉所得税が多い場合
法人の銀行口座に預け入れている預金も、源泉所得税が差し引かれるものの、法人税と相殺されます。
当期は赤字で相殺する法人税がない場合や、法人税額が少額のときには、相殺しきれない税額部分の還付を受けることができます。
更正の請求をした場合
「更正の請求」とは、確定申告期限後に申告書の税額に誤りがあったことで、後日正しい額に訂正する手続です。
収益を二重計上していた場合や、収益が過大計上されていた場合などは、法人税を余分に納めていることになります。
そのため過大に納めた状態を解消するために、正しい税額に訂正する手続として更正の請求を行い、払いすぎた法人税は還付してもらいましょう。
過誤納金があった場合
法人税の過誤納金があった場合も還付の対象ですが、主に過納金と誤納金の2つのケースがあります。
過納金は、減額の変更(申告・減免・更正など)があったことで納め過ぎた税金です。
また、二重に納付するなど、誤って納めた税金を誤納金といいます。
還付金等の還付を受ける場合は納付手段に関わらず、申告書に記載した金融機関の預貯金口座に振り込まれます。
何らかの事情で振り込みが使えない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取ることもできます。
災害で損失が発生した場合
法人税では、災害などで被害を受けた法人に対し、被災した資産(滅失・損壊した資産)の損金算入を認める規定がされています。
災害で災害損失金が発生していれば、中間納付の法人税額から控除しきれなかった金額を、災害損失金額を限度に還付してもらえます。
欠損金が発生した場合
青色申告した法人において、事業年度で生じた欠損金額がある場合には、欠損事業年度から1年以内に開始したいずれかの還付所得事業年度の所得の法人税額を還付請求できます。
通常の法人であれば事業年度は1年であるため、前期に繰り戻して還付請求することが可能です。
なお、法人税の繰戻し還付については次で詳しく説明します。
法人税の繰戻し還付とは

法人税の組戻し還付とは、確定申告で欠損金が生じた場合、すでに納付済の法人税・地方法人税と相殺して払い戻してもらえる制度です。
たとえば前期は利益が出ていたために法人税を納めていたものの、今期は経営悪化などで損失が出た場合は、前期に納めた法人税を還付請求できます。
なお、法人税等とは、主に次の3つの税金のことです。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
このうち、繰戻し還付は国税である法人税(と地方法人税)のみに適用される制度です。
法人県民税と法人事業税においては地方税であるため、繰戻し還付制度の適用はありません。
そのため法人税や地方法人税で欠損金の繰戻し還付が適用される場合でも、法人事業税(所得割)と法人住民税(法人税割)の計算では、繰戻し還付がなかったものとして別途手続が必要です。
法人税の繰戻し還付と必要な手続について、次の3つの税金に分けて説明していきます。
法人税
法人税(と地方法人税)は、欠損金が生じたときに還付所得事業年度に繰戻すことで、すでに納付済の法人税や地方法人税の還付を受けられます。
法人税と地方法人税の還付請求額については、次の計算式で算出します。
|
法人税の還付請求額 = 還付所得事業年度の法人税額 × (欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額) 地方税の還付請求額 = 法人税の還付請求額 × 4.4%
|
法人事業税
当該事業年度で発生した繰戻し還付適用前の欠損金は、「欠損金額等及び災害損失金の控除明細書」の事業税の欠損金として翌期以降に繰り越し、翌期以降の法人事業税の計算の基礎となる所得金額から控除します。
住民税
欠損金の繰戻し還付の規定で還付された法人税額は、住民税の欠損金として「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」による翌期以降の繰り越しとなり、翌期以降の法人住民税の計算の基礎となる法人税額から控除します。
なお、還付された法人税額はその後の9年間で課税標準(法人税額)から控除対象還付法人税額の控除として繰り越すことになります。
法人税の繰戻し還付の要件
法人税の繰戻し還付により、すでに納めた税金を払い戻してもらうためには、次の要件を満たすことが必要です。
- 還付所得事業年度から欠損事業年度の全事業年度までの各事業年度で、連続して青色申告による確定申告書を提出していること
- 欠損事業年度の青色申告による確定申告書を期限までに提出していること
- 欠損事業年度の確定申告書と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出していること
還付所得事業年度とは、欠損金が発生した事業年度(欠損事業年度)開始日前1年以内に開始した事業年度です。
事業年度が12か月なら、前事業年度が還付所得事業年度となります。
また、欠損金の繰戻し還付を適用できるのは「中小企業者等」であり、次の法人が該当します。
- 普通法人(資本金または出資金が1億円以下)(資本金5億円以上の親会社の100%子会社以外)
- 法人税法で定められている公益法人や協同組合など
- 法人税法以外の法律で公益法人等とみなされる法人(団地組合管理法人・認可地縁団体・防災街区整備事業組合など)
- 人格のない社団等
繰戻し還付のメリット
繰越控除では、赤字を翌年度以降に赤字を繰り越すことで、将来の黒字と相殺できることがメリットです。
しかし黒字になるまでは、相殺効果を得ることはできないことはデメリットといえます。
それに対し欠損金の繰戻し還付では、支払い済の法人税が戻ってきます。
手元のお金が増えて資金繰りに余裕ができることは、大きなメリットです。
繰戻し還付のデメリット
欠損金の繰戻し還付は、国税にのみ適用される制度です。
法人住民税や法人事業税などは地方税であるため、繰戻し還付の対象にはならず、繰越控除として後の減税になります。
地方税については、効果の即効性を感じられないことがデメリットといえます。
また、繰戻し還付制度で還付請求があった場合、税務署からの問い合わせや税務調査などの対象になる可能性もあることは留意しください。
消費税等が還付されるケース
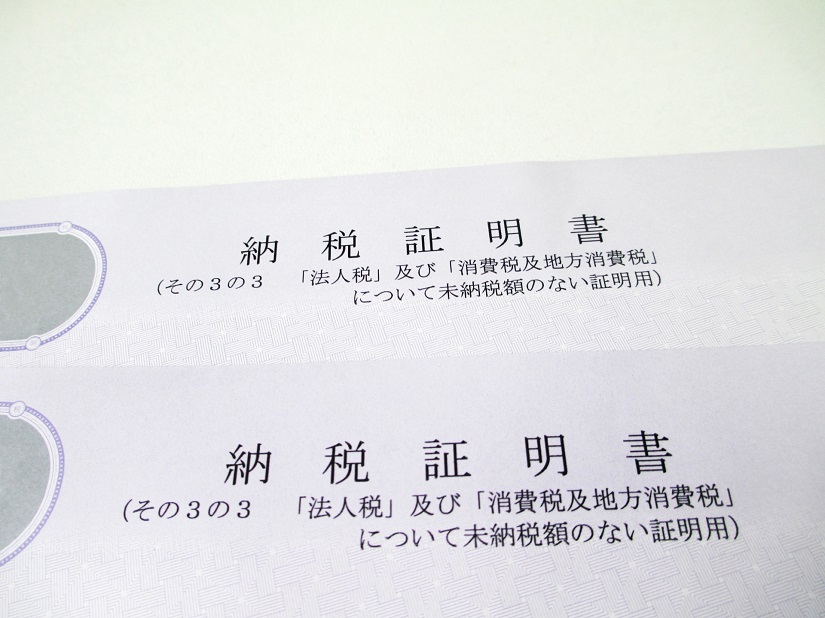
法人が納める税金は法人税等だけでなく、消費税なども含まれます。
消費税についても還付されるケースがあるといえますが、たとえば次の2つのケースです。
- 中間納付で納め過ぎていた場合
- 仮受消費税より仮払消費税が多い場合
それぞれ説明します。
中間納付で納め過ぎていた場合
消費税等も、法人税と同じく中間納付することができます。
前期の納付額に応じて中間納付の回数や支払う金額を決定し、中間納付で納めた金額と確定した納税額との間で差が発生すれば、その差額は還付されます。
仮受消費税より仮払消費税が多い場合
商品などを販売したときに顧客から預かった仮受消費税よりも、商品などを購入したときに支払う仮払消費税のほうが多ければ、その差額は還付の対象です。
たとえば設備投資などで、高額な設備や備品を購入したため、仮払消費税が多くなっているときなどに発生しやすい事例といえます。
また、不動産を購入したときのも還付されることがあります。
仮受消費税が発生しない輸出取引についても、取引全体で見ると仮払消費税が仮受消費税を上回ることが多いため、その差額相当分が還付されます。
法人税を還付してもらう方法

法人税を還付してもらうための還付申告は、対象年の翌年から5年間で行うことが必要です。
たとえば2022年分の還付申告については、2023年1月1日から2026年12月31日までに行うことが必要となります。
なお、還付申告書については提出期限が定められていません。
対象年の翌年1月1日以後であればいつでも提出できるため、還付金等の消滅時効の規定の適用による還付請求の起算日は翌年1月1日となります。
たとえば平成30年分の還付請求については、平成31年1月1日から令和5年12月31日までとなるため、この期間を経過した後で還付請求しても認められません。
郵送で提出する場合には、期間内の消印であれば受け付けてもらうことができるため、遅れることなく申告しましょう。
なお、法人税を払いすぎているのではなく、反対に支払いが厳しいときには延滞税など発生する可能性があります。
その場合、以下の記事を参考に対処法を検討することをおすすめします。
法人税の延滞金が発生するケースとは?支払えない場合の対処法を解説
まとめ
法人税は、法人の事業活動で得た所得に対する税金ですが、様々なケースで還付してもらえます。
青色申告で確定申告書を提出している法人の場合には、生じた欠損金を繰り戻して還付請求できる制度もあり、活用すれば手元のお金を増やせます。
還付されるのは法人税と地方法人税のみで、地方税である法人住民税や法人事業税は繰越控除による減額となります。
法人税に限らず消費税の還付対象となるケースもありますが、いずれの場合でも還付申告の手続は、期限内に申請することが必要です。
期限を過ぎれば時効により請求できなくなってしまうため、還付請求により払い戻してもらえる税金があるときには、忘れず手続しましょう。
中小企業経営者向け!