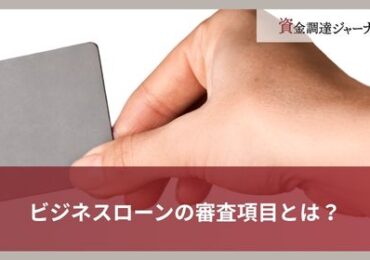両立支援等助成金とは、従業員が仕事と家庭を両立して働くことができるように、環境作りへ取り組む事業主のための制度です。
複数のコースがあるため、種類によって申請における要件や期限などは異なります。
夫婦共働きが当たり前になった現代では、両立支援等助成金を活用して働きやすい職場に整えることで、離職率低下や人材確保につなげられます。
そこで、両立支援等助成金について、コースの種類や内容、申請方法をわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

両立支援等助成金とは

「両立支援等助成金」とは、仕事を続けながら子育てや介護ができる就業環境を整備する事業主へ支給される助成金です。
労働者の雇用安定化を目的として創設された制度であり、職業と家庭を両立する職場環境づくりを支援する制度といえます。
日本では共働きが一般化していることや、高齢化が進んでいるため育児や介護をしながら働く方も少なくありません。
しかし継続して働くことのできる就労環境を整備することで、育児や介護を理由に離職せざるを得ない状況を回避し、定着率をアップさせられます。
両立支援等助成金では、多くのコースで中小企業事業主のみを支給対象としています。
両立支援等助成金のメリット
両立支援等助成金は、従業員が育児・介護・不妊治療などを行いながら、安心して仕事を続けることができるようにするための制度です。
取り組みとして休業制度や業務代替体制を整えるなど、一定要件を満たした事業主に必要な資金が助成金として支給されます。
以上を踏まえて、両立支援等助成金のメリットといえるのは以下の3つです。
- 職場環境が整備される
- 人材確保が有利になる
- 人材定着につながる
それぞれ説明します。
職場環境が整備される
両立支援等助成金のメリットは、従業員が長く働ける環境が整備されることです。
従業員が育児や介護などを続けながら、仕事ができる環境を整備しなければなりません。
申請に向けて条件を満たすことにより、仕事と家庭を両立できる体制が構築され、従業員が長く働ける環境が整備されます。
人材確保が有利になる
両立支援等助成金のメリットは、人材の確保が有利になることです。
人手を募集するときに、仕事と家庭を両立できる職場環境が整備されていることは、ワークライフバランスが保たれるため安心して働けます。
休業体制や職場復帰体制、様々な勤務制度などが整備されていることは、求人応募に有利になると考えられます。
人材定着につながる
両立支援等助成金のメリットは、人材定着につながることです。
育児や介護などの問題を抱えている従業員の多くは、仕事と家庭を両立することに難しさを感じており、離職してしまうケースもあります。
しかし事業主が両立支援等助成金を活用することで、従業員が仕事を続けることができる可能性が高まり、会社も戦力を失うことがありません。
両立支援等助成金の注意点
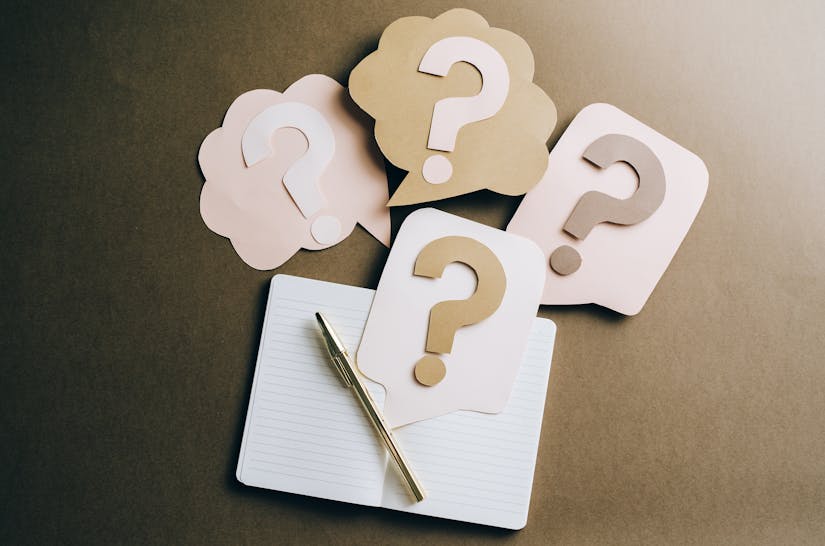
両立支援等助成金は、夫婦共働きが主流となった現代や、在宅介護が増えつつある現状に即した制度といえます。
そのため有効活用が望ましい制度といえるものの、申請においては以下の5つに注意しましょう。
- 支給される単位に注意する
- 制度整備が必要になる
- 労務管理を徹底する
- 受給時間に注意する
- 従業員へ周知する
それぞれ説明します。
支給される単位に注意する
両立支援等助成金の申請においては、支給される単位に注意しましょう。
事業主単位で支給される助成金であり、事業所単位ではありません。
また、支給対象となるのは原則、中小企業事業主であり、以下の要件を満たす事業主です。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
制度整備が必要になる
両立支援等助成金の申請においては、制度整備が必要です。
たとえば育児休業は、労働協約や就業規則に運用ルールを明記することが必要となります。
単に育児・介護休業法の内容によるなどの委任規定だけでは十分といえません。
また、介護休業では介護支援プランの作成も必要です。
労務管理を徹底する
両立支援等助成金の申請においては、労務管理を徹底しましょう。
申請において添付書類が必要であり、たとえば出勤簿・労働者名簿・賃金台帳・労働条件通知書などを求められることが多いといえます。
提出を求められても問題なく対応できるように、普段から作成・保存しておくことが大切です。
就業規則は最新の法令に沿った内容にすることが必要となるため、改正があれば内容を確認し最新状態に整備してください。
受給時間に注意する
両立支援等助成金の申請においては、受給時間に注意してください。
準備を開始して助成金を受給するまで、概ね2〜3か月はかかります。
制度によってはさらに長期化する場合もあるため、助成金に頼りすぎない資金繰りを徹底しましょう。
従業員へ周知する
両立支援等助成金の申請においては、従業員へ制度を周知しましょう。
休業制度・短時間勤務制度・費用補助制度などを創設しても、従業員が制度の存在を知らなければ意味がありません。
そのため、回覧・メール・イントラネットなどを活用するなど、社内の従業員が把握しやすい状況を作ることが必要です。
両立支援等助成金のコース

働き続けながら、子育てや介護などを行う従業員の雇用継続を図るために、就業環境を整備する事業主に支給されるお金が両立支援等助成金です。
事業主の取り組み促進と雇用安定を図ることにつながるといえますが、両立支援等助成金には主に以下の6つコースがあります。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 育児休業等支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 不妊治療両立支援コース
- 育児中等業務代替支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
それぞれ簡単に説明します。
なお、各コースの申請における概要や必要書類等に関しては、厚生労働省・東京労働局の公式サイト「仕事と家庭の両立に関する助成金(両立支援等助成金)」を参考にしてください。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」は、男性従業員が育児休業を取得しやすい労働環境を整備した事業主に助成金が支給されます。
事業主が雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得したときや、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成される制度といえます。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり) |
①第1種(男性の育児休業取得)(対象労働者が子の出生後8週以内に育休開始)
②第2種(男性育休取・得率の上昇等)(第1種受給年度と比較し男性育休取得率が30ポイント以上上昇した場合等)
|
| 申請期限 | ①第1種 対象労働者の育児休業が終了した日の翌日から2か月以内 ②第2種 要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内※第1種を受給した事業主のみ |
育児休業等支援コース
「育児休業等支援コース」は、働き続けながら育児をする従業員の雇用継続を図るために、育児休業の円滑な取得と職場復帰に向けた取り組みを行った中小企業事業主に助成金が支給されます。
仕事と家庭の両立支援に関する取り組みを促し、雇用安定に資することを目的とした制度です。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)※無期雇用者、有期雇用労働者各1人限り | ①育休取得時(プランに基づき3か月以上の休業取得) 30万円 ②職場復帰時 (育休から復帰後、継続雇用) 30万円 |
| 申請期限 |
①育休取得時 育児休業(産後休業の終了後、育児休業を継続するときは産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する翌日から2か月以内 ②職場復帰時 育児休業終了日の翌日から起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 ③業務代替支援(新規雇用/手当支給等) 育児休業終了日の翌日から起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 ④職場復帰後支援(子の看護休暇制度/保育サービス費用補助制度) 育児休業終了日の翌日から起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 |
介護離職防止支援コース
「介護離職防止支援コース」は、仕事と介護を両立する従業員を支援するための職場環境整備に取り組み、介護支援プランを作成・措置を実施し、介護休業の円滑な取得と職場復帰の取り組みを行った場合に助成金が支給されます。
仕事と介護との両立に資する制度利用の円滑化に向けた取り組み、家族を介護する労働者の有給休暇取得の取り組みを実施した中小企業事業主が対象です。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)※介護休業・介護両立支援制度それぞれで1年度5人まで |
①介護休業
②介護両立支援制度 30万円 |
| 申請期限 | ①介護休業取得時 対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計5日経過する日の翌日から2か月以内 ②職場復帰時 対象労働者の介護休業終了日の翌日から起算して3か月経過する日の翌日から2か月以内※支給対象は、休業取得時と同じ対象労働者の同介護休業について、休業取得時を受給している場合 |
不妊治療両立支援コース
「不妊治療両立支援コース」では、不妊治療と仕事を両立するための職場環境整備に取り組み、不妊治療両立支援プランの策定とそれに基づく措置を実施し、治療を目的とした休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に助成金が支給されます。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり) | 環境整備・休暇取得等 (対象労働者が5日(回)以上制度を利用) 30万円※1回限り |
| 申請期限 | ①環境整備・休暇取得等 不妊治療休暇・両立支援制度を5日(回)利用した日の翌日から2か月以内 ②長期休暇加算 不妊治療休暇(20日以上連続)終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内 |
育児中等業務代替支援コース
「育児中等業務代替支援コース」は、仕事を続けながら育児をする従業員の雇用継続を図るために取得した育児休業や育児短時間勤務に対し、業務代替体制を整備した中小企業事業主へ助成金が支給されます。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間 | ①育児休業中の手当支給 最大125万円 ②育短勤務中の手当支給 最大110万円 ③育児休業中の新規雇用 最大67.5万円 |
| 申請期限 | 対象労働者が取得した育児休業期間、または利用した育児短時間勤務制度の利用期間により申請期間は異なる |
柔軟な働き方選択制度等支援コース
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」とは、仕事を続けながら育児をする従業員の雇用継続を図るために、子が3歳以降小学校就学前までの従業員について柔軟な働き方ができる制度を複数導入する取り組みを行った中小企業事業主に支給される助成金です。
| 支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)※1年度5人まで | ①制度2つ導入の上、対象者が制度利用 20万円 ②制度3つ以上導入の上、対象者が制度利用 25万円 |
| 申請期限 | 6か月間の制度利用期間翌日から2か月以内 |
両立支援等助成金の申請方法

両立支援等助成金は、以下の流れに沿って申請しましょう。
|
なお、コースによっては一般事業主行動計画の策定と、労働局への届出が必要となります。
一般事業主行動計画とは、仕事と育児や介護を両立できる環境整備に、どのように取り組むか計画を立てることです。
従業員が100人以上の会社では、一般事業主行動計画の策定・届出・周知が義務付けられています。
また、郵送での申請においては、期限内に必着とされているため注意してください。
必要書類はコースによって異なるため、必ず確認しもれなく準備を進めましょう。
まとめ
両立支援等助成金とは、仕事と家庭を両立する職場環境の整備に取り組む事業主を支援する制度です。
育児休業や介護休業の取得促進を目的とした制度でもあり、働きやすい職場を整えることで離職率低下や人材確保につなげることができます。
夫婦共働きや在宅介護が増えつつあるため、両立支援等助成金を有効活用することをおすすめします。
中小企業経営者向け!