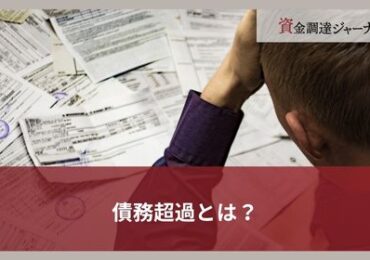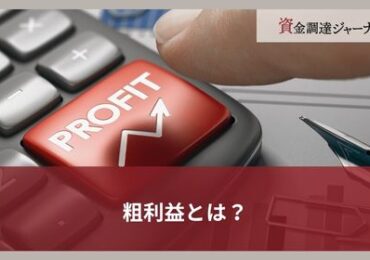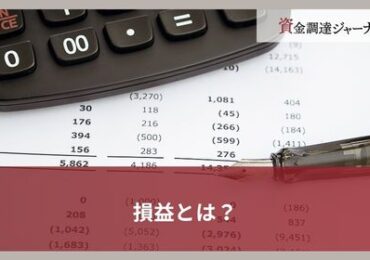債務超過とは、負債総額が資産総額を上回っている状態です。
所有する資産をすべて売却し、お金に換えて債務の返済に充てても、完済できない状況を債務超過といいます。
債務超過とは倒産を意味する言葉ではなく、赤字や資金ショートとも異なります。
そこで、債務超過とはどのような状態なのか、問題点と貸借対照表の判断基準、解消法などについてわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

債務超過とは
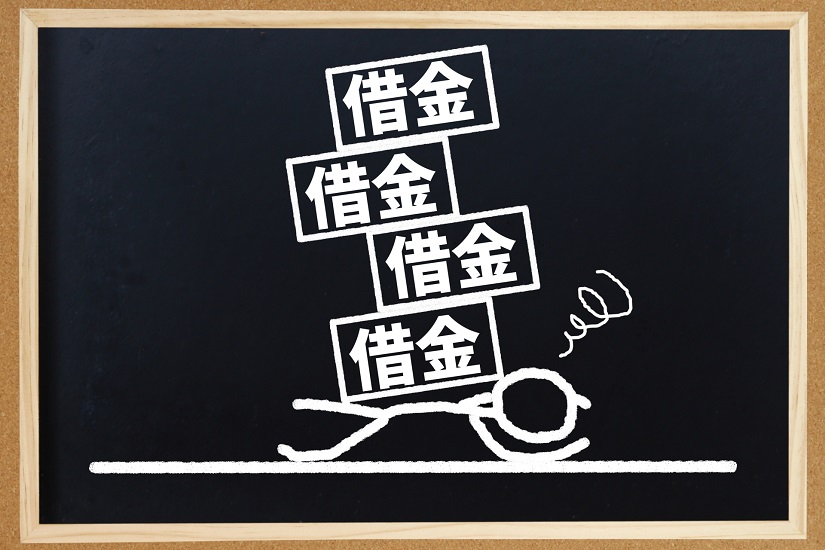
「債務超過」とは、貸借対照表の純資産がマイナスであり、負債総額が資産総額を上回っている状態のことです。
在庫商品や事務所備品など、すべて売り払ってお金に換えて借金や固定費の支払いに充てても、賄いきれない状態といえます。
資産をすべて簿価で売却しても借金が残ってしまうため、財政状態が不健全な会社に見られることの多い状態です。
債務超過とは赤字や資金ショートと異なる状況といえますが、それぞれ次の2つに分けて説明します。
- 赤字との違い
- 資金ショートとの違い
赤字との違い
「赤字」とは、損益計算書の当期純損益がマイナスの状態です。
単年度の収益に損失が発生している状況ですが、長年に渡る赤字では倒産リスクが高くなります。
ただし一過性の理由による赤字であれば、黒字転換も期待できます。
なお、赤字であることが原因で債務超過に陥るわけではなく、黒字でも債務超過の場合はあります。
そのため債務超過と赤字には、以下の違いがあると考えられます。
| 債務超過 | 貸借対照表の純資産はマイナスで財務の安全性が低下している |
| 赤字 | 損益計算書の当期純損益がマイナスで単年度の収益が悪化している |
債務超過と赤字経営の違いとは?倒産リスクを回避するための対策を徹底解説
資金ショートとの違い
「資金ショート」は、手元の現金が不足している状態です。
債務超過と資金ショートには、緊急性に違いがあります。
資金ショートすると、借入金を返済できなかったり納税できなかったり、設備費用の支払いができないなど倒産に直結する緊急性の高い状態です。
赤字または黒字に関係なく、売掛金の回収が遅れることや、支払いが先行することで資金ショートすることはあり得ます。
債務超過も長期化すればいずれ倒産してしまう恐れはありますが、資金ショートほどのひっ迫した状態ではないといえます。
債務超過の原因
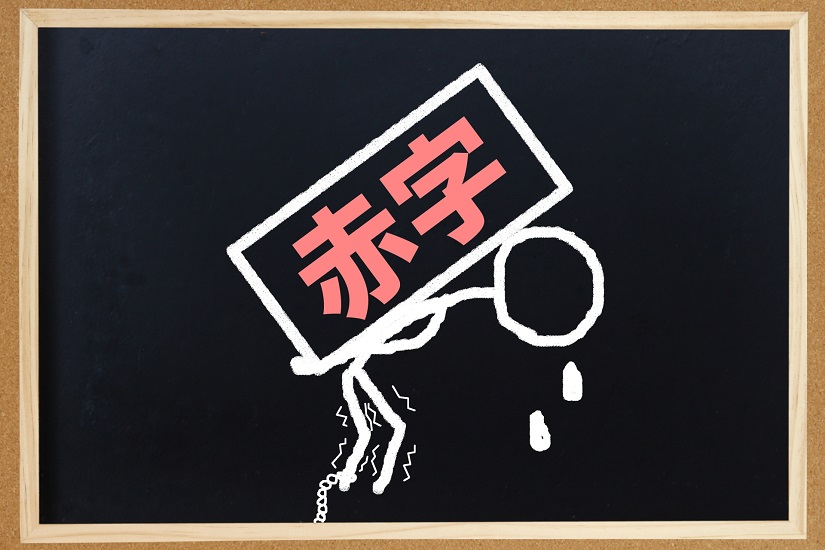
債務超過に陥ってしまう「原因」は、主に次の5つです。
- 起業して間もない
- 赤字が常態化している
- 投じた資本を回収できていない
- 資本金が少なすぎる
- 財務状況を把握できていない
それぞれ説明します。
起業して間もない
起業して間もない時期は、初期投資を回収できていない状況のため、債務超過に陥ることがあります。
会社設立や事業開始の時期はいろいろな費用が必要となるため、実際に事業が軌道に乗るまで経営は安定せず、赤字が続いてしまえば債務超過に陥るとも考えられます。
ただし経営が安定してくれば、黒字転換できる可能性もあるため、初期段階での債務超過はそれほど大きく心配する必要はありません。
赤字が常態化している
赤字が常態化していることも、債務超過に陥ってしまう原因です。
長期に渡る赤字経営で、現預金などの資産は減少してしまいます。
資産が減少すれば負債のほうが多くなりやすいため、債務超過に陥ってしまうと考えられます。
投じた資本を回収できていない
銀行融資で資金調達後、設備などに投じた資本を回収できていないことも、債務超過に陥ってしまう原因です。
新規事業や設備投資で必要な資金を借入れで調達した場合、想定したとおりの利益を得ることができなければ、負債だけが増加します。
返済に充てる予定の収益を得られない状況で、手元の資金不足で新たに融資を頼ることが必要であれば、負債が膨れ上がることで債務超過に陥ると考えらえます。
資本金が少なすぎる
資本金が少なすぎることも、債務超過に陥ってしまう原因です。
現在では、1円の資本金で会社を設立することもできます。
しかし会社経営をスタートさせる上で、設備投資や運転資金の原資となる資本金が少なすぎると、少額の赤字でも債務超過に陥りやすくなります。
財務状況を把握できていない
本業が忙しく、十分に財務状況を把握できていないことも、債務超過に陥る原因といえます。
スモールビジネスでは、経営者がトップセールスマンも兼ねて活躍している場合など、経理事務がおろそかになりがちです。
利益の減少や負債の増加などをから、債務超過の兆候を感じられなけければ、対策を講じることもできません。
債務超過の問題点

債務超過に陥るとすぐに倒産するわけではないものの、経営状況が悪化していることにかわりはありません。
そのため債務超過とは、次の4つの問題点を抱えた状態と考えられます。
- 倒産リスクが高まる
- 金融機関に信用されなくなる
- 取引先との関係が悪化する
- 上場廃止になる
それぞれの問題点について説明します。
倒産リスクが高まる
債務超過の問題点は、「倒産リスク」が高まることです。
所有する資産を現金化しても、負債を解消できない状況のまま、純資産が尽きてしまえば債務超過を解消できません。
債務超過の状況が続けば、手元の資金も足らなくなると考えられるため、倒産リスクを高めてしまいます。
金融機関に信用されなくなる
債務超過の問題点は、金融機関に信用されなくなることです。
信用を失えば、資金の借入れを申し込んでも審査に通りません。
返済能力に不安がある会社などに融資は実行しないため、債務超過で銀行の企業格付が下落していれば、追加融資は厳しくなることに注意しましょう。
取引先との関係が悪化する
債務超過の問題点は、取引先との関係が悪化することです。
仕入先や販売先などが、債務超過であることを知れば、資金難に陥っている経営の危うい会社と懸念されないとも言い切れません。
それにより、契約の打ち切りや、取引量や決済方法を変更されたり制限されたりする恐れもあります。
上場廃止になる
債務超過の問題点は、上場企業の場合、「上場廃止」となることです。
日本取引所グループでは、上場廃止の基準を以下としています。
| 債務超過状態となってから1年以内に状態を解消できなかったとき |
債務超過に陥り、1年以内に解消できなければ、上場廃止となり株価が暴落して資金調達も難しくなります。
債務超過の判断基準
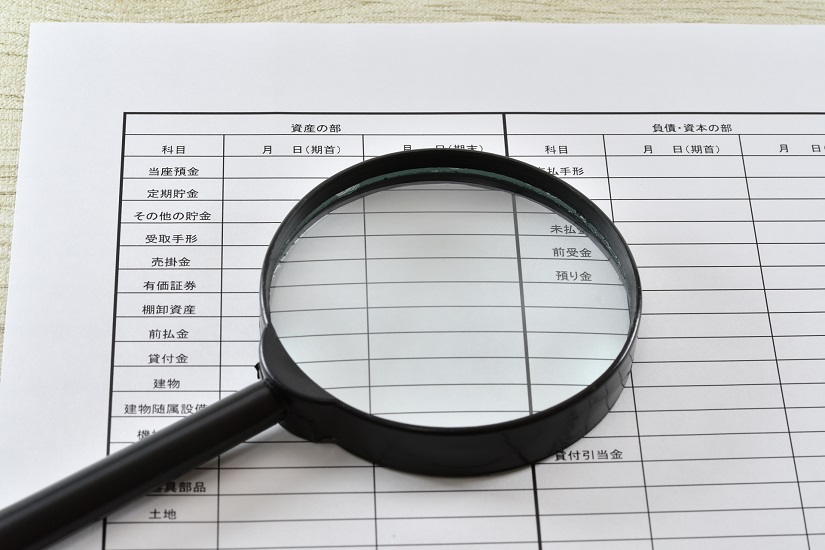
現在、債務超過に陥っているのか確かめたい場合には、以下の3つの判断基準を参考にしてください。
- 貸借対照表による基準
- 実態貸借対照表による基準
- 経営分析の指標による基準
それぞれ説明します。
貸借対照表による基準
債務超過に陥っているか見分けるときは、「貸借対照表」により以下の2つの方法で確認できます。
- 資産から負債を差し引く方法
- 純資産の減少を確認する方法
それぞれ説明します。
資産から負債を差し引く方法
債務超過に陥っているか見分けるときは、貸借対照表の資産から負債を差し引いてみましょう。
その数値が、以下のどちらに該当するかによって債務超過か判断できます。
|
「資産合計-負債合計」 = 「資産>負債」 = 債務超過ではない 「資産合計-負債合計」 = 「負債>資産」 = 債務超過である
|
経営管理が疎かであるため債務超過とも考えられるため、違和感があるときや債務超過の傾向を掴みたいときは、定期的にチェックすることをおすすめします。
純資産の減少を確認する方法
債務超過に陥っているか見分けるときは、貸借対照表の「純資産」の減りを確認しましょう。
負債を貯めた純資産から支払っていれば、実質的に、負債のほうが資産を上回っているため債務超過と判断できます。
実態貸借対照表による基準
債務超過に陥っているか見分けるときは、「実態貸借対照表」を作成して確認しましょう。
実態貸借対照表とは、現時点の適切な資産額を算出し、現実に即した数値へ修正した貸借対照表です。
通常の貸借対照表から実態貸借対照表への修正は、以下の項目ごとに行います。
| 資産の修正 | 売掛金・貸付金・未収入金 | 回収不可能なものや長年回収していないものは差し引く |
| 棚卸資産 | 架空在庫や不良在庫を差し引く | |
| 仮払金・繰延資産 | 資産性がないものを差し引く | |
| 土地 | 時価へ修正する | |
| 建物 | 減価償却を適用した額へ修正する | |
| 投資有価証券 | 時価に修正する | |
| 負債の修正 | 役員未払金・役員借入金 | 純資産とみなして差し引く |
| 退職給付引当金 | 積立分の不足額は負債へ計上する | |
| 保証債務 | 保証人債務の発生はその金額を負債へ計上する |
経営分析の指標による基準
より詳細に債務超過に陥っているか確認したいときは、以下の経営分析の「指標」を基準にするとよいでしょう。
- 流動比率
- 当座比率
- 固定比率
- 固定長期適合率
- 負債比率
それぞれ説明します。
流動比率
「流動比率」とは、短期的な支払い能力をあらわす指標です。
|
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%
|
上記の割合が100%を超えていれば、流動資産が流動負債を上回っているため、短期的な支払い能力に問題がないと判断されます。
当座比率
「当座比率」も、流動比率と同様に、短期的な支払い能力をあらわす指標です。
|
当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100%
|
上記の割合が100%以上なら、短期的な支払い能力には問題がないと判断されます。
固定比率
「固定比率」とは、自己資本に対する固定資産の比率であり、長期的な支払い能力をあらわす指標です。
|
固定比率 = 固定資産 ÷ 自己資本 × 100%
|
固定資産は長期的に使用するため、返済期限のない自己資本で調達することが望ましいといえます。
そのため上記の割合が低いほど安全性が高いとされており、100%以下なら固定資産をすべて自己資本で賄っていると判断できます。
固定長期適合率
「固定長期適合率」も、固定比率と同様に長期的な支払い能力をあらわす指標です。
|
固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (自己資本+固定負債) × 100
|
固定資産が安定した資金でまかなうことができているか示すため、上記の割合が低いほど財務状況は安定していると判断できます。
100%未満なら、長期的な安全性に問題がない状態と考えられます。
負債比率
「負債比率」とは、自己資本に対する負債の比率であり、長期的な安全性をあらわす指標です。
|
負債比率 = 負債 ÷ 自己資本 × 100%
|
上記の割合が低い方が財政上の安全性は高いと判断できます。
借入金への依存度を示すため、100%以下なら負債を自己資本で賄うことができている状態です。
目安は100~150%と考えられますが、小売業や宿泊飲食業などは200%超が平均となるため、業種などで基準は異なります。
債務超過を解消する方法

債務超過ですぐに倒産することはなくても、何の対策も取らずに放置すれば、いずれ事業継続は困難な状況となります。
そのため解消することが必要ですが、その方法として以下の4つが挙げられます。
- 経営を見直す
- 増資する
- 債務免除を交渉する
- 債務を株式に転換する
それぞれ説明します。
累損とは?原因や赤字の種類・債務超過の解消方法をわかりやすく解説
経営を見直す
債務超過を解消するために、経営を見直すことが必要です。
経営の見直しは利益を生むための対策ですが、売上を増やすか支出を減らすことで利益は増えます。
そこで、営業戦略と支出を見直し、無駄なコストを削減することも徹底して行いましょう。
増資する
債務超過を解消する方法として、「増資」することが挙げられます。
増資とは資本金を増やすことですが、以下の3つの方法があります。
| 公募増資 | 新株発行の際に不特定多数の投資家に出資を募る方法 |
| 第三者割当増資 | 特定の第三者に新株を発行する方法 |
| 株主割当増資 | 既存株主に保有株式数の新株を割り当てる方法 |
増資で債務超過が解消されても、優遇税制が適用されなくなる場合があるため注意してください。
債務免除を交渉する
債務超過を解消する方法として、「債務免除」を交渉することが挙げられます。
債務免除とは、債権者に借金を放棄してもらうことです。
交渉により、債務免除に合意してもらうことで借金が消滅し、「債務免除益」として利益に計上できます。
債務を株式に転換する
債務免除を解消する方法として、債務を株式へ転換する「DES(デット・エクイティ・スワップ)」を行うことが挙げられます。
返済義務を実質的になくすための方法であり、次の2つから選択できます。
| 新株払込方式 | 新株発行により払い込まれた資金を返済に充てる方法。会社の株式発行総数が増えるため、既存株主の持株比率や利益に影響することを踏まえた株式の保有割合の検討が必要。 |
| 現物出資方式 | 債権者が債務者に債権を出資する方法。借入金などを出資とみなし、株式を交付するため、現金の移動はなく帳簿上で調整できる。 |
まとめ
債務超過とは、資産よりも負債が上回っている状態であり、単なる赤字や資金ショートとは異なります。
ただし赤字が続けば、いずれ債務超過に陥ることとなり、資金ショートのすえ倒産するリスクは高まるでしょう。
そのため債務超過を解消することや、赤字経営であれば黒字転換することが必要です。
また、会社が倒産する理由の資金ショートを未然に防ぐために、手元の資金を枯渇させない資金調達の方法も確保しておきましょう。
赤字や債務超過でも、売掛金を現金化するファクタリングなら資金調達の方法として活用できるため、方法の1つとして検討してください。
中小企業経営者向け!