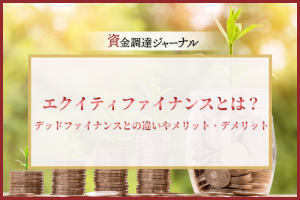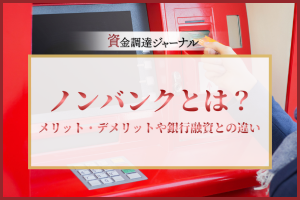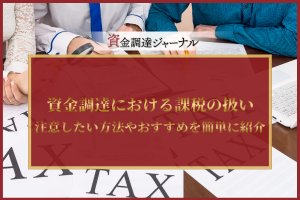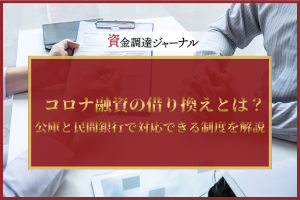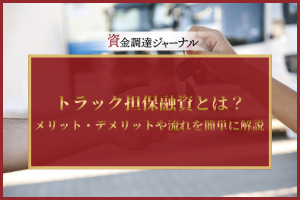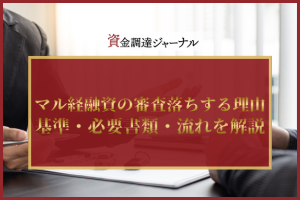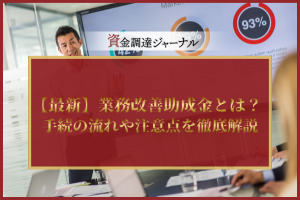事業主貸とは、個人事業主がプライベートの支払いを事業用の預貯金で支払ったときなどに使用する勘定科目です。
個人事業主は、法人と異なり事業者本人が経営者であるため、役員報酬などの概念はありません。
そのため、プライベートと事業用の収支を区別するために事業主勘定を使うことになりますが、事業主貸と事業主借の2つの使い分けが必要です。
そこで、事業主貸を含めた事業主勘定について、事業主借との使い分け方や仕訳例をわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

事業主勘定とは
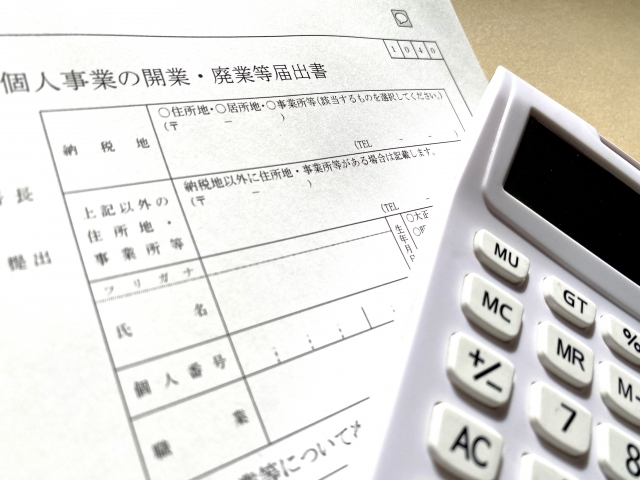
「事業主勘定」とは、個人事業主がプライベートと事業用のそれぞれに使ったお金を区別するための勘定項目です。
会社経営者であれば、事業は法人、経営者は個人と事業と経営者が別人格で分かれています。
そのため経営者がプライベートで使用した支払いと、事業のために使ったお金が区別できなくなることはありません。
しかし個人事業主は、個人の事業であり、経営するのも個人です。
事業と経営はどちらも個人となるため、支払ったお金がプライベートと事業のどちらのためだったのか、区別することが必要となります。
たとえば個人名義の車をプライベート以外にも事業で使っているときなどは、ガソリン代の計上においてプライベートと事業のどちらで使った燃料なのか、区別が難しいと考えられます。
そもそも個人事業主には役員報酬や給与などの概念がないため、生活費も事業用の預貯金から引き出すこともあれば、事業資金を個人の預貯金から充てることもあります。
事業と直接関係のない費用が発生することや、預貯金を引き出したり預け入れたりといったケースにおいて、用いる勘定科目が事業主勘定といえます。
事業主勘定の種類

事業主勘定は、以下の2種類に分類されます。
- 事業主貸
- 事業主借
名称が似ているため混同しやすいため、実際の会計処理においてどのようなときに使用するのか確認しましょう。
それぞれ説明します。
事業主貸
「事業主貸」とは、事業用のお金を生活費で使用したときに用いる勘定科目であり、たとえば以下の場合の処理で使います。
|
個人事業主が家計の支払いを事業用の預貯金で支払ったときや、事業で得た利益を家計の支払いに充てるため事業用口座から引き出したときに事業用貸で処理します。
なお、通常であれば事業で収益を得るための支払いは、必要軽費として認められますが、事業主貸で処理した支払いは必要経費にはなりません。
事業側から見たときの事業用貸で処理した支払いは、事業者である個人にお金を貸した状態ともいえるため、「事業主貸」という勘定科目で処理を行います。
事業主借
「事業主借」とは、プライべート用のお金を事業用へと移したときの勘定科目であり、たとえば以下のケースで用います。
|
事業用資金が一時的に不足したときの個人資金での充当や、必要経費をプライベートのお金で立替えて払ったときなどに用いる勘定科目です。
事業主貸とは反対に、事業側から見れば個人からお金を借りたことになるため、「事業主借」の勘定科目で処理をします。
事業主勘定の仕訳例
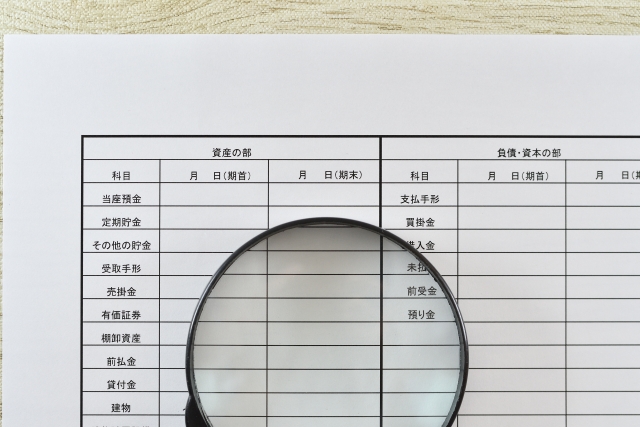
事業主勘定を使うときはどのようなケースなのか、実際の仕訳例で確認するとわかりやすいといえます。
そこで、以下の2つの仕訳例をそれぞれ説明していきます。
- 事業主貸の仕訳例
- 事業主借の仕訳例
事業主貸の仕訳例
事業主貸は、事業用資金を個人の生活費などプライベートで使用したときの勘定科目ですが、仕訳例をいくつか紹介します。
| 例:事業用の普通預金口座から個人の生活費30万円を引き出した | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主貸 300,000 | 普通預金 300,000 |
上記は、基本的な事業主貸の使い方の例といえます。
| 例:本年分の個人の住民税15万円を事業用の普通預金預金から支払った | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主貸 150,000 | 普通預金 150,000 |
なお、事業所得に対する事業税や税込経理の消費税、領収書などに貼付して納める収入印紙などは「租税公課」の勘定科目で経費計上できます。
| 例:個人の国民健康保険料3万円が、事業用の普通預金口座から引き落とされた | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主貸 30,000 | 普通預金 30,000 |
国民年金・国民年金基金・国民健康保険料などは事業所得の経費として計上できません。
ただし所得税の確定申告で、「社会保険料控除」として、1年間で支払った保険料の金額を所得全体から差し引くことはできます。
| 例:個人の生命保険料(年払い)12万円を事業者用の普通預金から支払った | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主貸 120,000 | 普通預金 120,000 |
個人が加入している生命保険の保険料も、事業に関係しないため事業所得の経費として計上できません。
事業用で使っている車の自動車保険や、業務上の損害賠償責任保険などの保険料は必要経費として計上できます。
なお、生命保険や地震保険などの保険料は、確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除として所得全体から差し引くことが可能です。
| 例:全体の3割を事務所としても使っている自宅の家賃10万円を、事業用の普通預金口座から支払った | |
| 借 方 | 貸 方 |
|
事業主貸 70,000 地代家賃 30,000 |
普通預金 100,000
|
事業用として使っているのは、家賃100,000円×事務所割合30%=30,000円です。
プライベート用と事業用が混在する場合の家事関連費は、使用量や面積などの合理的な割合から按分することが必要となります。
毎月、家事按分した分を計上してもよいですが、一旦は地代家賃でまとめて支払い、決算時に1年分まとめて家事按分する方法も可能です。
| 決算時(1年分総額1,200,000円) | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主貸 840,000 | 地代家賃 840,000 |
|
事業主借の仕訳例
事業主借は、個人の生活費などプライベートのお金を事業用に移したとき合に使用する勘定科目ですが、仕訳例をいくつか紹介します。
| 例:事業用の資金が足らなくなったため、プライベートの預金から20万円引き出し移した | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 普通預金 200,000 | 事業主借 200,000 |
上記の仕訳が、基本的な事業主借の使い方といえます。
| 例:事業用の普通預金口座に、利息80円が入金された | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 普通預金 80 | 事業主借 80 |
事業用の預金の利息も「利子所得」に分類されるため、事業所得に関係のない扱いとなり、事業主借で処理します。
預金利息は源泉分離課税であるため、利息の受け取りの際に所得税や住民税が天引きされています。
税金は精算されている状態のため、確定申告に含める必要はありません。
| 例:事業用の自動車を買い替えるために下取りに出したときの価額が300,000円だった。車両の帳簿残高は100,000円であり、一度現金を受け取ったものとして処理する。 | |
| 借 方 | 貸 方 |
|
現金 300,000
|
車両運搬具 100,000 事業主借 200,000 |
事業用の車両などを売ったときも、事業の収入ではなく動産の譲渡として扱います。
そのため「譲渡所得」となり、事業所得に関係のない扱いとなるため、事業主借で処理します。
なお、動産の譲渡による譲渡所得は、確定申告に含めることが必要となるため注意しましょう。
| 例:個人のプライベートで使っていた電化製品をリサイクルショップで売却し、売ったお金50,000円を事業用の資金として充てた | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 現金 50,000 | 事業主借 50,000 |
事業用の動産ではなく、生活用の動産を譲渡したときには非課税として扱われます。
そのため、譲渡は確定申告に含める必要はないものの、売却代金を事業用資金に移したことで、事業主借で処理が必要です。
期末と期首の事業主勘定の処理方法

事業主勘定は、次の2つの時期にそれぞれ適切な処理が必要です。
- 期末(確定申告)
- 期首
上記のタイミングにおける処理方法を説明します。
期末(確定申告)
事業主勘定のうち、事業主借は会計において、事業が個人から借りた借入金です。
反対に事業主貸は、事業が個人へ貸した貸付金といえます。
個人事業主は、個人と事業が同一であるため、借入金と貸付金を両建てで残す必要はありません。
そのため決算修正において、以下の仕訳例のとおり相殺します。
| 例:事業主貸で100万円、事業主借は50万円がそれぞれの残高となったため、相殺処理を行った | |
| 借 方 | 貸 方 |
| 事業主借 500,000 | 事業主貸 500,000 |
相殺したことで、事業主借または事業主貸の一方が残ることになるものの、青色申告決算書の貸借対照表に計上したままで特に問題はありません。
事業主勘定の残高は、借入金または貸付金などの「資産・負債項目」のため、損益計算と関係がないからです。
そのため青色決算書上で残高がある場合でも、所得金額に影響せず、残っていてもよいと考えられます。
期首
事業主借・事業主貸・元入金・青色申告控除前の所得金額は、いずれも事業主の運転資金として考えられます。
そのため事業主借と事業主貸、元入金を両建てで残しておくことはできないため、翌期に繰り越すときには4つを「元入金」にまとめて他の3つの残高はゼロへリセットします。
この場合に行う会計処理の流れと、流れをまとめた計算式は以下のとおりです。
- 事業主貸が残ったときは元入金から減算
- 事業主借が残ったときは元入金へ加算
- 前年分の青色申告控除前の所得金額を元入金へ加算
|
新年度の元入金 = 前年の青色申告特別控除前の所得金額 + 前年における期末元入金 + 事業主借勘定 - 事業主貸勘定
|
なお、青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得を計算するときに、決算上の利益から差し引きます。
そのため青色申告特別控除を差し引く前の金額で計算します。
計算した結果マイナスになっても特に問題はなく、繰越処理で翌年期首の損益や事業主勘定はすべてゼロにリセットされます。
青色事業専従者給与の特例が適用されるケース
確定申告を青色申告で行うのなら、一定要件を満たすことにより、「青色事業専従者給与の特例」が適用されます。
「青色事業専従者給与の特例」とは、生計が同じ配偶者や親族への給与を経費計上できる特例措置です。
個人事業主は事業に従事する配偶者や親族に対し支払った給与があっても、経費として計上できません。
しかし、青色事業専従者給与の特例が適用されれば、配偶者や親族に対する給与を「専従者給与」の勘定科目で、経費として計上できます。
青色事業専従者給与の特例は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署へ提出することが必要です。
詳しくは、国税庁の公式ホームページの「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」を参考にするとよいでしょう。
まとめ
事業主貸や事業主借などの事業主勘定は、個人事業主が日々の取引を会計処理し、帳簿を作成する上で用いる勘定科目です。
プライベートと事業で使ったお金を明確に区分するための勘定科目であり、事業に関係のない収入や支出を分けるときに使うことで、適正な事業所得を計算できます。
個人事業主は事業と経営をどちらも事業者である個人が担うため、プライベートと事業のどちらで使ったお金なのか、区分しにくい部分もあります。
しかし事業主貸や事業主借の勘定科目で整理できれば、正しい損益計算ができます。
中小企業経営者向け!