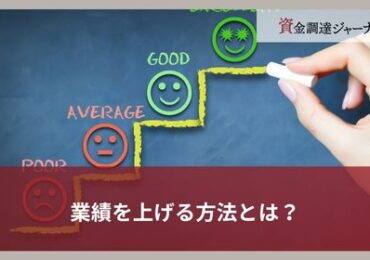売上低迷で危機的状況にある企業は、まず会社の枠組みから見直すことが必要です。
そこで、売上低迷の原因について、把握と改善に有効な枠組みと対策を解説します。
中小企業経営者向け!

売上低迷の要因

会社の売上が減少し、低迷といわれる状態になる要因は、大きく次の2つに分けられます。
| 外的要因 | 周囲の状況や他者からの影響など社内以外に要因がある場合 |
| 内的要因 | 行動の結果の原因が性格や能力など社内に要因がある場合 |
市場や経済の変化など、会社の外の影響で売上が低迷してしまうのが「外的要因」で、社内の営業力などに問題があり売上低迷に陥るのが「内的要因」です。
売上が低迷する5つの外的要因
社内ではなく、社外で起きたことが影響し売上が低迷することを外的要因といいますが、主に次の5つが挙げられます。
- 流行による影響
- 周囲の環境変化による影響
- 同業他社の業績向上による影響
- 商品・サービスのイメージが悪化している
- ホームページやSNSのアクセス数が減少している
それぞれ説明します。
流行による影響
売上が低迷してしまう外的要因として挙げられるのが、時代の流れなどによる「流行」です。
「はやり」に乗ることができた場合には、売上を大きく伸ばすことができます。
流行は永続的に続くわけではなく、次の流行に移れば売上は下がるため、縛られすぎれば売上は低迷します。
業界に限らず、消費者の購買意欲が高いものは一時爆発的に売れることはあっても、ニーズが下がればたちまち売れにくくなる傾向がみられます。
別商品などの開発に取り組むなど、流行が覚める前に対策を講じておかなければ売上は低迷します。
周囲の環境変化による影響
会社が販売する商品やサービスは変化していなくても、たとえばそれらを販売する店舗の周囲環境が変化することで売上が減少・低迷する原因になります。
静かな場所にある飲食店として知られていたのに、近隣に商業施設ができたため、車の通りが増えて落ち着けない店になったなどが挙げられます。
新たな道が通ったため、店前の道を人の通行が少なくなったケースや、バスや電車など公共交通機関の本数減少で来店回数が減った場合なども該当します。
環境変化には常にアンテナを張り、情報収集と早期対策の検討が必要です。
同業他社の業績向上による影響
自社と同じ業界で似た商品を取り扱う他社の業績アップは、自社の売上に影響を与えます。
競合他社やライバル会社の商品のニーズが高まり、自社の顧客が他社に移ってしまえば売上は減少・低迷します。
同業他社の新商品リリースやキャンペーン開催の情報などは、常に入手し確認できる体制をつくっておくことが大切です。
ライバル会社となるケースはいろいろあるため、同じ商品やサービスを扱う会社の情報だけでなく、全体の状況などを確認しつつ売上減少・低迷の原因を探りましょう。
商品・サービスのイメージが悪化している
売上が減少・低迷してしまう原因として、商品・サービスのイメージが悪くなっているケースもあります。
SNSの利用者が多いため、ユーザーの1人が商品やサービスに関して不満を抱いたとき、その内容が口コミとして広がると考えられます。
取り扱う商品に関するネガティブ情報が拡大すれば、業界全体のイメージが低迷するため、売上を引き上げるまで時間がかかります。
自社商品や業界のイメージが悪化することが起こっていないか、常に新たな情報を収集し確認することが大切です。
ホームページやSNSのアクセス数が減少している
集客の方法を主にインターネットで行っていた場合、自社のホームページやSNSに対するアクセス数が減っていれば、売上減少・低迷につながる恐れがあります。
ホームページ開設に関しては、GoogleやYahooの検索順位でアクセス数は大きく左右されます。
検索順位が上がればアクセス数も増えるものの、順位が下がればアクセス数も減少します。
日本内で検索エンジンとしてのシェアを占めるサイトは、GoogleのAIにより順位が決められています。
ホームページの検索順位やSNSで多く検索されている事柄などを常に確認し、それが集客の低下につながっていないか確認しましょう。
売上を低迷させる内的要因

売上を減少させてしまう内的要因には、事業内容が影響しています。
事業が停滞する変化はなかったか、社内の環境や戦略など現状を把握することが必要ですが、売上を低迷させる内的要因には主に次の6つが考えられます。
- 新規顧客の減少
- 既存顧客のリピート率減少
- 既存の顧客離れ
- 客単価低下の影響
- 商品・サービスの質の低下
- 従業員の質の低下
それぞれ説明します。
新規顧客の減少
既存の顧客ばかりにとらわれ、新規顧客を開拓していなければ売上は上がることはありません。
当然、既存顧客を引き続き大切にすることも大切ですが、リピーターを得ることができる仕組みでないビジネスは新たな顧客の獲得はできないといえます。
常に新たな顧客を取り入れることができるように、既存顧客にのみとらわれることのない仕組みや工夫を検討するべきです。
既存顧客のリピート率減少
既存の顧客のリピート率が減少することも売上が低迷する原因になるでしょう。
安い商品は売れているのに、値段が高めの商品はまったく売れてないときや、リピート客が減少しているときなどは注意が必要です。
競合他社の存在を気にして自社商品の値下げで対抗しようとした場合、このようなケースに陥りやすくなります。
値下げし過ぎれば、商品やサービスは売れていても、利益を出すことができません。
顧客数に変化がない場合でも、購入回数が減れば売上は下がります。
リピーターの購入回数なども確認し、減っている場合には対策を検討したほうがよいでしょう。
既存の顧客離れ
売上が減少・低迷する原因として、既存顧客が離脱していることも関係します。
他社商品に切り替えたときや、必要なくなってことを理由に、既存の顧客が自社商品やサービスを購入しなくなってしまうケースです。
一度獲得した顧客が離れてしまうことは大きな痛手と考え、継続して購入・利用してもらえる仕組みや工夫を考えましょう。
客単価低下の影響
顧客の数は変わっていない場合でも、客単価が下がれば売上は減少してしまいます。
値段が高めの商品から安い商品へと購入を切り替えていないか、購入する量などは減っていないか確認しましょう。
売上を回復させることを目的に値下げしたときにも客単価は下がるため、いずれにしても対策の見直しが必要です。
商品・サービスの質の低下
販売する商品・サービスの質が低下すれば、購入する顧客も不満を抱き、売上は減少します。
売上が減少しているため、少しでも利益を上げようと、これまで使っていた製品より質は落ちるけれど価格が安い製品に切り替えたとします。
提供するサービスや商品の質も下がった場合は、継続購入していた顧客が従来と同じ金額を払っても、同じレベルの満足感を得ることはできません。
初めて自社商品・サービスを購入する顧客も、他社のほうがよい商品・サービスだったと不満を感じ、購入しない可能性があります。
仕入れた材料の質や、従業員レベルが低下している場合も商品やサービスの質は落ちます。
顧客へのアンケートなどで声を拾い、評価を確認する仕組みを作りましょう。
従業員の質の低下
従業員の質が低下していれば、1人頭の売上が減少することとなり、会社全体の売上低迷につながります。
受注する仕事の量が減少するだけでなく、値切られてしまい、本来の金額で販売することは難しくなるでしょう。
従業員に対する教育を徹底し、同業他社がより良い商品やサービスを作り提供していたとしても、人と人とのつながりで売上を低迷させない仕組みをつくることが必要です。
売上低迷の原因を知るための枠組み(フレームワーク)

売上が減少したり低迷したりしたときは、まず何が原因なのか明確にし、原因に合う対策を立てて実行することが必要です。
そして対策を講じた後も、本当にその改善方法でよいのか分析や改善を繰り返しましょう。
まずは売上減少や売上低迷の原因を洗い出し追及することが必要ですが、その際に用いるのが次の2つの枠組み(フレームワーク)です。
- ロジックツリー
- PEST分析
それぞれ説明します。
ロジックツリー
「ロジックツリー」とは、現状に対する「Why(なぜ)」という質問を繰り返すことにより、、問題の根本となる原因を探るフレームワークです。
売上が低下しているときには、その理由を洗い出していきます。
仮に質の低下が原因であれば、なぜ質が低下したのかまで掘り下げて考えることが必要です。
原因を掘り下げることで根本的な原因にたどりつき、何を解決しなければならないか知ることができます。
根本原因を確認し、その原因に対する「How(どうやって)」を繰り返して追及し、解決手段を探ります。
売上低迷の原因が仕入れている材料の質の低下にあったときには、その材料の質をどのように戻すのか、その解決策を探ることが必要です。
ロジックツリーでは、以下を何度も繰り返します。
- Why(なぜ)
- How(どうやって)
汎用性が高く社内にも導入しやすいフレームワークです。
PEST分析
「PEST分析」とは、問題の外部要因を分析・整理するフレームワークであり、次の4つの頭文字を省略した名称の分析方法です。
- Politics(政治)
- Economy(経済)
- Society(社会)
- Technology(技術)
会社の売上が低下・低迷したときにはこの4つそれぞれの要因も調査しましょう。
売上低迷の対策
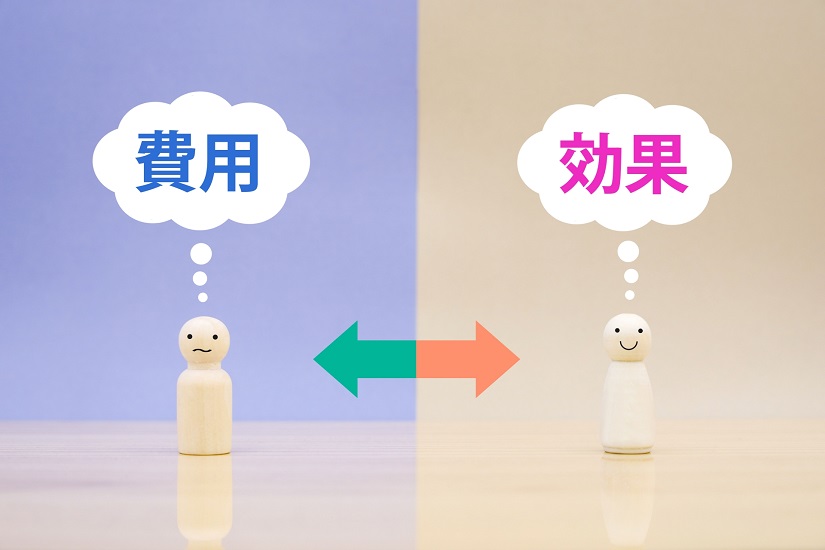
売上低迷の原因を枠組み(フレームワーク)で確認できたら、以下の対策を実践しましょう。
- 原因を分析する
- 資金ショート回避に向けて経費を見直す
- 新規顧客獲得に向けて集客率を向上させる
- 既存顧客掘り出しとリピート率を向上させる
- 客単価を上げる
- 商品・サービスの質を上げていく
- 従業員のモチベーションを向上させる
それぞれ説明します。
原因を分析する
売上が減少・低迷したときには、原因を分析することが必要です。
原因を分析せずに、たとえばネットやセミナーで得た売上回復のための知識やノウハウを実践したとしても、売上を回復させることはできません。
仮に何らかの対策を講じたとしても、その内容が自社の売上が低迷している原因に合った内容でなければ、さらに売上を低迷させる可能性もあります。
資金ショート回避に向けて経費を見直す
売上が減少・低下したときには、資金をショートさせないように経費を見直しましょう。
売上が減少しているのに支払う経費も同じである場合、これまでは黒字だった場合でも大きな赤字となります。
赤字でも手元に十分な資金があれば、経費の支払いに困ることはありません。
しかし手元に資金がなければ、近いうちにショートし、会社を倒産させる恐れがあります。
経費削減や赤字を減少させることを心掛け、無駄な経費を削減しましょう。
新規顧客獲得に向けて集客率を向上させる
売上の減少・低迷の原因に、新規顧客が獲得できていないことが含まれているのなら、新しく顧客を獲得できる仕組みをつくることが必要です。
新規顧客獲得に向けた方法として、以下が挙げられます。
- 新聞・雑誌・テレビなど既存メディアに広告を出す
- インターネット広告を活用する
- ポスティングによりチラシをまく
- ホームページのSEO対策を行う
- SNSを使ったプロモーションを実施する
自社に合った広告などの活用で、しっかり新規顧客を獲得できる方法を実践しましょう。
既存顧客掘り出しとリピート率を向上させる
既存の顧客の中には、ここ最近は購入履歴のない方なども含みます。
その場合、そのようなリピートの少ない顧客の掘り出しやリピート率向上を図る工夫をすることで、売上回復を図れます。
購入頻度が減少している顧客などに、再度、自社の商品やサービスを思い出してもらえるように、次の方法を検討しましょう。
- 手紙やメールなどを使って商品・サービスをアピールする
- 既存顧客向けのイベントなどを開催し招待する
- パンフレットや無料サンプルなどを送付し試してもらう
積極的に顧客フォローを行うことも、顧客離れを防ぐ一歩となり、継続して購入し続けてもらえます。
客単価を上げる
客単価が下がれば当然、売上も低下・低迷することとなりますが、回復させる方法として検討できるのは以下のとおりです。
- 商品・サービスそのものの価格を上げる
- 商品(サービス)に関連する別商品(別サービス)をセット販売し購入を促す
- 高額商品やセット購入の案内を行う
- 高額商品の体験ができるサービスや機会を提供する
客単価を上げれば顧客数を増やさず売上を伸ばすことができます。
商品・サービスの質を上げていく
商品・サービスの質が低下していれば、既存の顧客は離れ、新規顧客は獲得しにくくなります。
そのため販売している商品やサービスの質を改善するにようにし、顧客満足度をアップさせましょう。
顧客満足度が上がれば、高額な商品を購入しようと考えてもらいやすくなり、客単価もアップさせられます。
他社が販売する商品やサービスに劣らない質の商品・サービス提供に向けて、売上低迷の原因である質改善の開発を進めることが必要です。
従業員のモチベーションを向上させる
低迷した売上を回復させるには、社員や従業員のモチベーションを上げることも必要です。
どれほど有効な対策を立てたとしても、実際にその対策を現場で実行するのは社員や従業員といえます。
そのため社員や従業員のモチベーションが低ければ、対策により想定していた改善が見られなくなります。
経営者だけでなく、現場の従業員とも、低迷した売上を回復させるように一致団結して取り組む姿勢が必要です。
人材不足による売上低迷の対策

需要低迷や大型店舗進出などの影響もあり、売上が低迷しているケースもめずらしくありません。
人手不足の中、限られた資金力と人材で現場をまわす場合、次の対策で営業活動を効率化させましょう。
- ノウハウをマニュアル化する
- 無駄な活動はなくす
- 内勤の時間を抑え外勤の時間を増やす
- 顧客に優秀な営業担当者をつける
- 営業の効率化を図る
それぞれ説明します。
ノウハウをマニュアル化する
商品やサービスの販売に直接かかわることとなる営業担当者が優秀であれば、売上は向上しやすくなります。
しかし同じ商品やサービスを販売する場合でも、営業担当者によって売れる場合と売れない場合があるのは、担当者の営業能力が関係します。
そこで、優秀な営業担当者の行動をお手本に、行動パターンや商談におけるノウハウなどをマニュアル化してみましょう。
マニュアル化するときには、以下の2つに分けて作成します。
- 営業アプローチ
- クロージングまでの営業プロセス
それにより、プロセスごとに改善する意識を持つことができます。
無駄な活動はなくす
売上を思うように伸ばすことできない営業担当者の以下を分析しましょう。
- 1日の行動
- 週間行動
行動を分析することによって、本来の営業活動に関係のない行動が多いことに気がつくこともあります。
さらに営業能力の高い優秀な営業担当者と、平均的な営業担当者の行動パターンを比較することで、より優秀な営業担当者の特性などを見ることもできます。
秀な営業担当者の場合、無駄な行動が省かれていることがほとんどです。
優秀な営業担当者の行動を参考に、他の営業担当者の無駄な行動をなくすことへつなげるようにしてください。
内勤の時間を抑え外勤の時間を増やす
売上・業績を改善させていくために、以下の方法で顧客との商談時間を最大にすることが必要です。
- 内勤業務を減らし外勤時間を増やす(営業担当者以外が対応できる見積書作成・DM送付・事務処理などは内勤社員や事務担当者が行う)
- 顧客分担を見直しす(成績のよい営業担当者は将来性の高い顧客の対応を行う)
- 直行・直帰制導入で移動時間を減少させる(移動時間の減少により営業活動時間を増加させる)
- 提案書や見積書作成など商談準備業務は標準化させる
内勤や事務を担当する社員なども協力し、営業担当者をサポートすることが必要といえます。
顧客に優秀な営業担当者をつける
成長性の高い顧客に重点を置いた営業活動で、効率的に売上を拡大させることもできます。
そのため、将来的に拡販できる顧客か、売上規模の大きさなどを参考にしつつ、重点に置いたほうがよい顧客を見極めましょう。
将来性が高く見込める顧客には、訪問頻度・販売促進・価格など優遇しつつ、優秀な営業担当者をつけるなど効率的な営業活動を目指すことが必要です。
営業の効率化を図る
- 顧客・キーパーソンの情報
- 進行中の商談の進捗状況
- 頻繁に活用する提案書や見積書の雛形
- 過去の相談の成功事例・失敗事例
上記の情報をデータベース化し、共有して営業の効率化を図りましょう。
売上低迷時にやってはいけないこと

売上が減少・低迷したときに絶対にやってはいけないこととして、特に何の分析なども行わずに改善へ行動してしまうことが挙げられます。
何が原因かわからずに行動してしまうケースとして多いのは、たとえば商品やサービスの価格をひとまず値下げすることです。
値下げにより一時的に売上が回復することもあるため、対策として問題なかったと考える経営者も少なくありません。
しかし実際には、利益率が低下しており状況を改善させることはできていないといえます。
低い利益率のままでは、労働時間を増やすこととなり、原価の高騰などがあれば一気に赤字転落します。
一度値下げした状態から値上げすることは簡単なことではないため、まずは原因を分析し、何をするべきか考えた上で改善させていくことが必要です。
まとめ
売上が低迷してしまったときには、その原因をまずは追究することが必要です。
売上低下の原因を発見するための2つの枠組み(フレームワーク)を活用し、どれほど細かく分析できるかによって、最善といえる対策につながるかが決まります。
現状を把握することと、売上が低下・低迷していることの原因追及は必ず行ってください。
中小企業経営者向け!