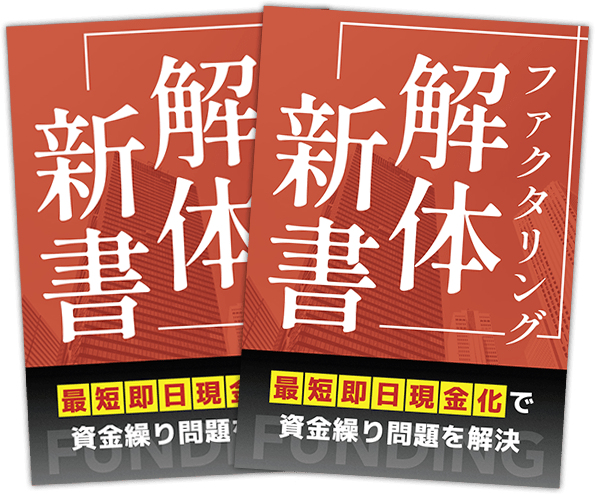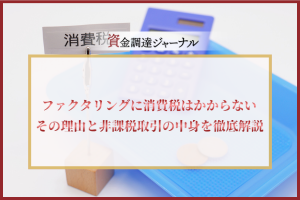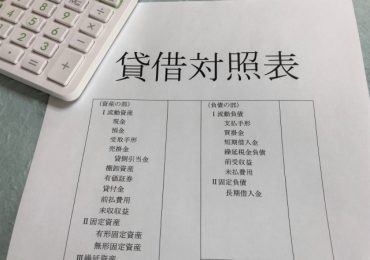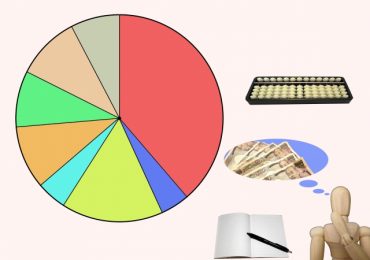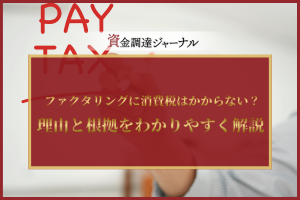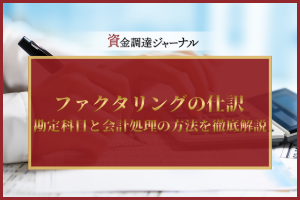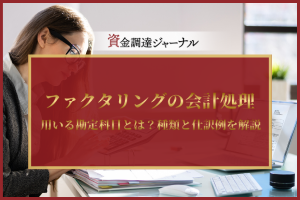ファクタリングを利用した場合、不安に感じるのは経理処理の方法です。
売掛先が倒産しても、現金化した売掛金の弁済義務を負うことのないノンリコース契約のファクタリングは、融資に該当するリコース契約と経理処理の方法が異なります。
そこで、ファクタリングを利用したときの経理処理について、仕訳の作成方法など紹介します。
中小企業経営者向け!
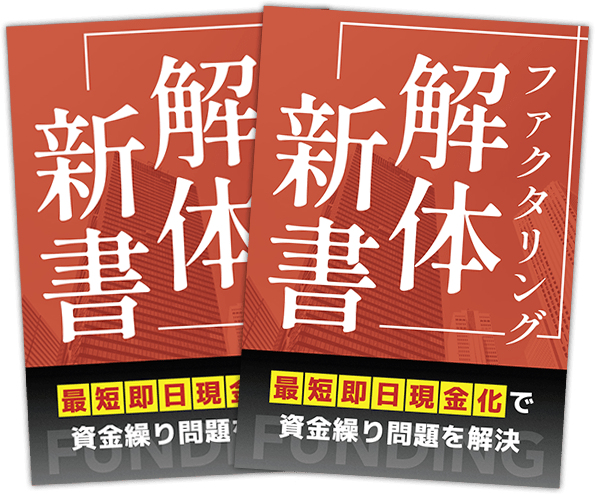
ファクタリング利用の経理処理
仕訳とは、発生した取引をそれぞれの勘定科目に分類する経理処理のことです。
通常、企業間の商取引で売掛債権が発生したときには、以下の仕訳を作成します。
| 借方 | 貸方 |
| 売掛金 | 売上 |
その後、売掛先から売掛代金が期日に入金されたときは、以下の経理処理が必要です。
| 借方 | 貸方 |
| 現金(または預金) | 売掛金 |
ただし先にファクタリングで売掛金を現金化するときは、以下の経理処理を行います。
| 借方 | 貸方 |
| 未収入金 | 売掛金 |
その後、ファクタリング会社から売掛金の売却代金の入金があったときには、以下の仕訳で経理処理を行いましょう。
| 借方 | 貸方 |
| 現金(または預金) | 未収入金 |
| 売掛債権売却損 |
売掛債権売却損という勘定科目は、ファクタリング会社に支払う売買手数料のことです。
ファクタリングを利用する場合、売買手数料を差し引いた残りを、売却代金として受け取ります。
資金繰りのお悩みを解決!まずは相談してみる
ファクタリングと消費税の関係
ファクタリングの利用に関係なく、売掛債権は売上高に含まれるため、消費税の対象です。
消費税の申告の際には、商品販売により顧客から受け取った消費税額から、仕入れなどで支払った消費税を控除し、納める消費税を計算します。
この処理を仕入税額控除といいますが、課税対象期間中の課税売上高が5億円以下であり、課税売上割合が95%以上ある場合には全額控除となります。
課税売上割合は、以下の計算式で算出します。
| 課税売上割合 = 課税期間中の課税売上(税抜) ÷ 課税期間中の総売上(税抜) × 100 |
総売上部分には、預金や売掛金、貸付金など、その他金銭債権も加算することが必要です。
ファクタリングにより得た対価も、本来なら金銭債権と考えられます。
ただし例外規定により、ファクタリングで得た対価は加算しなくてもよいとされています。
課税売上割合にファクタリング取引は考慮しなくてもよいと理解しておきましょう。
中小企業経営者向け!