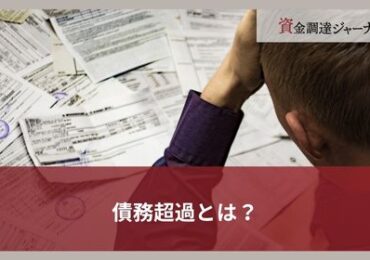運転資金を計算しておくことは、事業継続において重要なことです。
資金がショートしてしまうと、たとえ赤字であっても会社は倒産するからといえます。
また、運転資金を計算すれば、事業運営や財務状況の課題や正常なキャッシュフローなどの分析もできます。
そこで、運転資金の計算方法や、必要資金の目安や調達方法をわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

運転資金の種類

「運転資金」とは、事業継続・運営のために必要な資金です。
事業運営で必要となるお金は、設備資金と運転資金に分けることができますが、このうち運転資金は用途によって主に5つに細分化できます。
- 経常運転資金
- 増加運転資金
- 減少運転資金
- 季節性運転資金
- その他運転資金
それぞれ説明します。
経常運転資金
「経常運転資金」とは、事業運営において常に必要となる資金です。
多くの事業で最も必要性の高い運転資金であり、一般的な「運転資金」はこの「経常運転資金」を意味します。
経常運転資金の内訳は、以下のとおりです。
- 事務所の家賃
- 仕入れ代金
- 従業員に対する給与
- 広告宣伝費
増加運転資金
「増加運転資金」とは、事業拡大に沿って増加した売上に対し、必要となる運転資金です。
売上が増えれば新規取引先の開拓や販売数の増加などで、仕入れや従業員を増やすことが必要となるため、資金も必要になります。
設備投資や仕入れに充てる資金は、会社や事業が成長するに伴い増えます。
十分に資金を用意できなければ、たとえ黒字でも「黒字倒産」するリスクを高めます。
訪れたビジネスチャンスを逃すことのないようにシミュレーションを行い、支出拡大に耐えられる資金を確保することが必要です。
減少運転資金
「減少運転資金」とは、売上が減少しても毎月発生する固定費の支払いに充てる運転資金です。
事務所の家賃や従業員の給与などは、たとえ売上が減少しても支払い続けることが必要になります。
手元の資金が足りていなければ、減少運転資金を調達し、補うことが必要になるでしょう。
季節性運転資金
「季節運転資金」とは、特定の時期や季節で必要となる運転資金です。
日頃は必要ではない運転資金であり、たとえば以下のタイミングでは通常よりも多い運転資金の準備が必要になります。
- 賞与月(従業員に対してボーナスを支給するなど)
- 季節により売上が低下する月(季節商品やビジネスパーソン向けサービスの大型連休による利用率低下など)
- クリスマスや正月などイベント月(イベント商品取り扱いによる直前の大量仕入れなど)
その他運転資金
「その他運転資金」とは、たとえば取引がスムーズに進まず一時的に資金が不足した場合、追加で必要になる運転資金です。
他にも取引先の都合で売掛金の入金が遅れてしまい、現金化できない売掛債権が増えた場合なども、追加で運転資金が必要になります。
反対に仕入れ代金の支払サイトが短くなったときや、掛け取引から現金決済に変更された場合なども同様です。
状況が改善されるまで、追加で運転資金を調達し補う必要があるといえます。
運転資金の内訳

運転資金には上記のように複数の種類がありますが、どの運転資金においても充てる用途は次の2つに分けられます。
- 変動費
- 固定費
軽費を変動費と固定費に分けることで、利益を予測し「損益分岐点」を把握できます。
損益分岐点とは、「売上高-変動費=限界利益」=「固定費」となるタイミングです。
赤字と黒字の境目であり、プラマイゼロになる分岐点のため、損失を出さないためには損益分岐点の把握が必要といえます。
変動費と固定費について、それぞれ説明します。
変動費
「変動費」とは、売上増減により変動する費用です。
事業運営で必要な経費のうち、売上・生産・販売などに比例して増減する費用といえます。
売上が伸びるほど必要な資金は増えていきますが、たとえば次のような費用が変動費に含まれます。
- 原材料費
- 仕入原価
- 外注費
- 派遣・契約社員の給与
- 販売手数料
- 運搬代
利益が上がることで、より売上を増やそうと製造や仕入れに費用がかかり、変動費に充てるお金が必要です。
固定費
「固定費」とは、売上の増減に関係なく、一定でかかる費用です。
事業運営において、たとえ売上がゼロであっても発生する経費といえます。
たとえば次の費用が固定費に含まれます。
- 事務所の家賃
- 従業員の給与
- 光熱費
- リース料
多少の変動はあっても支払う額は売上に左右されないため、毎月一定の金額を固定費として負担することになります。
運転資金の計算方法

手元の資金を枯渇させないためにも、必要な運転資金を計算し把握しておくことが必要です。
運転資金の計算方法は、主に次の2つの方法を用います。
- 在高方式
- 回転期間方式
それぞれ説明します。
在高方式
「在高方式」の「在高」とは、手元の資産やお金の総量であり、資産や負債から計算する方式です。
運転資金を在高方式で算出するときには、次の計算式を用います。
|
運転資金 = 売掛債権(売掛金+受取手形) + 棚卸資産 - 買掛債務(買掛金+支払手形)
|
売掛債権や棚卸資産は、まだ現金化されていないもののこれからお金になる予定の資産です。
これに対し、まだ支払いを終えていない債務が買掛債務といえます。
現金化される金額から支払い予定の金額を差し引くことで、必要な運転資金を算出できます。
売上が計上されても、すぐに代金が入金されるわけではなく、一時的なタイムラグが発生します。
このタイムラグで発生する支払いに充てるつなぎ資金として運転資金が必要となりますが、計算式で用いる項目については以下のとおりです。
- 売掛債権
- 棚卸資産
- 買掛債務
それぞれ説明します。
売掛債権
「売掛債権」とは、商品を販売し売上計上したものの、まだ入金されていない未回収の債権です。
掛け取引で商品を売り、取引先に請求書を渡しているものの、入金期日が未到来となっている間に発生する「売掛金」は売掛債権に含まれます。
また、代金の支払いとして「為替手形」や「約束手形」を受け取り、設定された支払期日を迎えていない「受取手形」も売掛債権の1つです。
棚卸資産
「棚卸資産」は、販売や消費目的で仕入れた商品が、まだ社内にとどまり在庫として保管されている資産です。
商品・製品以外にも、原材料や製造途中の仕掛品も棚卸資産に含まれます。
まだ販売されていない状態ではあるものの、販売後は売上として計上されることが予定されているため、資産として扱われます。
買掛債務
「買掛債務」は、商品の仕入れや材料購入にかかった代金をまだ支払っていない状態の債務です。
掛け取引により、取引先から請求書を受け取っているものの、支払い期日が到来していないため未払いの「買掛金」は買掛債務に含まれます。
また、支払い代金を手形の振り出しにより行った場合の「支払手形」も、買掛債務の1つです。
回転期間方式
「回転期間方式」とは、どのくらいのお金が何日間で必要なのか算出するための方式です。
運転資金は入金と出金の間で発生するタイムラグを埋めるお金ですが、次の計算式で算出できます。
|
運転資金 = 平均月商 × (売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-買入債務回転期間)
|
回転期間方式により、タイムラグがどのくらい発生するのか計算することができ、正確な運転資金を算出できます。
計算式に用いる項目は主に次の4つです。
- 平均月商
- 売上債権回転期間
- 棚卸資産回転期間
- 買入債務回転期間
それぞれ説明します。
平均月商
「平均月商」とは、1か月平均の売上高のことであり、以下の計算式で算出できます。
|
平均月商 = 年商(売上高) ÷ 12か月
|
季節性の変動が売上に発生する業種の場合、月単位の売上でバラツキがみられることを考慮することが必要です。
月商を算出し指標として用いることで、在庫や借入れの適性を計り、財務を分析できます。
売上債権回転期間
「売上債権回転期間」とは、掛け取引により商品販売後、代金を回収するまでの期間です。
売掛債権を1日あたりの平均売上で割って計算しますが、次の計算式で算出できます。
|
売上債権回転期間 = (売掛金+受取手形) ÷ (年間売上高÷12か月)
|
売上債権回転期間を計算することにより、未入金となっている売上が何日分あるか確認できます。
数値が小さければ売掛金を順調に回収できている健全経営と判断できるのに対し、大きな数値をあらわすときには回収までの期間の見直しが必要です。
棚卸資産回転期間
「棚卸資産回転期間」とは、在庫として保管している商品や材料を販売し、売り切れるまでの期間です。
棚卸資産を1日あたりの平均売上原価で割って計算しますが、次の計算式で算出できます。
|
棚卸資産回転期間 = 棚卸資産 ÷ (年間売上原価÷12か月)
|
保管している在庫が、売上に対し何日でなくなるか計算することができます。
数値が小さい場合には、順調に在庫を販売できていると判断されるのに対し、数値が大きい場合は不良在庫が増えているため処分の必要性が問われます。
買入債務回転期間
「買入債務回転期間」とは、掛け取引により商品や材料を仕入れてから、その代金を支払うまでの期間です。
買掛債務を1日あたりの平均売上原価で割って計算しますが、次の計算式で算出できます。
|
買入債務回転期間 = (買掛金+支払手形+受取手形の譲渡高) ÷ (年間売上原価÷12か月)
|
いずれ支払う必要のある代金が、どのくらいの期間未払い状態であるか確認することが可能です。
数値が大きいときは、支払いを先延ばしできているため、無理が生じにくく好ましい状態といえます。
小さい数値のときは、支払サイトの見直しなどが必要です。
必要な運転資金の目安

資金が枯渇しないように、必要な運転資金を計算し把握することが必要ですが、目安になる金額は次の3つを押さえた上で検討しましょう。
- 月商3~6か月分が目安
- 入金の少ない期間に注意する
- 支出のタイミングを把握しておく
それぞれ説明します。
月商3~6か月分が目安
必要な運転資金の一般的な目安は、月商3~6か月分ほどといわれています。
たとえば日本政策金融公庫から運転資金を借りるときも、月商3か月分までが融資可能額の目安とされています。
業種などによって異なるものの、3か月程度は最低でも目安としたほうが安心です。
資金力が強い会社なら1~2か月分の運転資金でも着実に事業運営を継続できるでしょう。
しかし急な出費や突然訪れたビジネスチャンスに対応するためには、資金ショートを防ぐためにも6か月分は確保しておきたいと考えられます。
仮に6か月分の蓄えがあった場合、経営危機に陥ってもその対応に半年ほど時間をかけられるため、経営の立て直しも期待できます。
入金の少ない期間に注意する
必要な運転資金を確保する上で、特に入金が少ない期間には注意しましょう。
仕入れに対する支払いは、売上による入金よりも先に発生します。
そのため入金よりも出金のほうが多い月などが生じると考えられますが、この期間こそが経営危機に陥るときです。
運転資金が著しく減少している入金の少ない期間に、何らかのトラブルなどが発生すれば対処できなくなります。
万一不測の事態が起きても対応できるように、入金の少ない時期を把握し、より多く資金を確保しておきましょう。
支出のタイミングを把握しておく
必要な運転資金を確保する際には、支出のタイミングを把握しておきましょう。
いつ、どのくらいの金額を支払わなければならないのか、正確に把握しておくことが重要です。
月単位での把握ではなく、日付まで確認できていれば、わずかな資金調達のズレで資金ショートを防げます。
たった1日の支払いや入金のズレが会社の存続を決める場合もあるため、資金を必要とする日時や金額などは正確に把握しておくことが必要です。
資金繰り安定化につなげるポイント

運転資金を計算し、確保しておくことは事業運営において欠かせません。
慌てて資金調達に頭を悩ませることなく、安定した資金繰りを実現することで、運転資金の確保にも余裕が生まれます。
そこで、資金繰り安定化につなげるポイントとして次の4つを押さえつつ、事業を運営しましょう。
- 支払サイトを長くする
- 売上債権回転期間を短縮する
- キャッシュフロー把握を徹底する
- 不良在庫を処分する
それぞれ説明します。
支払サイトを長くする
資金繰りの安定化のためには、支払サイトはできるだけ長く設定しましょう。
新規取引先との交渉で仕入れ代金の支払い日を決めるときは、できるだけ先に延ばしにしたほうが売上代金の入金分で支払いやすくなります。
交渉においては、取引する数量・単価・頻度など、取引先が納得できる代替え案を提案することも必要です。
売上債権回転期間を短縮する
資金繰りの安定化のためには、売上債権回転期間を短縮しましょう。
売上債権回転期間が長期化すれば、売掛金の回収に時間がかかるため資金繰りを悪化させます。
利益が出ていても黒字倒産するリスクが高くなるため、売掛金回収が遅延していないか、取引先から支払いの先延ばしを依頼されていないか確認してください。
また、売掛金を期日に着実に回収するためにも、新規や継続取引において与信管理が重要です。
取引先に倒産や不渡りを出す可能性が感じられる異変はないかなど情報を入手した上で、取引量や決済方法の見直しなども必要になります。
キャッシュフロー把握を徹底する
資金繰りの安定化のためには、キャッシュフロー把握を徹底することが必要です。
長期的なキャッシュフローを確認し、前期や前々期などと今期を比較しながら、売上や売掛金回収などの予測を立てていきます。
そのために資金繰り表を作成し、常に現金の流れや財務状況を知っておくことが必要です。
不良在庫を処分する
資金繰りの安定化のためには、不良在庫を処分しましょう。
棚卸資産回転期間が長期化し、在庫を多く抱えている場合、手元の現金が増えないため資金繰りは悪化します。
在庫として保管していれば、売上が増えたときや急な注文には対応しやすくなるでしょう。
しかし売れなかった場合、劣化や損耗で価値が低下し、売れ残りの不良在庫化する恐れもあります。
さらに在庫の保管や管理においては、倉庫や管理人材の費用もかかるため、余計なコストのみ発生します。
そのためにも不良な在庫は思い切って処分し、適切な量に調整することが大切です。
運転資金の調達方法
安定した資金繰りを実現できれば、慌てて資金調達することもなくなります。
ただ、手元の資金が足らなくなるタイミングにおいては、外部から運転資金を調達することも必要です。
また、機動的な事業拡大を検討しているときには、自己資金だけでは対応できず資金を調達することになるでしょう。
運転資金を調達する方法は、目的や資金使途によって異なるといえますが、主に次の5つが挙げられます。
- 政府系金融機関の融資
- 民間銀行の融資
- ビジネスローンの借入れ
- 補助金・助成金の申請
- ファクタリングの活用
それぞれ説明します。
政府系金融機関の融資
政府系金融機関である日本政策金融公庫は、国が100%出資している金融機関であり、中小企業などにも積極的に事業資金の貸し付けを行っています。
運転資金や設備資金など、用途に応じた事業資金の融資制度があり、小規模事業者や個人事業主も相談できます。
条件を満たすことで無担保・無保証人で融資を受けることができ、低金利で一定の据置期間を設けた上での借入れも可能です。
ただし必要書類の準備や審査に時間がかかるため、1~2か月は資金調達までかかると見込んでおくことが必要といえます。
民間銀行の融資
民間銀行の融資も、運転資金の調達の方法です。
都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合など種類はいろいろあり、中小企業などの場合には都市銀行以外の民間銀行に相談することになるでしょう。
一般の事業性融資の場合、金利は比較的低めに設定されますが、資金調達まで1~3か月程度はかかります。
不動産担保融資の場合、担保として不動産を差し入れるため、申込者だけでなく不動産の調査なども審査で行われます。
一括借入れと限度額設定のもの都度借入れる方法があり、担保の資産価値が高ければ1か月程度で資金調達できます。
ただし融資限度額は不動産の担保価値に依存するため、資産価値の高い不動産を所有していなければ、希望する額は調達できない場合もあります。
なお、銀行融資の流れについては、以下の記事を参考にしてください。
銀行融資の流れとは?申し込みや審査の必要書類などわかりやすく解説
ビジネスローンの借入れ
ビジネスローンは、一般的な銀行融資を受けにくい事業者にたいし、事業資金を貸し付けることを目的としてできた金融商品です。
銀行と消費者金融で取り扱いを行っており、消費者金融のビジネスローンであれば最短即日で資金調達できます。
銀行のビジネスローンでも1週間程度で審査が完了するため、スムーズな資金調達を希望するときには適しています。
ただし金利は高めに設定されるため、長期利用や繰り返し利用することは避け、一時的なつなぎ資金で利用する程度に留めておくことが必要です。
補助金・助成金の申請
国や地方自治体の補助金や助成金は、返済不要で多額の資金を調達できる方法です。
助成金は通年公募で、要件を満たすとほとんどが資金調達につながります。
しかし補助金は公募期間が限られており、要件を満たしても採択されなければ資金調達にはつながりません。
また、どちらも実際にかかった費用を後払いで受け取ることができる制度であるため、一時的な立て替えなどが必要です。
必要書類も詳細な資料を求められるため準備に時間がかかり、審査期間も制度によって異なるものの、3~6か月など長期に渡るといえます。
ファクタリングの活用
ファクタリングは、保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、現金化することで資金調達できるサービスです。
取引先に商品やサービスを販売した代金が入金されるまで、期間が空きすぎてしまうと支払いに充てるお金が不足し、資金繰りが悪化します。
このような場合、まだ回収していない売掛金をファクタリング会社に売却することで、入金される予定を前倒しして運転資金を確保できます。
また、ファクタリングを利用した後で売掛金が回収不能になった場合でも、利用者が責任を負うことはありません。
ただし売買手数料が割高になることを踏まえ、ビジネスローン同様に長期利用は避け、いつまで利用するか決めておくことが必要といえます。
なお、ファクタリングの仕組みに関しては、以下の記事を参考にしてください。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく図で解説
まとめ
運転資金を計算し、事前にどのくらいのお金がいつ必要なのか、把握しておくことは事業運営において欠かせないことです。
手元の資金が枯渇すれば、たとえ利益がでていたとしても会社は倒産します。
このような黒字倒産を防ぐためにも、毎月の現金の流出入を把握しておき、資金不足に陥らない健全経営を目指しましょう。
中小企業経営者向け!