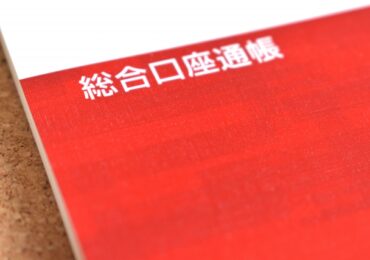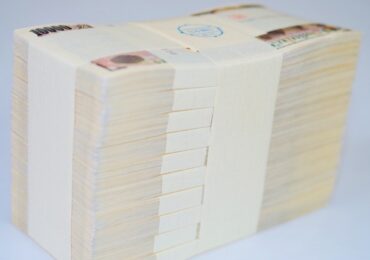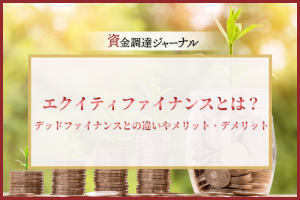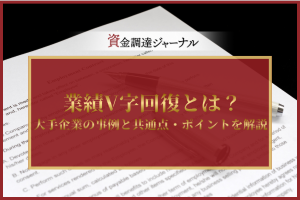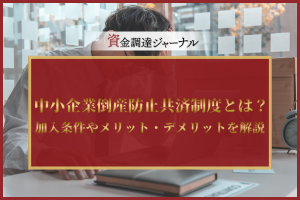会社設立時には、資金調達が欠かせません。
手元に資金がなければ、会社を設立したくても手続できず、事業運営に必要な設備を揃えることも仕入れもできなくなります。
会社設立に必要なお金をすべて自己資金で賄えないなら、外部から資金調達することが必要です。
そこで、会社設立など創業時に活用できる資金調達の方法と、それぞれの種類のメリット・デメリットを紹介します。
中小企業経営者向け!

会社設立時の資金調達の種類

会社設立時に資金調達する場合、次の2つの種類からそれぞれの方法を検討することになります。
- 自己資本を増やす
- 他人資本を増やす
それぞれ説明します。
自己資本を増やす
「自己資本」とは、会社設立後に事業に使用する資金のもととなる返済義務のないお金です。
返済義務を負わず自由に使えるお金であるため、自己資本を増やすことは安定した経営につながります。
貸借対照表の右半分は「負債」と「純資産」で構成されますが、負債は「他人資本」、純資産を「自己資本」と呼びます。
負債と純資産を合わせたものが「総資本」であり、会社経営に必要な資金源となる部分です。
会社設立時において、自己資本を増やす資金調達の方法は主に次の3つです。
- 自己資金
- 出資
- 公的援助
それぞれ説明します。
自己資金
「自己資金」とは、会社設立に向けて経営者本人が貯めたお金です。
たとえばサラリーマンとして会社勤務している期間中に、コツコツと資金を貯めておけば、誰を頼ることもなく自らの資金のみで会社を設立できます。
仮に会社設立後に失敗した場合でも、誰に迷惑をかけることもなく、返済義務に追われることもなく立ち直りやすいといえます。
しかしサラリーマン時代に貯めることのできる資金は限られていることが多いため、自己資金で賄うことができなければ他の方法も検討が必要です。
出資
「出資」とは、発行した株式を投資家に購入してもらい、返済義務のない資金を調達する方法です。
お金を借りるわけではないため、返す必要のないお金を自由に使えることがメリットである一方、発行株式の保有割合によっては経営権を脅かされます。
また、出資者が物言う株主となることで、経営に口を出される可能性もあることも踏まえた上での選択が必要です。
公的援助
「公的援助」とは、国や自治体などの「補助金」や「助成金」です。
返済する必要のないお金を支給してもらえるため、資金繰り不安を解消しやすい方法といえます。
ただ、申請要件を満たすことが必要であることと、基本、後払いとなるため立て替えるだけの資金を別途準備しておくことが必要です。
他人資本で増やす
「他人資本」とは、調達した資本のうち、株主以外から調達した外部資本のことです。
自己資本は返済義務のない資金であるのに対し、他人資本は「負債」であるため、返済義務を負います。
貸借対照表で他人資本の負債が占める割合が増えすぎると、返済負担が重くなり資金繰りが悪化するリスクが高まるため、注意が必要です。
他人資本には、借入金・買掛金・未払金・支払手形などいくつか種類があり、会社設立時では「借入」により負債を増やして資金を調達することになります。
借入
会社設立時に他人資本を増やす場合、銀行などの金融機関からお金を借入れることが検討されます。
民間銀行から融資を受ける方法以外にも、政府系金融機関の日本政策金融公庫や、自治体などの制度融資など候補先は多岐に渡ります。
どの調達先から資金を調達した場合でも、設定された金利に応じた「利子」が発生します。
借金が増えすぎれば安定経営を失われ、信用力を低下させると留意しておくことも必要です。
会社設立時の資金調達方法10選

会社設立時は、実績などもない状況の中で資金を調達することになるため、その方法も限られます。
ただ、たとえ会社設立時であっても、資金調達の方法は多岐に渡るため、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で選ぶことが必要です。
考えられる会社設立時の資金調達は、主に次の10個といえます。
- 自己資金
- 個人からの借入れ
- 日本政策金融公庫の融資
- 民間銀行の融資
- 制度融資
- ベンチャーキャピタル
- エンジェル投資家
- クラウドファンディング
- ファクタリング
- 補助金・助成金
それぞれの方法を説明します。
①自己資金
会社設立時の資金調達方法1つ目は「自己資金」の準備です。
独立・開業に向けて、会社勤務している期間や個人事業主として働いている間に、「自己資金」を貯めて準備しておくと、資金調達に悩むことはありません。
実績のない状況で銀行がお金を貸してくれるとは限らないため、会社設立を目指すのなら自己資金を貯めておくことが理想です。
目指す事業によっては資金が不足すると考えられるため、その場合には他の資金調達方法と合わせた資金の準備が必要となります。
②個人からの借入れ
会社設立時の資金調達方法2つ目は「個人」からの借入れです。
親や親戚など、親しい間柄の方からお金を借りて資金調達する場合、返済計画を自由に決めやすいというメリットがあります。
また、利子などを求められることなく、書類準備など面倒な手続を経ず資金調達しやすいともいえます。
ただ、仮に快くお金を貸してもらえたとしても、会社設立後に計画通りの返済ができなければ、関係が悪化します。
親しい間柄であることで安心してしまい、つい返済が遅れがちになると、訴訟を起こされる恐れがあるため計画に沿った返済が必要です。
さらに個人からお金を借りる場合には、調達金額は少額になりやすいため、不足するときは他の資金調達方法と合わせた検討が必要となります。
③日本政策金融公庫の融資

会社設立時の資金調達方法3つ目は「日本政策金融公庫」の融資です。
日本政策金融公庫は「政府系金融機関」の1つであり、民間の金融機関の融資補完を目的とした運営を行っています。
そのため設立段階の会社でも積極的に相談に応じ、資金の貸し付けも行います。
ただしすぐに手元のお金が増えるわけではなく、準備書類が多岐に渡るなど申請準備に手間がかかるといったデメリットもあります。
④民間銀行の融資
会社設立時の資金調達方法4つ目は「民間銀行」の融資です。
資金調達の方法として、真っ先に思い浮かぶのが民間銀行から融資を受けることといえます。
民間銀行の融資のうち、「プロパー融資」は銀行独自の責任で事業資金を貸し付けています。
融資額に上限もなく、信用保証協会を通すわけではないため銀行のみの審査のみで保証料も不要です。
ただし万一返済されなかった場合の貸し倒れリスクは銀行が背負うことになるため、審査はかなり厳しく簡単には通りません。
会社設立前後の民間銀行からの融資は、不動産を担保とした不動産担保融資や、信用保証協会に保証してもらう保証付融資などを利用することになります。
⑤制度融資
会社設立時の資金調達方法5つ目は、地方自治体の「制度融資」です。
「制度融資」とは、中小企業など資金体力が十分でない企業支援を目的としてた制度で、自治体・金融機関・信用保証組合の3つが連携して行うことが特徴です。
創業前でも申し込みが可能であり、無担保・無保証で事業資金を借りることができるだけでなく、自治体によっては保証料や利子の一部を補助してもらえます。
融資額の上限や設定される金利は、利用する自治体や自己資金・事業計画などで異なるものの、一般的には上限3千万円程度で金利も2.1~2.7%です。
低金利・長期借入れが可能な方法ではあるものの、提出書類が多く審査にも一定の時間がかかります。
さらに信用保証協会を通すため、銀行だけでなく保証協会の審査にも通過することが必要であることや、保証料負担などのデメリットは留意が必要です。
⑥ベンチャーキャピタル
会社設立時の資金調達方法6つ目は「ベンチャーキャピタル」に出資してもらうことです。
「ベンチャーキャピタル」とは、まだ上場していないベンチャー企業など、新興企業に対して資金を投じる投資会社です。
新興企業の発行した株式を購入し、上場後に売ってキャピタルゲインを獲得することがベンチャーキャピタルの目的といえます。
ただし、将来的に有望で成長率が高いと判断されなければ出資してもらえず、資金投下に見合うリターンを求められます。
ベンチャーキャピタルの経営方針に従うことが必要であり、経営コンサルティングなども積極的に行われるため、自由な事業運営は難しくなります。
会社設立時の資金調達方法7つ目は、「エンジェル投資家」に出資してもらうことです。
「エンジェル投資家」とは、起業前や起業して間もないスタートアップ企業などに対し、資金面で支援してくれる個人投資家です。
もともと実業家や会社経営者がエンジェル投資家として活動していることも多いため、悩みなども理解した上で救いの手を差しのべてくれます。
ただし、純粋に若い起業家を応援する目的のエンジェル投資家もいれば、ベンチャーキャピタル同様に上場後の売却益を目的とした投資家もいるため見極めが重要です。
なお、エンジェル投資家に関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
エンジェル投資家とは?出資してもらうメリット・デメリットや探し方を解説
⑧クラウドファンディング

会社設立時の資金調達方法8つ目は、「クラウドファンディング」の利用です。
「クラウドファンディング」とは、インターネットにビジネスやアイデアを公開し、共感や賛同した不特定多数の個人から少額資金を集める仕組みです。
大きなリスクを負うことなく挑戦でき、事前にファン獲得つなげたりテストマーケティングに活用したりと、様々なメリットがあります。
ただし注意したいのは、インターネットにビジネスやアイデアを公開することになるため、盗用されるリスクがあることです。
さらにクラウドファンディングは、支援者が起案者に対しどのような形式で資金を提供し、リターンを得るかによって次の6つの型に分類されます。
- 購入型
- 寄付型
- 融資型
- ファンド型
- 投資型
- ふるさと納税型
選ぶ型によっては、目標金額達成に至らなければ1円も資金調達できないケースもあるため、成功につなげるためには適切な方法を選ぶことが必要です。
なお、クラウドファンディングに関しては、以下の記事を参考にしてください。
クラウドファンディングとは?やり方やメリット・デメリットを簡単に解説
⑨ファクタリング

会社設立時の資金調達方法9つ目は、「ファクタリング」の利用です。
「ファクタリング」とは、事業間で行う商取引で発生した売掛金を、ファクタリング会社に売って現金化する資金調達サービスです。
入金までの期間、先に計上した売上の未回収分は「売掛金」で処理します。
売掛金は「売掛債権」という資産の1つであり、ファクタリング会社に売ることで、早ければ最短即日で売掛金が現金化されます。
お金を借りる方法ではないため、借金を増やすわけではなく、当然、担保や保証人も必要ありません。
さらにファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されるため、未回収の信頼性の高い債権を保有していれば、赤字決算や債務超過でも資金調達に活用できます。
ただし売買手数料が高めで、調達可能な金額は売掛金額までに留まることはデメリットです。
なお、ファクkタリングに関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
⑩補助金・助成金

会社設立時の資金調達方法10個目は、国や自治体の「補助金」や「助成金」の活用です。
どちらも国や自治体が支給する資金であり、返済義務を負うことなく資金調達できる方法といえます。
「助成金」は受給条件を満たすことでほぼ資金調達できるのに対し、「補助金」は政策推進において、もっともよい提案が採択されます。
受給条件を満たす場合でも、採択されなければ資金調達につながりません。
公募期間も、たとえば厚生労働省の助成金は通年など長期で募集しているのに対し、経済産業省系の補助金は募集開始から締切までたった数週間と短期募集です。
募集時期や条件なども変わることがあるため常に最新の情報を収集することが求められます。
会社設立でかかる費用

会社設立でかかる費用は、どの法人格を選ぶかによって異なります。
たとえば「株式会社」設立であれば、次の費用を準備しておくことが必要です。
- 印紙代(4万円程度)
- 登録免許税(15万円程度)
- 定款認証(3~5万円程度)
- 謄本発行費用(2千円程度)
以上の費用が必要となるため、実費のみで22~24万円はかかることになりますが、「合同会社」であれば10万円程度あれば設立できます。
ただ、会社を設立する以外にも、維持費用が必要です。
会社として事業活動する維持費として、たとえば次の費用が挙げられます。
- 事務所の家賃
- 事務所の水道光熱費
- 在庫管理費
- 人件費(給与・社会保険料・福利厚生費)
- 士業に対する顧問報酬
また、会社設立し法人として運営するのであれば、たとえ赤字でも一定額の税金を納めることが必要になります。
会社の税金は固定費として扱われることとなり、小規模も会社でも法人住民税の均等割7万円程度は発生すると認識しておきましょう。
具体的にどのくらい起業する上で資金が必要になるのか、事前に資金計画を立てておくことが必要です。
まとめ
会社設立時の資金調達の方法は、実際に事業を運営し、法人として実績を積んだ後よりも限定されます。
ただ、選べる種類が限りなく少ないというわけではなく、個人事業主よりも選択できる方法は多いといえるでしょう。
そのため、会社設立後の売上や収益の見込みなども踏まえた上で、どの資金調達方法を選ぶかしっかりと検討することが必要です。
また、実際に会社を設立し、事業を運営すると「売掛金」が発生することになります。
売掛金は期日まで現金化されない債権ですが、「ファクタリング」を使えば前倒しで資金調達に活用できます。
中小企業経営者向け!