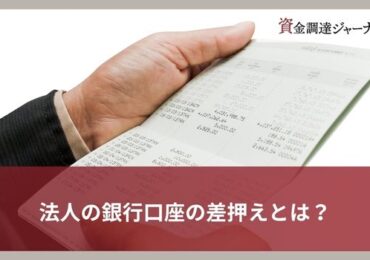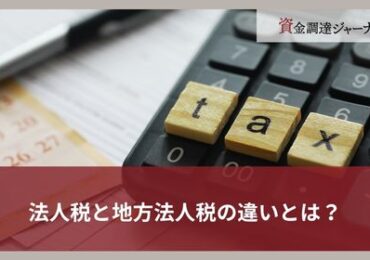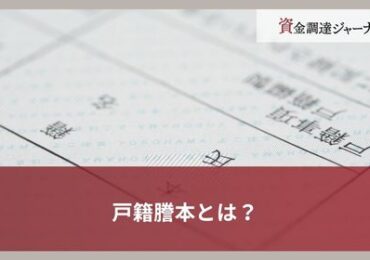個人事業主と法人は、事業を運営する上で様々な違いがあります。
当初は個人事業主として事業を営んでいた場合でも、事業拡大や税負担が増えるタイミングなどでの法人化を検討する例も多く見られます。
特に個人事業主と法人には税制面などで大きな違いがあるため、異なる部分を理解しておくと適切なタイミングでの法人成りも検討しやすくなります。
そこで、個人事業主と法人の違いや、法人化したほうがよいケースについて解説してます。
中小企業経営者向け!

個人事業主とは

「個人事業主」とは、会社を設立せずに税務署へ「開業届」を提出し、事業を営む方です。
一定の目的のもとで反復・継続して行う事業を、会社を立ち上げずに個人で営むケースといえます。
反復・継続・独立性の程度の定義は特にないものの、専業で事業を営んでいる方だけでなく、会社員として勤務先に所属しつつ副業で事業を営む方も含まれます。
個人で特定の団体に所属せず、単発の仕事ごとで契約を結び、請け負いで仕事をする「フリーランス」といった働き方もあります。
しかし個人事業主は税務署に開業届を提出し、継続して事業を営んでいることが違いです。
個人事業主は、会社設立など登記申請などは不要であり、特別面倒な手続が必要ないことが法人との違いといえます。
法人とは

「法人」とは、法務局で法人設立登記を行い、法人格を取得して法律上の人格に基づき事業を営む組織形態です。
個人事業主と同じく、権利・義務が認められた組織であり、「法」によって「人」と同じ資格を認められているため「法人」と呼ばれます。
法人格が対外的な窓口となるため、個人事業主であれば個人が取引先や銀行などと直接契約を結ぶのに対し、法人では会社が契約を結びます。
個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人は、次の12個の違いがあると考えられます。
- 事業開始の手続・費用
- 納める税金・税率
- 経費計上できる範囲
- 字の繰越期間
- 社会保険の加入義務
- 責任の範囲
- 社会的な信用力
- 資金の調達方法
- 事業維持にかかる費用
- 事業廃止する費用
- 業種による利便性
- 事業継承の手続方法
それぞれ説明します。
事業開始の手続・費用
個人事業主と法人の違いとして、事業を開始するときの「手続」の手間や「費用」が挙げられます。
まず個人事業主が事業をスタートする場合、所轄の税務署に「開業届」を提出すればよいため、特に面倒な手続はありません。
しかし法人の場合、法務局で登記申請の手続が必要であり、たとえば株式会社であれば約20万円、合同会社でも10万円程度の費用が発生します。
法人登記とは?個人事業主の法人化するメリット・デメリットを解説
納める税金・税率
個人事業主と法人の違いとして、納める「税金」の種類や適用される「税率」、赤字だったときの納税義務などが挙げられます。
収入から経費を差し引いた所得に応じて納税義務が発生する点は共通しているものの、個人事業主は「所得税」、法人は「法人税」を納めます。
また、所得税と法人税は「税率」にも違いがあります。
個人事業主の事業所得は最大税率45%の超過累進課税が適用されるのに対し、法人は最大税率23.2%と抑えられています。
たとえば個人事業主の所得が900万円以上の場合の所得税率は33%であるのに対し、法人税率は23.2%のままです。
ただし個人事業主は所得が発生しなければ所得税の納税義務はなくなるのに対し、法人はたとえ赤字でも法人住民税の均等割を少なくても年間7万円を納めなければなりません。
経費計上できる範囲
個人事業主と法人の違いとして、経費として計上できる「範囲」が挙げられます。
法人は、個人事業主が経費計上を認められている業務上の費用以外にも、以下の支払いを経費として扱うことができます。
- 役員報酬・賞与・退職金など
- 福利厚生費
- 健康診断費用
- 法人契約者の生命保険の保険料
- 出張の日当
- 社宅の家賃(会社名義の賃貸または購入物件を従業員等に貸し出した場合)
なお、交際費は個人事業主なら上限がないのに対し、法人(資本金1億円以下の中小企業)は年間800万円までなど、会社規模などでルールが設けられています。
企業の員即接待について、税務上の経費として扱うことのできる金額は、1人あたり5千円から1万円へと引き上げられています。
赤字の繰越期間
個人事業主と法人の違いとして、「赤字」で発生した欠損金を繰り越すことのできる期間が挙げられます。
個人事業主と法人はどちらも青色申告であれば、赤字決算により発生した欠損金を次年度へ繰り越せます。
しかしせ繰り越し可能となる期間は、個人事業主が翌年以後3年間であるのに対し、法人は10年間です。
長期的な視野で初期投資し、赤字が4年以上続く事業戦略を描いているのなら、10年間繰り越しできる法人のほうが有利と考えられます。
社会保険の加入義務
個人事業主と法人の違いとして、「社会保険」の加入義務が挙げられます。
まず個人事業主では、常時雇用する従業員が5人未満なら、社会保険へ加入する義務はありません。
しかし法人では、経営者のみの会社でも社会保険へ加入する義務が発生します。
社会保険料は労使折半であり、会社が半分負担することが必要となるため、書類手続の手間が増えるだけでなくコストもかかります。
責任の範囲
個人事業主と法人の違いとして、事業運営などにおける「責任」の範囲が挙げられます。
まず個人事業主は、事業における責任は「無限」といえます。
仮に事業目的でお金を借りたときには、個人の財産を持ち出しても返済する義務を負います。
しかし株式会社や合同会社などの法人の責任は「有限」であるため、事業を失敗したことによる負債を経営者が肩代わりする必要はありません。
出資していたお金は戻らないものの、連帯保証人などになっていないのなら出資金を超える範囲の責任の負担は不要です。
社会的な信用力
個人事業主と法人の違いとして、社会的な「信用力」が挙げられます。
まず個人事業主は、法人のように登記簿などで事業実態を把握できないため、経営が不安定といった印象を与えがちです。
しかし法人は、法務局で商業登記簿を取得し、事業実態を確認できます。
銀行融資においても、個人事業主と法人では、審査のハードルや融資可能額などが大きく異なります。
そのため、法人の方が社会的な信用力は高いといえます。
資金の調達方法
個人事業主と法人の違いとして、資金の「調達方法」が挙げられます。
株式会社なら、株式発行や社債発行による資金調達方法も利用できます。
個人事業主は、株式や社債を発行して出資してもらうことはできません。
銀行融資においても、先に説明したとおり審査の難易度や、調達額に差があります。
補助金・助成金・クラウドファンディングなどは個人事業主と法人のどちらも利用できるとはいえ、個人事業主のほうが条件は厳しいことがほとんどです。
以上により、資金調達においては法人の方が総合的に有利と考えられます。
個人事業主と法人の違いとして、事業を「維持」する上でかかる費用が挙げられます。
まず個人事業主は、事業維持でかかる特別な費用はありません。
しかし法人は、会社を設立した後も維持するいろいろな費用がかかります。
まず先にも説明したとおり、たとえ決算が赤字だった場合でも7万円程度は税金を納めなければなりません。
さらに社会保険料は半分負担が必要です。
事業廃止する費用
個人事業主と法人の違いとして、事業を「廃止」における費用が挙げられます。
まず個人事業主が廃業するときは、所轄の税務署に「廃業届」を提出すれば手続は完了します。
しかし法人は、法務局や税務署などで以下の手続を行い、費用を支払うことが必要です。
- 法務局で解散・清算人選任・清算結了など「登記」の申請(費用は約4万円)
- 税務署で「廃止届」の提出
- 年金事務所で「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」の提出
- ハローワークで「雇用保険適用事業所廃止届」などの提出
- 労働基準監督署で「確定保険料申告書」「労働保険料還付請求書」の提出
- 官報で解散の事実の公告(費用は約4万円)
手続でかかる費用は8万円ほどといえますが、司法書士など専門家に依頼すれば報酬が発生します。
そのため事業を廃止する場合、手間や費用は個人事業主よりも法人のほうが負担が大きいといえます。
業種による利便性
個人事業主と法人の違いとして、許認可などが必要となる「業種」による利便性が挙げられます。
起業・開業において、業種によって許認可が必要です。
たとえば建設業許可は、個人事業主と法人のどちらでも取得できるといえるものの、個人事業主の法人化では会社として再度取得しなければなりません。
また、個人事業主は事業主本人に対する許可であるのに対し、法人は会社に対する許可となるため、事業を引き継ぎに影響します。
再度取得の手間や費用もかかるため、届出・登録・認可・許可・免許などの種類で手続は異なるものの、一般的に法人の方が利便性が高いといえます。
事業承継の手続方法
個人事業主と法人の違いとして、「事業承継」における手続の方法などが挙げられます。
法人は事業承継において特別な手続はいらないのに対し、個人事業主は「人」が事業で収入を得ている扱いのため、資産の所有権を移転させることが必要です。
税務署に事業廃止届出書(承継側は事業開始届出書)を提出することや、資産の受け渡しにおける手続が必要となります。
特に個人事業主が他界したことで、相続が発生したときには相続人全員の同意がなければ事業の引き継ぎもできません。
預金口座も凍結され、必要な支払いなどできなくなる恐れもあります。
対する法人では、経営者が他界しても「会社」として事業を営んでいるため、事業自体は次の後継者へスムーズに引き継ぐことができます。
個人事業主を法人化したほうがよいケース

個人事業主と法人の違いを理解した上で、個人で事業を営むことから法人化へ転換させるべきケースとして、以下の3つが挙げられます。
- 年間課税売上が1,000万円を超える
- 年間所得が800万円を超える
- 多額資金の調達が必要である
それぞれ説明します。
年間課税売上が1,000万円を超える
個人事業主を法人化したほうがよいのは、年間課税売上が1,000万円を超えるタイミングです。
消費税の納税義務についての判断は2年前の年間の課税売上が基準となり、1,000万円を超えた場合には納税義務が発生します。
そのため2年前の年間課税売上が1,000万円を超えるタイミングで個人事業主から法人成りした場合、法人化した年が開業1年目とされます。
2年前の売上高は存在しないことになるため、消費税の納税義務を回避することができます。
ただし新設法人が消費税の納税義務を免除される免税事業者となるためには、以下の要件を満たす法人成りに限定されます。
- 設立時(第1期目)の期首資本金が1,000万円未満であること
- 第2期目も免税事業者になる場合は、上記の要件に加えて特定期間に以下のいずれかの要件を満たしている
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下である
年間所得が800万円を超える
個人事業主を法人化したほうがよいのは、年間所得が800万円を超えるタイミングといえます。
たとえば個人事業主の年間所得が700〜800万円までの所得税率は23%であるのに対し、資本金1億円以下の会社が同じ年間所得だった場合の法人税率は15%です。
個人事業主の所得税には累進課税制度が適用されているため、所得が増えれば増えるほど税率が高くなります。
しかし法人税は比例課税制度が採用されているため、一部の例外を除き所得にかかわらず税率は一律です。
以上のことから、年間所得700万円を超えるあたりで個人事業主から法人成りすることを検討したほうが、税負担を抑えられます。
多額資金の調達が必要である
個人事業主を法人化したほうがよいのは、多額資金を調達しなければならないときです。
事業規模を拡大する際、外部から資金を調達するのなら、社会的信用力の高い法人のほうが有利です。
株式会社であれば、株式発行による出資を受けることで、返済不要の資金を調達できます。
銀行融資を受ける際にも個人事業主よりも信用力が高いと判断されやすく、審査のハードルを下げられます。
法人のみが対象の補助金や助成金なども利用できるため、事業拡大などにおいて多額の資金が必要なときには法人化を検討するとよいでしょう。
まとめ
個人事業主と法人の違いは、独立して反復・継続による事業を営む個人が個人事業主であるのに対し、法人格を取得し事業営むのが法人です。
所得に応じて課税される税金も異なり、個人事業主法は所得税、法人は法人税と種類に違いがあります。
細かく説明すると、税金や税率以外にも、経費計上できる範囲や赤字を繰り越しできる期間などいろいろな違いがあるといえます。
社会的な信用力や事業経営における責任の範囲なども異なるため、個人事業主と法人、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選びましょう。
個人事業主が法人成りを検討するとよいタイミングは、年間課税売上が1,000万円を超えるときや年間所得が800万円を超える場合などです。
特に節税や資金調達などを検討しているときには、想定している効果を本当に得ることができるのか、シミュレーションした上での判断をおすすめします。
中小企業経営者向け!