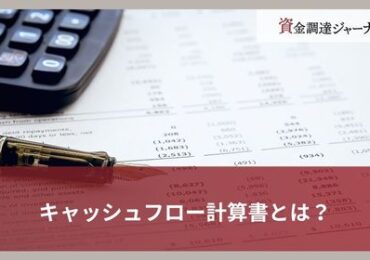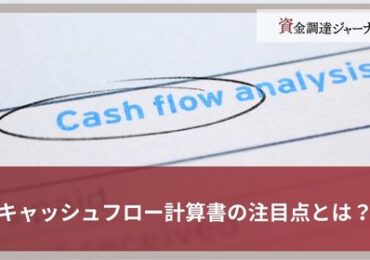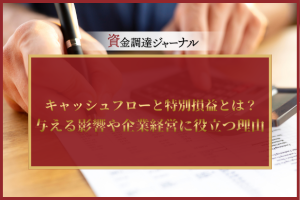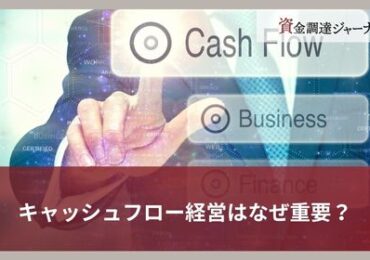売掛金は掛取引で商品を売った場合、それに対する代金を受取る権利で、販売対価の未回収額です。
反対に掛取引で商品を買った場合の債務が買掛金です。
そしてキャッシュフローは企業活動や財務活動により実際に得た収入、そして外部に対する支出という2つのお金を総称したものですが、売掛金の増加と買掛金の減少がキャッシュフローを圧迫することになります。
中小企業経営者向け!

売上に計上するタイミング
現金と引き替えて品物を渡す商売なら、売れたタイミングが入金日となり、そのまま売上額になります。
このように現金の流れと売上として計上するタイミングが同じなら問題ないでしょうが、一般的に掛けによる売上は、商品を納品する時点で売上として認識することが多く、これを引渡し基準といいます。
発生主義で計上した売上代金の請求権
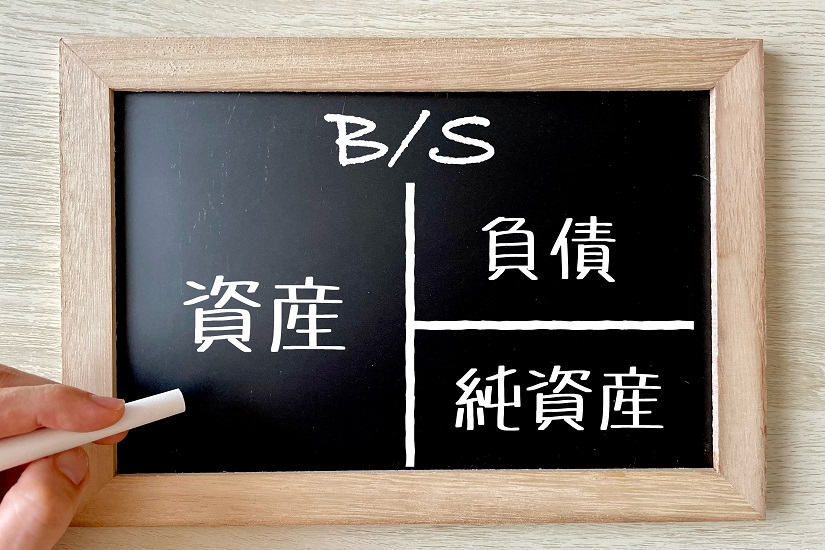
現金の動きに沿って行う現金主義とは異なり、取引が実際に発生した時に経理を行うことを発生主義会計といいます。
現金主義の場合には現金を受取るまで売上がないものと考えるために売上計上するタイミングが遅くなりますが、発生主義なら商取引の流れで売上計上することが可能ですので合理的に考えることができます。
この発生主義会計で計上した売上代金を請求する権利が売掛金です。
ただし売上計上して帳簿上は利益が出ていたとしても、売掛金を回収するまでは資金にはなりません。
利益と資金を算出した時のズレ
キャッシュフローにこの掛けが影響する理由は、まず利益と資金の算出方法から確認できます。
利益は売上から売上原価と経費を差し引いて算出したものです。
対して資金は入金から出金を差し引いたものになります。利益は収益から費用を差し引き算出しますが、資金は入金から出金を差し引くだけなのでズレが生じることになってしまいます。
具体的な例
例えば50万円で仕入れた商品を80万円で掛売りし40万円は回収。
さらに仕入れ代金は現金で支払ったという場合、利益は売上の80万円から仕入れ代金の50万円を引き30万円になります。
一方の資金は、売掛代金の入金40万円から仕入れ代金の50万円を差し引いてマイナス10万円になってしまいます。
損益計算書上の利益は30万円であるのに、実際には10万円不足していることになり、損益計算書の利益と資金を一致させるためには、売掛金残高の40万円を回収する必要があります。
支払条件の見直しがキャッシュフローを改善させる
このように売掛金が発生し残高が増えていけば次第にキャッシュフローを圧迫することになっていきます。
ただし掛売りした80万円を現金で回収し、仕入れ代金50万円の支払いまでの期間に余裕がある場合には買掛金として50万円が発生しますが、一時的に80万円が手元に残るため資金に余裕ができます。
このようにあるべく早く売掛金を回収し、なるべく遅く買掛金を支払うというような支払条件の見直しを行うことがキャッシュフローに大きく影響すると考えられます。
中小企業経営者向け!