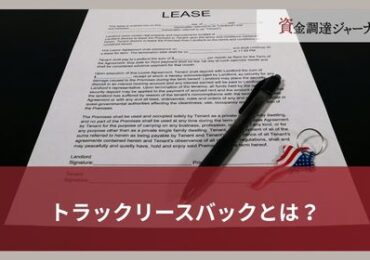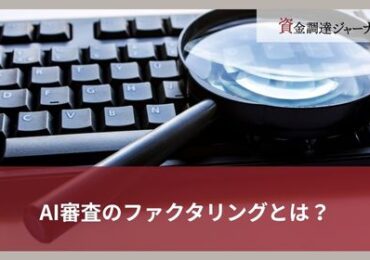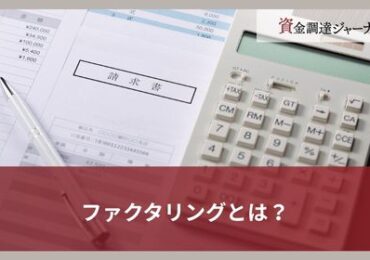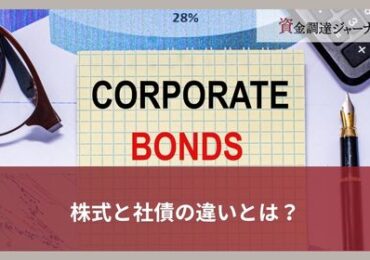資金繰り悪化で悩む中小企業などに最近注目されている「資本性劣後ローン」は、負債を増やさず資本を増強できるなど様々なメリットがあります。
そこで、資本性劣後ローンとはどのようなローン制度なのか、メリットとデメリットについてわかりやすく解説します。
中小企業経営者向け!

資本性劣後ローンとは

「資本性劣後ローン」とは、返済順位が劣後するローンであり、会社が法的倒産した場合の返済順位が後回しになることが特徴です。
法的倒産したときの債権は、民法で次の4つに分けられ、上から順番に回収が優先されます。
- 優先的破産債権(税金・社会保険料・従業員の給料など)
- 一般の破産債権(金融機関の借入金・買掛金など)
- 劣後的破産債権(破産手続開始後の利息・損害金など)
- 約定劣後的破産債権(劣後ローン・劣後債など)
銀行から融資を受けたときの借入金は2番目に回収される順位であるのに対し、資本性劣後ローンは4番目の最下位です。
債権者である金融機関にとって回収順位の低い「劣後」したローンであり、借入金であるものの形式的には資本金を強化した扱いになります。
また、毎月利息は返済することが必要になるものの、元金は期限一括返済となることも特徴です。
令和2年度第2次補正予算で盛り込まれた「中⼩企業向け資本性資⾦供給・資本増強⽀援事業」の1つに、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」があります。
コロナ禍で⼀時的に財務状況が悪化した中⼩企業などに対して、⽇本政策⾦融公庫や商⼯組合中央⾦庫など政府系金融機関の行う支援制度です。
なお、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業で次のいずれかに該当することが必要です。
- 「J-Startupプログラム」に選定された方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構(出資ファンド検索システム参照)が出資する投資事業有限責任組合(出資ファンド検索システム)から出資を受けた方
- 中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会を含む)の支援を受け事業再生を行う方、(「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」または「再生計画策定支援」を受けていることが必要)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(出資ファンド検索システム)の関与のもと事業再生を行う方(中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資または融資を受けた方)
- 上記に該当しない方で事業計画書を策定し民間金融機関等による支援を受けることができるなど支援体制が構築されている方(原則、融資後1年以内に民間金融機関等からの出資または融資で資金調達が見込まれることが必要)
なお、民間金融機関の協調支援を希望しない場合は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受け事業計画を策定することが必要とされています。
資本性劣後ローンと一般的な融資の違い

「資本性劣後ローン」とは、通常の銀行融資と異なり、借入れが資本とみなされるローンです。
一般的な銀行融資などの場合、借入金を増やし貸借対照表の負債を増加させるため、財務状況が悪化したと評価されます。
しかし資本性劣後ローンでは、負債ではなく資本を増やすため、資本増強による財務状況改善という評価を受けることができます。
また、資本性劣後ローンでは、持株比率の低下なども気にする必要なく、資本増強が可能です。
資本性劣後ローンで資金調達しても、負債はそのままで自己資本比率のみ増えるため、資金調達後は財務基盤が強化された評価を受けます。
さらに業績連動型の金利体系であるため、業績に応じた金利設定で資金繰りも楽になりやすいといえます。
借入期間中も利子のみ負担すればよいため、返済負担を抑えることができるなど、中長期的に資金繰りの安定化に寄与できます。
通常の融資と異なり、資本性劣後ローンであれば自己資本を強化・安定化しやすく、「劣後」と名称にあるとおり、他の債務よりも返済順位が低くなります。
万一法的倒産した場合でも、他の支払いが優先されるため、返済すべき順位を決めやすいローンです。
以上により、資本性劣後ローンと一般的な融資の違いをまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 資本性劣後ローン | 一般的な融資 |
| 対象者の違い | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人・個人企業など一定要件を満たす方 | 特に制限なし |
| 返済期間 | 5年1か月・7年・10年・15年・20年のいずれか | 5~35年など(審査により異なる) |
| 返済方法 | 期限一括返済(利子のみ毎月払い) | 毎月返済 |
| 利率 |
融資後3年間は0.5%(3年目以降でも赤字期間は0.5%) 黒字の場合は返済期間により異なる(5年1か月2.6%・7年2.6%・10年2.6%・15年2.7%・20年2.95%) |
0.9~3.5%(審査により異なる) |
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 | 担保の差し入れまたは人的保証が必要 |
| 借入金の扱い |
資産査定上自己資本とみなす 法人倒産では劣後する 融資後5年間は一括返済不可 |
負債が増える 法人破産で劣後せず経営者の自己破産につながりやすい 期限に関係なく繰り上げ返済できる |
資本性劣後ローンの活用場面
資本性劣後ローンは、売上減少で財務状況が悪化した場合において、通常の融資を受けられないときにも利用できます。
民間銀行で追加融資を受けたくても、審査に通らなければ資金調達はできません。
しかし資本性劣後ローンは、日本政策金融公庫などの政府系金融機関が、通常の融資で対応できない企業を支援するための制度です。
さらに調達資金は負債ではなく資本でカウントするため、資金繰りを安定化させつつ資本増強も図り、追加融資を申し込むことも可能となるでしょう。
資本性劣後ローンのメリット

「資本性劣後ローン」は、通常の銀行融資と違った特徴があり、利用することには次の5つのメリットがあるといえます。。
- 自己資本とみなされる
- 担保や保証人は不要
- 返済負担が軽減される
- 業績悪化で金利が安くなる
- 返済計画を立てやすい
それぞれのメリットを説明します。
①自己資本とみなされる
資本性劣後ローンのメリットとして、「自己資本」とみなされることが挙げられます。
借入れにより調達した資金は、会計上は「長期借入金」として計上し、負担した利子は「支払利息」として計上します。
ただし資本性劣後ローンの場合、金融検査上は自己資本とみなされることが特徴です。
疑似的に自己資本比率を向上させ、資本増加による財務基盤が強化と評価されることがメリットといえます。
実質的には借金であるものの、銀行など金融機関では自己資本としてみなされるため、追加融資に影響を及ぼすことがありません。
②担保や保証人は不要
資本性劣後ローンのメリットとして、「無担保」「無保証人」で借入れできることが挙げられます。
一般的な銀行融資の場合、不動産を担保として差し入れることや、経営者など代表者の人的保証を求められがちです。
しかし日本政策金融公庫などの政府系金融機関の資本性劣後ローンでは、担保や保証人は不要であるため、不動産などの資産がなくても利用できます。
③返済負担が軽減される
資本性劣後ローンのメリットとして、「返済負担」が軽減されることが挙げられます。
その理由は、資本性劣後ローンは「期限一括弁済」だからです。
借入期間中の支払いは利子のみであるため、一般的な元利均等払いや元利均等払いのローンのように、毎月の返済負担に苦しむことはありません。
また、毎年直近決算の業績に応じた金利設定であり、業績が回復していなければ0.5%の金利が適用されます。
返済額が圧迫する可能性も低く、中長期で資金繰りを安定させやすいでしょう。
ただし元金を期限一括弁済しなければならないため、一括で支払うタイミングに合わせた返済資金の確保は必要です。
④業績悪化で金利が安くなる
資本性劣後ローンのメリットとして、業績悪化で「金利」が安くなることが挙げられます。
先にも述べた通り、資本性劣後ローンは毎年直近決算の業績に応じた金利設定となります。
融資後3年間は0.50%であり、融資後3年経過した後は毎年の直近決算の業績に応じた利率のため、赤字続きであれば安い金利が適用され続けます。
赤字経営で大変なときこそ、適用される金利が低いことはメリットといえます。
⑤返済計画を立てやすい
資本性劣後ローンのメリットとして、「返済計画」が立てやすいことが挙げられます。
万一会社が法的倒産した場合、「劣後」されるローンであるため、他の借金より返済の優先順位は低くなります。
返済しなければならない支払いを先に、資本性劣後ローンは後回しにできるローンとして返済計画を立てやすくなることもメリットといえます。
資本性劣後ローンのデメリット

メリットの多い資本性劣後ローンですが、次の4つのデメリットには留意しておく必要があります。
- 適用条件を満たすことが必要
- 審査が厳しい
- 一括返済が必要
- 業績好転で利子負担が増える
それぞれのデメリットを説明します。
①適用条件を満たすことが必要
資本性劣後ローンのデメリットとして、「適用条件」を満たすことが必要であることが挙げられます。
先にも述べたとおり、資本性劣後ローンの対象者は日本政策金融公庫の概要にある適用要件を満たす方です。
なお、一定の要件を満たさなければ利用できないことはたしかにデメリットといえます。
ただし、事業計画書策定と、民間金融機関等による支援を受けられる支援体制が構築されていれば申請はできます。
資金調達コンサルタントのアドバイスなど受けながら、申請を検討してみましょう。
②審査が厳しい
資本性劣後ローンのデメリットとして、「審査」が厳しいことが挙げられます。
万一法人が法的倒産した場合、回収順位は最下位となるローンであるため、金融機関側も一般的な融資より高い信用力を求めます。
資本性劣後ローンの申請では、事業の種類や規模は問われないものの、通常の融資と違って特約締結義務が課されます。
この特約締結義務は、四半期ごとに経営・財務状況の報告などを含む資料提出の義務です。
他の提出資料よりも詳細な内容が記されるため、厳格な審査であると考えられます。
また、今後10年に渡る事業計画書を作成し提出しなければならないため、中長期の事業計画書作成は大きな負担になります。
③一括返済が必要
資本性劣後ローンのデメリットとして、元金は「一括返済」が必要であることが挙げられます。
毎月の返済は利子のみであり、返済負担が軽減されることはメリットであるものの、期限一括弁済のあるためまとめて元金を返さなければなりません。
借入期間が終了する前に、弁済する資金を用意しておかなければならないのはデメリットです。
毎月の返済負担に苦しむことはない一方で、数年または数十年先の一括弁済資金準備に苦しむ可能性は否定できないのはがデメリットといえます。
④業績好転で利子負担が増える
資本性劣後ローンのデメリットとして、業績好転で「利子負担」が増えることが挙げられます。
もともと資本性劣後ローンは、一般の銀行融資と比較したときの返済可能性は低めであるため、金融機関もそのリスクに応じた高い金利を設定します。
それでも赤字など業績悪化しているときの金利は低いため、利子負担が厳しいと感じることはないといえます。
ただし借入れから4年目以降に黒字化した場合、一般的な銀行融資よりも金利は高めです。
原則5年間は期限前返済できないため、高い利率で返済することになります。
赤字経営なら0.5%の低金利の適用で返済額を抑えることができる一方で、経営が黒字化した場合には注意が必要になることはデメリットといえます。
借入期間を長期で設定した場合、利子負担が過大になる可能性もあることは留意が必要です。
まとめ
財務状況が悪化してしまい、現在でも業績が回復しない中の物価上昇などで厳しい環境にある中小企業は少なくありません。
銀行から融資を受けて負債が増えれば、財務状況をより悪化させ、その後の追加融資など期待できない可能性があります。
しかし資本性劣後ローンなら、資本的な性格を持ったローンであるため、借入れをしても自己資本としてみなされ評価を下げません。
金融機関が経営再建計画の一環として、融資を資本的劣後ローンに転換している場合には、資本とみなすことができる制度です。
なお、資本性劣後ローンで資金調達するまでの間に資金ショートしそうな場合は、売掛金を現金化するファクタリングの検討をおすすめします。
中小企業経営者向け!