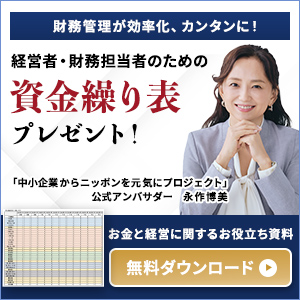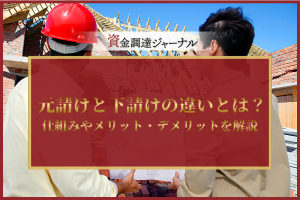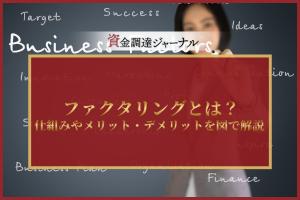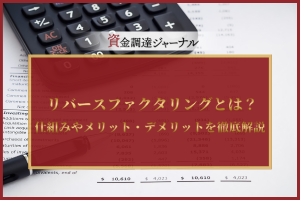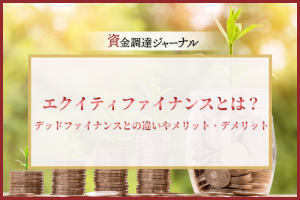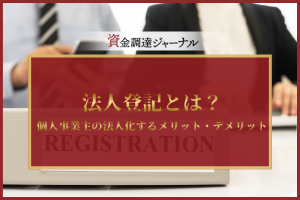元請けとは、発注者から直接仕事を請け負う業者であり、請負契約の一次請負事業者です。
正式には元請負人と呼ばれる存在であり、建設業界などでは重層下請構造による請負契約が慣習化しているため、元請けと下請けを存在させます。
しかし重層下請構造は、川下に行けば行くほど安価に仕事を請け負わなければならないなど、いろいろな問題があるとされています。
そこで、元請けと下請けの違いや仕組み、メリットとデメリットを解説します。
建設業の経営者向け!
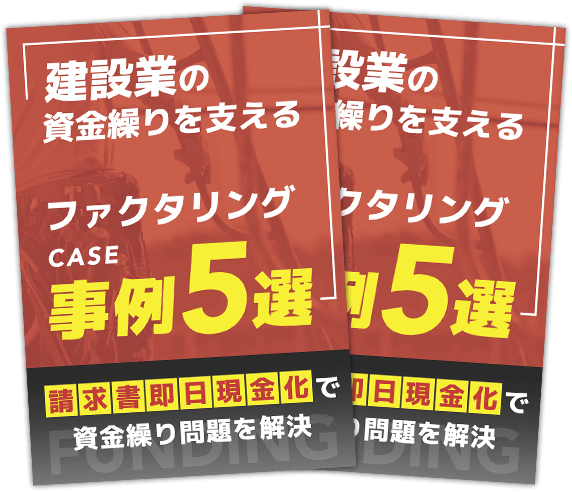
建設業の資金繰りを支えるファクタリング事例5選
建設業の経営者・財務担当者のために、実際に当社をご利用いただいた事例をもとに、ファクタリングの利用のタイミングなどを詳しく解説した資料です。
元請けとは
「元請け」とは、発注者から直接仕事の依頼を請けた企業です。
たとえば総合請負業を営むゼネコンは、元請けの建設会社として各種土木や建築工事を発注者から直接請負います。
請負った工事一式の全体を取りまとめる役割を担い、完工した建設物を引渡すことや維持管理なども担当します。
なお、建設業として仕事を請け負うときは、軽微な建設工事以外、建設業許可が必要です。
建設業法に基づく国土交通大臣や都道府県知事の「建設業許可」には、「一般」と「特定」があります。
「一般」の場合は軽微な建設工事のみ受注できるのに対し、発注者から直接4千万円(建築工事業は6千万円)以上の工事を請け負うには「特定」の許可が必要です。
下請けとは
「下請け」とは、元請けと契約を結び、仕事を請ける企業または個人事業主などです。
仕様書に従い、資材・工具・機械などを自前で準備することになり、工法などは元請けの指示に従います。
「発注者」→「元請け」→「一次下請け」→「二次下請け」…
と仕事が次々に依頼されることが多いものの、下請けの次数が増えるほど途中でマージンが徴収されるため受け取れる金額は少なくなります。
元請けと下請けの違い

建設業界で見られがちなのが、複数の下請企業で形成される「重層下請構造」による請負いです。
重層下請構造は、以下のとおり複数の下請けでピラミッド型の請負契約のもと、形成されます。
|
建設業界では、元請けが請け負った仕事を次々に下請け企業に発注する形態が常態化していますが、元請けと下請けには次の違いがあるといえます。
- 発注者
- 指示系統
- 請負金額
それぞれの違いを説明します。
発注者
元請けと下請けで根本的に異なる部分は「発注者」です。
まず元請けが受注契約を結ぶ相手は「発注者」であるのに対し、下請けが契約する相手は「元請け」といえます。
下請けが発注者と関わることはなく、あくまでも現場で作業を担当します。
なお、元請けが請け負った工事を下請けに丸投げする「一括下請負」は禁止されています。
指示系統
元請けと下請けで根本的に異なる部分は「指示系統」です。
まず元請けは、発注者の指示に従うのに対し、「下請け」は元請けの指示に従い作業を進めます。
請負金額
元請けと下請けは、「請負金額」に違いがあります。
まず元請けは、発注者から多額の請負金額で仕事を請け負います。
しかし実際に現場で仕事をするのは、元請けから依頼された下請けの業者です。
重層下請構造は、元請けの仕事を受注する一次下請けだけでなく二次下請け、さらに三次・四次…と続きます。
二次下請けは、元請けから見たときの請負関係の立場です。
一次下請けから二次下請けに工事を発注するときにはマージンが差し引かれ、二次下請けから三次下請けに依頼するときも同様にマージンが引かれます。
そのため重層下請構造の下位に位置するほど、受注金額は少なくなり厳しい経営を強いられるといえます。
元請けのメリット

元請けとして発注者から直接仕事を請け負い、実際の現場の工事は下請けが担当することには、以下のメリットがあります。
- 有利な条件での契約が可能
- 自由な料金設定が可能
- 自社が対応できない仕事を受注可能
- 作業の効率化が可能
- 雇用にかかる固定費用削減が可能
それぞれの元請け側のメリットを説明します。
有利な条件での契約が可能
元請けは直接仕事を請け負う立場となるため、下請けより有利な条件で契約することができます。
工事の価格・工期・工事の進め方など、交渉の際に有利に話をしやすいといえます。
さらに顧客ニーズを直接聞くことができるため、事業を進めていく上で改善しなければならない部分を把握しやすく、業務実績や宣伝効果も期待できます。
それに対し下請けは、元請けの契約を踏まえた受注となるため、金額や工法などの制約を受けやすくなってしまいます。
自由な料金設定が可能
元請けが発注者に対し見積もりを提示し、双方が納得すれば契約することになるため、自由に工事の料金を設定できることもメリットです。
下請けに仕事を発注するときの金額も元請けが設定するため、施工費用を抑えながら利益を得やすいといえます。
自社が対応できない仕事を受注可能
元請けは、受注した仕事を下請けに発注します。
そのため元請け企業の規模以上の業務や、自社では対応できない専門分野の工事を、下請けに依頼することで幅広い業務を請け負うことができます。
大規模工事を受注するため、企業共同体(JV)を設立するなど面倒な手続も不要です。
作業の効率化が可能
工事を受注するときには、現在の予定の中で空いている日を作業日程に充てられるか検討し、判断します。
しかし下請けへの発注を前提にした場合、自社の都合を優先させた工期設定も可能であり、作業効率を向上させられます。
建設機械や工具の準備や建設資材の購入も自社使用分のみの負担となり、効率的に作業を進めることができます。
スケジュールや規模に合わせながら自社の仕事分は確保し、下請けに回さず利益を確保するできるなど、臨機応変な対応も可能となることがメリットです。
雇用にかかる固定費用削減が可能
元請けは工事の規模によって、仕事を下請けに発注できます。
自社で人を雇用せず、人件費を抑えながら作業効率を高められます。
人を雇用した場合、基本給・各種保険・拠出金など、法定福利費の事業主負担分が発生します。
労働力を増やせるメリットがある反面、毎月負担が必要などコスト面で大きな負担を負います。
しかし下請けに仕事を発注することで、浮いた人件費を営業活動・企画・開発費用などに充てられるなど、現場は下請けに任せつつ固定費を抑えた経営ができます。
元請けのデメリット
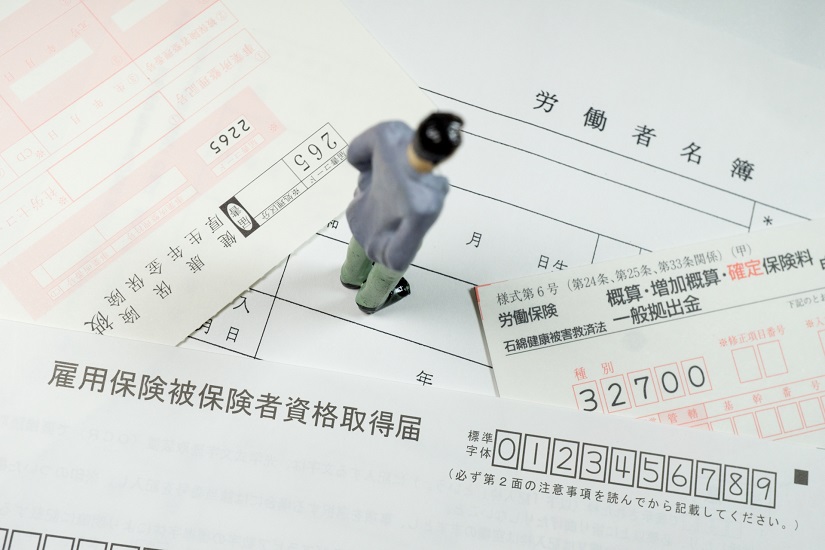
元請けとして仕事を受注できるため、利益を生みやすくなるなどのメリットがあります。
しかし仕事の責任はすべて元請けになることはデメリットです。
元請けは注文者から仕事を請けた受注者のため、発生したミスや事故は全責任を負います。
たとえば現場で工事中に事故が起きたときのための労災保険は、下請け分も元請けが一括で加入手続します。
現場で労災事故が発生すれば、元請けの労災保険で補償されます。
労働環境を整備することや、周辺住民から発生した苦情に対応することも元請けの仕事です。
施工ミスや完成後に生じた不具合なども、窓口となるのは仕事を受注した元請けであり、下請けに発注したため自社が担当していなかった工事でも受注責任を果たさなければなりません。
下請けのメリット

元請けから仕事を請け負う下請けの場合、重層下請構造の下位層に位置するほど、損をするといった印象を抱いてしまいがちです。
確かに途中でマージンなど差し引かれれば、実際に受け取ることができる金額は少なくなるものの、下請けとして仕事を請け負うことには以下のメリットがあります。
- 営業費や開発費を抑えることが可能
- 労力を抑えることが可能
- 一定量の業務確保が可能
それぞれのメリットを説明します。
営業費や開発費を抑えることが可能
下請けとして仕事を受注するメリットとして、まず営業費用や開発費を抑えつつ、一定量の仕事を確保できることが挙げられます。
中小の建設業は下請けとして仕事をすることが多いものの、営業費用や開発費などを十分確保できる資金力はありません。
しかし元請けからの仕事を請け負えば、営業や宣伝の活動に力を入れずに済みます。
営業や広告宣伝費などにお金をかける必要がなくなり、営業担当者に支払う人件費や活動費なども抑えることができます。
労力を抑えることが可能
下請けは元請けから仕事を発注してもらうため、自社が企画や開発を行う必要がなく、それにかかる労力や費用を抑えられます。
大手の建設会社なら、資金や労力も豊富なため、企画や開発なども行いやすいといえます。
中小の建設業は、企画や開発に資金や労力をかける余裕はありません。
そのため元請けから仕事を請け負うことで、新たな工法の指導を受けることや、業務以外に労力をかける必要がなくなります。
一定量の業務確保が可能
下請けは自社で営業をかけずに、元請けから仕事を回してもらえるため、一定量の業務を確保できることはメリットです。
元請けと長期的に取引することで資金繰りの目途も立ちやすくなり、収入の見込みが発生するなど業績も安定します。
下請けとして活躍する建設業は、主に土木・内装など専門性が高い業者であることが多いといえます。
ただ、直接発注者から仕事を受注できる機会が少ないため、元請けから仕事を回してもらえるで効率的に収益を上げられます。
下請けのデメリット

下請けは発注者と交渉ができないため、取引条件を変えることは不可であり、元請けの業績が悪化すればその影響を受けます。
工事中に何らかのアクシデントが発生し、元請けに提出した見積もりを超えたコストがかかる場合も、取引条件を変更できなければ赤字で工事を進めなければなりません。
これらを踏まえ、下請けとして仕事を請け負うことのデメリットは次の3つです。
- 取引条件を変更できない
- 元請けの業績低下が売上や受注量に影響する
- 突然仕事を打ち切られるリスクがある
それぞれのデメリットを説明します。
取引条件を変更できない
下請けは元請けと契約を結ぶため、仮に工事の途中で追加費用が発生しても、取引条件を変更できません。
まず建設工事は天候などの影響を受けやすく、雨や雪、台風などの影響で工期が遅れてしまうことはめずらしくありません。
しかし納期に間に合わせるため、時間外や休日の労働も必要となり、人件費も増えます。
さらに材料や機械の費用は下請けが負担するため、当初の見積もりと異なる材料費や機械のレンタル費用などがかかっても、取引条件を変えることはできず負担が増えます。
元請けの業績低下が売上や受注量に影響する
下請けは、元請けから発注された仕事を請け負うことで収益を上げています。
仮に元請けの業績が下がれば、下請けの売上も減少します。
営業活動をせず、一定量の仕事を確保できることは下請けのメリットです。
その反面、元請けから仕事が依頼されなくなれば、下請けの仕事もなくなります。
下請けが自前で営業活動する資金や労力の余裕もなく、取引先や仕事を失ってしまいます。
突然仕事を打ち切られるリスクがある
元請けと下請けは、仕事を発注する立場と請け負う立場であるため、取引上は元請けのほうが優位です。
そのため元請けから無理を強いられることや、突然仕事を打ち切られるリスクも抱えます。
必ず同じ下請けに仕事を回してくれるとは限らず、どれほど高い技術力で正確に仕事をしていたとしても、元請け側の何らかの都合で突然取引が停止してしまうとも考えられます。
将来を見通した経営計画を立てにくくなれば、資金繰りも不安を抱えた状態となるでしょう。
元請けと下請けが契約するときの注意点
元請けがどの下請けに仕事を依頼するか決めるとき、たとえば金額の設定や安全管理などを比較します。
下請けは仕事をできるだけ多く獲得しようと、能力以上の業務を受注しようとしたり無理をしたりといった傾向もみられます。
しかし下請けの能力と仕事が見合わず、無理が生じていたために事故が起こったとしても、その責任を問われるのは元請けです。
そのため元請けは、仕事を依頼する下請けについて、以下に配慮しながら選定を行います。
|
契約では何を重視されるのか、事前に把握しておくと安心です。
まとめ
元請けと下請けは、仕事を発注する側と受注する側という違いがあります。
建設業・造船業・鉄鋼業では、重層下請楮が一般的な形態であり、下請けや孫請けという立場であるが故の問題を抱えています。
特に古くから続く建設業界の過度な重層下請構造は改善には至っておらず、ブラックボックス化している状態です。
元請けと下請けの関係を適正化させるため、国土交通省も「建設業法令遵守ガイドライン」も公表しています。
重層構造を改善させることで、生産性を高め分かりやすい施工体制を作ることができるでしょう。
建設業の経営者向け!
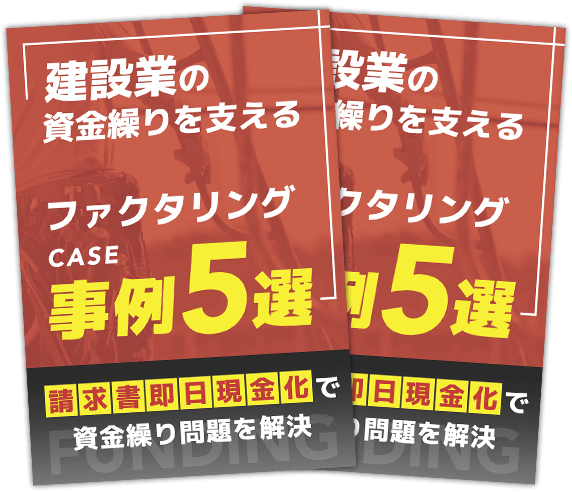
建設業の資金繰りを支えるファクタリング事例5選
建設業の経営者・財務担当者のために、実際に当社をご利用いただいた事例をもとに、ファクタリングの利用のタイミングなどを詳しく解説した資料です。