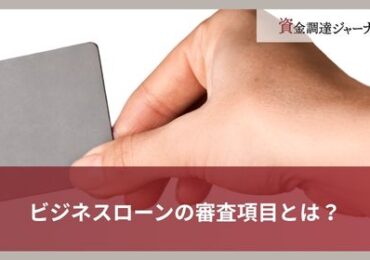「抵当権」や「根抵当権」は、どちらも設定されれば登記簿に記録されるため、担保として差し入れる必要がなくなったときには解除手続が必要です。
解除手続しないまま、抵当権や根抵当権が設定されたままの不動産を売ろうとしても、買い手は見つかることはありません。
銀行からお金を借りるとき、不動産などを担保として差し入れることで、「抵当権」や「根抵当権」が設定されます。
そこで、抵当権と根抵当権はそれぞれどのような権利なのか、2つの違いや解除するための抹消手続の流れを解説します。
中小企業経営者向け!

抵当権とは

「抵当権」とは、お金を借りる債務者が、万一返済できなくなった場合に備えて不動産を担保として差し入れる際の権利のことです。
債務者の返済が遅れた場合に備えて、不動産などを担保として取得しておけば、担保物件は他の債権者より優先して弁済を受けられます。
お金を貸す債権者は、債務者が約束通りに返済しない場合、抵当権を実行して差し押さえることができます。
抵当権実行により差し押さえられた土地や建物などは競売にかけられ、売却代金を返済に充てられます。
なお、抵当権は特定の借入れに対する担保設定であるため、対象となる借金を完済すれば、抵当権の抹消登記により解除できます。
根抵当権とは
「根抵当権」とは抵当権の1つであり、特定の債権を担保するのではなく、限度額を定めて一定範囲で複数の債権を担保する権利です。
継続的な取引関係からの債権を担保するために、一定の限度額をあらかじめ定めておき、将来確定する債権をその範囲で担保します。
そのため抵当権は、1つの借入れが完済するまで設定されるのに対し、根抵当権は同じ金融機関から同じ不動産を担保に繰り返し融資を受ける場合に設定されます。
根抵当権では極度額を決定するため、その範囲であれば自由に借入れができます。
抵当権と根抵当権の違い

抵当権と根抵当権の違いは、主に次の4つです。
- 対象となる債権の範囲
- 抹消義務の有無
- 優先弁済権の範囲
- 連帯債務者の扱い
それぞれ説明します。
対象となる債権の範囲
抵当権と根抵当権では、対象となる債権に違いがあります。
まず抵当権の場合、1つの債権に対して1つの抵当権を設定します。
抵当権の設定では極度額は設定されることはなく、繰り返し借入れすることは予定されていないため、融資実行は原則1回のみです。
対する根抵当権では、債務者と債権者との間で債権の種類を決め、担保として差し入れる不動産の評価額から借入れ上限額である「極度額」が設定されます。
たとえば次のように根抵当権を設定したとします。
- 極度額:5千万円
- 債権の範囲:金銭消費貸借取引・小切手債権・手形債権
この根抵当権設定では、金銭消費貸借契約で融資を受けることや手形貸付については、5千万円の範囲であれば何度でも担保されまます。
何度でも極度額を上限に担保とすることで、その範囲であれば自由に借入れが可能になる契約です。
抹消義務の有無
抵当権は、特定の債権を担保するために設定されます。
そのため、担保した債権が全額返済されることで、抵当権も消滅します。
対する根抵当権の場合、極度額の範囲内で繰り返しお金を借りることが予定されています。
そのため借入れ額がゼロになった場合でも、根抵当権そのものは消滅しません。
抵当権は、完済により抹消登記をすれば解除できるのに対し、根抵当権は完済しても抹消されず、解除手続においては債権者との合意が必要です。
根抵当権は反復した借入れが前提になるため、完済しても自動的に抹消されず、抵当権よりも面倒な手続が必要になります。
優先弁済権の範囲
「優先弁済権」とは他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利ですが、抵当権と根抵当権はどちらも優先弁済権が認められています。
ただし抵当権では、実行による優先弁済件の範囲は、元本と最後の2年分の利息・その他定期金・遅延損害金とされています。
最後の2年とは、競売の配当実施日から遡って2年とするため、利息・その他定期金・遅延損害金は通算2年分までしか請求できません。
これに対し、根抵当権では、最後の2年分という制限がないため、元本はもちろんのこと利息・その他定期金・遅延損害金も極度額を上限に優先して弁済を受けられます。
連帯債務者の扱い
「連帯債務」とは、1つの借入れを複数の者それぞれ全額債務を負うことです。
抵当権の場合、連帯債務者は認められるのに対し、根抵当権では認められません。
その理由として、抵当権の設定する債権は明確であるのに対し、根抵当権では極度額の範囲で借入れができるため、借入れと返済の時期が明確化されず連帯債務しにくいことが挙げられます。
抵当権設定までの流れ

担保として差し入れる土地や建物などに、抵当権または根抵当権設定を設定する流れは以下の3つです。
- 必要書類の準備
- 設定登記の申請
- 登記完了
融資を受ける際に抵当権を設定する場合、借入れの都度、上記の流れで手続が必要です。
しかし根抵当権を設定する場合には、最初に登記しておけば、その後の借入れで設定登記は必要ありません。
同じ不動産を担保として差し入れるときには、抵当権の設定・抹消を繰り返さなくて済むため、根抵当権を設定したほうが登記費用など安く抑えられます。
以上を踏まえて、上記3つの流れを説明します。
①必要書類の準備
抵当権を設定する際には、金融機関が抵当権設定契約書や司法書士の委任状など、一連の書類を準備することが多いといえます。
そのため融資を受ける借主側が準備するものは、以下の3点であることが一般的です。
- 土地・建物の所有者の実印
- 土地・建物の所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 土地・建物の登記済権利証または登記識別情報
②設定登記の申請
抵当権または根抵当権の設定登記は法務局(登記所)で行いますが、申請手続は司法書士が行います。
債権者である金融機関が提携している司法書士に依頼することがほとんどであるため、別途、専門家を探す必要はありません。
融資実行と同時に登記所で抵当権設定の登記申請が行われます。
登記申請においては、以下の2つの費用が発生します。
- 登録免許税
- 司法書士の報酬
登録免許税
「登録免許税」とは、登記をする際に納める税金であり、申請書に収入印紙を貼り付ける方法で納めます。
抵当権設定では、以下の計算式で算出した登録免許税を納めます。
|
抵当権設定登記にかかる登録免許税額 = 借入額 × 0.4%
|
たとえば3千万円融資を受けるための抵当権設定登記のおける登録免許税は以下のとおりです。
|
12万円 = 3千万円 × 0.4%
|
反対に抵当権を解除する際の登録免許税は、不動産1個につき1,000円が必要です。
司法書士の報酬
登記の申請など手続は、一般的に登記を専門とする司法書士に一任することが多いといえます。
この場合、司法書士に対する報酬が5~10万円程度は必要となります。
③登記完了
司法書士に登記申請を依頼した後、おおよそ1~2週間で登記手続完了を証明する「登記事項証明書」を取得できます。
抵当権・根抵当権の抹消方法
抵当権と根抵当権、どちらも不動産に設定されたままでは、その物件を売りたくても買い手はみつかりにくくなります。
そのため、抵当権と根抵当権はどちらを設定している不動産の場合でも、売却する際には解除するための手続が必要です。
そこで、抵当権と根抵当権それぞれの抹消方法について説明します。
抵当権の抹消方法
抵当権が設定されている場合、借りているお金を完済することにより、権利自体は消滅していると考えられます。
ただ、登記簿上の表示として抵当権が残ったままとなるため、解除するための抵当権の抹消登記を行いましょう。
「抵当権」の解除については、金融機関から受け取った登記抹消に必要な書類により、法務局で申請すれば問題ありません。
抹消登記の申請は比較的簡単なので、法務局の公式サイトなどを参考に、自身で行うこともできます。
また、多くの場合には、債権者だった金融機関が抹消手続まで行います。
根抵当権の抹消方法

問題なのは「根抵当権」の抹消です。
抵当権と違って自動的に消滅せず、債権者の合意を得て抹消手続することが必要となるため、次の流れで手続しましょう。
- 債権者との交渉
- 元本の確定
- 抹消登記の申請
それぞれ解説します。
①債権者との交渉
根抵当権の抹消手続においては債権者の合意を得ることが必要となるため、残債や査定価格など債権者である銀行に確認し、抹消してもらえるように交渉しましょう。
たとえば根抵当権が設定されている不動産の売却代金により残債を返済することを検討しているなら、不動産の残債や査定価格から、売ったときの代金が残債を上回ることを伝えて交渉します。
②元本の確定
金融機関との交渉が進んだ段階では、元本を確定することが必要です。
根抵当権の抹消前には、債権者と債務者の合意により元本確定という手続を行い、不動産を担保としてどのくらい借りているか確定させます。
根抵当権は何度でも繰り返し融資を受けることができる特性がありますが、元本確定によって極度額の範囲内での借入れはできなくなり、抵当権と同じ扱いとなります。
元本確定とは、「いつ」までにどのくらい「金額」を返済しなければならないのか、その義務を確定させることです。
なお、債権者(根抵当権者)である銀行が、確定請求することで期日を確定することもできます。
確定請求は銀行などが根抵当権を設定した時点で確定期日を定めていない場合に元本確定を請求する制度です。
たとえば、担保として差し入れてもらった不動産の価値が下落したため、根抵当権の担保としての融資はできないなどの理由により、元本を確定させたいときに請求されます。
③抹消登記の申請
根抵当権の元本確定後は、必要書類を揃えて法務局で根抵当権抹消の登記を行います。
抹消登記は自身で行うこともできますが、不安であれば司法書士などに依頼すると安心です。
抵当権・根抵当権の抹消登記で支払う登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
たとえば土地2筆の上に1個の建物が建っている場合において、抵当権を土地2筆と建物1個に設定していれば、登録免許税は3,000円必要となります。
さらに抵当権抹消登記では、以下のものが必要です。
- 抵当権抹消登記申請書
- 委任状(司法書士に委任する場合)
- 銀行からの抵当権抹消書類一式
抵当権を設定するときには、銀行が必要書類を一式揃えてくれることが多く、登記申請を依頼する司法書士も提携している専門家に一任することがほとんどです。
抵当権抹消の登記においては、銀行が提携している司法書士に依頼してくれる場合もあれば、完済したことを伝える書類一式が送られてくるのみという場合もあるかもしれません。
その場合、自身で抵当権抹消登記を手続するか、司法書士に依頼して代理で手続してもらうか選びましょう。
まとめ
抵当権は、設定した時点で対象の債権が明確になることが特徴であるのに対し、根抵当権は極度額の範囲で繰り返し借入れができるため、
- いつ
- どのくらいの金額を借りて
- いつ返済するのか
そのため連帯債務者を付けることは難しく、債務が完済されても自動的に抹消されることはありません。
根抵当権が設定されるのは、事業性の借入れなどが多いといえます。
完済しても、債権者である金融機関と交渉がまとまらなければ抹消することはできず、手続も複雑です。
今後借入れ予定がなくても抹消できなければ、担保がついたままの不動産を売ることもできないといったトラブルが起きる可能性もあります。
根抵当権抹消に関する同意を金融機関から得ることができれば、抹消登記はそれほど難しくありません。
そのため、抵当権・根抵当権のどちらを設定している場合でも、借りているお金を支払い終わった後は、早めに抹消登記を行いましょう。
中小企業経営者向け!